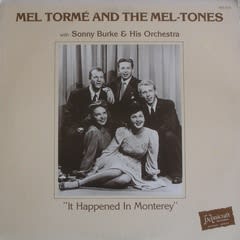When Lights Are Low / Kenny Burrell Trio
「タイトルは内容を表す」アルバムもよくある。
例えば、ジェリーマリガンのアルバムに”Night Lights”というアルバムがある。ジャケットの写真がビルの夜景をイラスト化したもので、都会の夜の雰囲気を感じさせる洗練された演奏だ。マリガンの良さが生かされていて自分も好きなアルバムだ。
このアルバムのタイトルは”When Lights Are Low”。ベニーカーターの有名な曲で名演も多い。このアルバムのジャケットもこのタイトルにぴったりのデザインだ。ケニーバレルがギターを抱え、明かりを落とした暖炉の傍でリラックスしてプレーをしている。隣に恋人でもいて彼女に向かって弾いていたりしたら、なお更雰囲気のあるシチュエーションだ。
アルバムに針を落としてもミディアムテンポからスローな曲が続く。ベイシーの演奏で有名なリトルダーリンも。バレルのオリジナルのブルース「ブルーミューズ」では、珍しくアコースティックギターも弾いている。
そして、B面にはバレルが尊敬するエリントンの曲も。最後にはベイシーに捧げてブルースで締めくくる。
この頃、Concordはこれまで自分のレーベルに登場したおなじみのギタリストのリーダーアルバムを続けて出している。カルコリンズ、レモパレミエリ、ハーブエリス、チャーリーバードといったように。
そして、今回はケニーバレル。コンコルドでは一年前に彼のデビュー曲である「ティンティンデュオ」をタイトルにしたアルバムを出しているのでリーダーアルバムとしては2作目になる。
今回もベースとドラムを加えたトリオ編成だが、プレーぶりはアルバムのタイトルに合わせてか得意のブルースもしっとりと聴かせている。
演奏、タイトル、曲、ジャケットと3拍子ならぬ、4拍子揃ったアルバムだと思う。
1. When Lights Are Low Carter, Williams 4:51
2. Body and Soul Elyton, Green, Heyman, Sour 6:25
3. Lil' Darlin' Hefti 5:28
4. Blue Muse Burrell 5:15
5. Ain't Misbehavin' Brooks, Razaf, Waller 4:58
6. It Shouldn't Happen to a Dream Ellington, George, Hodges 6:25
7. Blues for Basie Burrell 6:28
Kenny Burrell (g)
Larry Gales (b)
Cral Burnett (ds)
Carl Jefferson Executive Producer
Frank Dorritie Producer
Recorded in September 1978
Originally released on Concord CJ-83
「タイトルは内容を表す」アルバムもよくある。
例えば、ジェリーマリガンのアルバムに”Night Lights”というアルバムがある。ジャケットの写真がビルの夜景をイラスト化したもので、都会の夜の雰囲気を感じさせる洗練された演奏だ。マリガンの良さが生かされていて自分も好きなアルバムだ。
このアルバムのタイトルは”When Lights Are Low”。ベニーカーターの有名な曲で名演も多い。このアルバムのジャケットもこのタイトルにぴったりのデザインだ。ケニーバレルがギターを抱え、明かりを落とした暖炉の傍でリラックスしてプレーをしている。隣に恋人でもいて彼女に向かって弾いていたりしたら、なお更雰囲気のあるシチュエーションだ。
アルバムに針を落としてもミディアムテンポからスローな曲が続く。ベイシーの演奏で有名なリトルダーリンも。バレルのオリジナルのブルース「ブルーミューズ」では、珍しくアコースティックギターも弾いている。
そして、B面にはバレルが尊敬するエリントンの曲も。最後にはベイシーに捧げてブルースで締めくくる。
この頃、Concordはこれまで自分のレーベルに登場したおなじみのギタリストのリーダーアルバムを続けて出している。カルコリンズ、レモパレミエリ、ハーブエリス、チャーリーバードといったように。
そして、今回はケニーバレル。コンコルドでは一年前に彼のデビュー曲である「ティンティンデュオ」をタイトルにしたアルバムを出しているのでリーダーアルバムとしては2作目になる。
今回もベースとドラムを加えたトリオ編成だが、プレーぶりはアルバムのタイトルに合わせてか得意のブルースもしっとりと聴かせている。
演奏、タイトル、曲、ジャケットと3拍子ならぬ、4拍子揃ったアルバムだと思う。
1. When Lights Are Low Carter, Williams 4:51
2. Body and Soul Elyton, Green, Heyman, Sour 6:25
3. Lil' Darlin' Hefti 5:28
4. Blue Muse Burrell 5:15
5. Ain't Misbehavin' Brooks, Razaf, Waller 4:58
6. It Shouldn't Happen to a Dream Ellington, George, Hodges 6:25
7. Blues for Basie Burrell 6:28
Kenny Burrell (g)
Larry Gales (b)
Cral Burnett (ds)
Carl Jefferson Executive Producer
Frank Dorritie Producer
Recorded in September 1978
Originally released on Concord CJ-83
 | When Lights Are LowKenny BurrellConcord Jazzこのアイテムの詳細を見る |