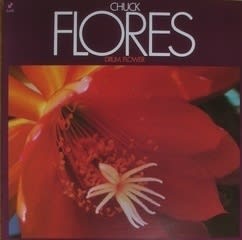Ruby and Woody / I had to be us
ラフな格好でリラックスした表情の2人。
「同窓会で久々に会った2人のスナップ」のような何の飾り気もないジャケットの写真だ。
二人とも「好好爺」という言葉にピッタリである。
ビッグバンドの両雄といえば、ベイシーとエリントン。
長い歴史の中で色々な苦難があったが、この2つのオーケストラはレギュラーバンドとして生き続けた。
これに負けていないのがウディーハーマンのオーケストラだ。
ベイシー、エリントンは基本的に自己のスタイルを変えなかったが、ウディーハーマンはメンバーも常に若い新しいメンバーを登用し時代に合わせて変化し続けた。
バップの誕生に合わせるようにスタートした彼のオーケストラ。“Herd”という名前が象徴するように、群れとなってその時代の先端の流れに切り込んでいった。
70年代の始めには、流行ったブラスロック風のハーマンも聴くことが出来る。
そんなハーマンも40周年の記念コンサートを経て、70年代の終わりにはストレートな演奏に戻っていった。
色々と気苦労の多いいつものオーケストラの活動を離れ、普段着で何気ない演奏を。
このアルバムは、ジャケットの写真の印象どおり、そんなアルバムだ。
相手を務めたのは、ルビーブラフのコルネット。
筋金入りのスイング派だ。Concordの初期のアルバムにも登場している。
ハーマンもここではクラリネットそしてボーカルで、それに合わせた演奏、そして歌を披露している。いつもは余興で一曲という感じであるが、ここではたっぷりとハーマンの歌を聴ける。
軽快なスイングのリズムに乗って、デビューした頃を思い出していたのかもしれない。
変な気負いもかければ、妙なブローも無い。
同窓会の流れで気の合った2人が、久々に昔を思い出して一丁やってみようかといったノリである。
ハーマンの晩年は、滞納していたバンドのメンバーの税金の支払いに追われていたとか。
必ずしも悠々自適な生活を送っていたのではなさそうだ。
どんなに苦労をしても、面と向かっては笑顔を絶やしたことが無かったといわれるハーマン。
ほっと一息ついた演奏に、これは本心からの笑みがこぼれてるのかもしれない。
東海岸のConcordともいえる“Chiaroscuro”。
なかなかアルバムを残している。
1. I Can't Believe That You're in Love With Me
2. Rose Room
3. Solitude
4. I Hadn't Anyone Till You
5. As Time Goes By
6. Sheik of Araby
7. It Had to Be You
8. There Is No Greater Love
9. Wave/Spain
10. I Cried for You
11. 'Deed I Do
12. Sheik of Araby, No. 2 [*]
13. Solitude, No. 2 [*]
14. It Had to Be You, No. 2 [*]
15. George Avakian Jazzspeak [*]
<Personnel>
Woody Herman (vocals, clarinet)
Ruby Braff (cornet)
John Bunch (piano)
Wayne Wright (guitar)
Michael Moore (bass)
Jake Hanna (drums)
Producer George Avakian
Engineer Jon Bates
Recorded in New York City,12&13,March,1980
ラフな格好でリラックスした表情の2人。
「同窓会で久々に会った2人のスナップ」のような何の飾り気もないジャケットの写真だ。
二人とも「好好爺」という言葉にピッタリである。
ビッグバンドの両雄といえば、ベイシーとエリントン。
長い歴史の中で色々な苦難があったが、この2つのオーケストラはレギュラーバンドとして生き続けた。
これに負けていないのがウディーハーマンのオーケストラだ。
ベイシー、エリントンは基本的に自己のスタイルを変えなかったが、ウディーハーマンはメンバーも常に若い新しいメンバーを登用し時代に合わせて変化し続けた。
バップの誕生に合わせるようにスタートした彼のオーケストラ。“Herd”という名前が象徴するように、群れとなってその時代の先端の流れに切り込んでいった。
70年代の始めには、流行ったブラスロック風のハーマンも聴くことが出来る。
そんなハーマンも40周年の記念コンサートを経て、70年代の終わりにはストレートな演奏に戻っていった。
色々と気苦労の多いいつものオーケストラの活動を離れ、普段着で何気ない演奏を。
このアルバムは、ジャケットの写真の印象どおり、そんなアルバムだ。
相手を務めたのは、ルビーブラフのコルネット。
筋金入りのスイング派だ。Concordの初期のアルバムにも登場している。
ハーマンもここではクラリネットそしてボーカルで、それに合わせた演奏、そして歌を披露している。いつもは余興で一曲という感じであるが、ここではたっぷりとハーマンの歌を聴ける。
軽快なスイングのリズムに乗って、デビューした頃を思い出していたのかもしれない。
変な気負いもかければ、妙なブローも無い。
同窓会の流れで気の合った2人が、久々に昔を思い出して一丁やってみようかといったノリである。
ハーマンの晩年は、滞納していたバンドのメンバーの税金の支払いに追われていたとか。
必ずしも悠々自適な生活を送っていたのではなさそうだ。
どんなに苦労をしても、面と向かっては笑顔を絶やしたことが無かったといわれるハーマン。
ほっと一息ついた演奏に、これは本心からの笑みがこぼれてるのかもしれない。
東海岸のConcordともいえる“Chiaroscuro”。
なかなかアルバムを残している。
1. I Can't Believe That You're in Love With Me
2. Rose Room
3. Solitude
4. I Hadn't Anyone Till You
5. As Time Goes By
6. Sheik of Araby
7. It Had to Be You
8. There Is No Greater Love
9. Wave/Spain
10. I Cried for You
11. 'Deed I Do
12. Sheik of Araby, No. 2 [*]
13. Solitude, No. 2 [*]
14. It Had to Be You, No. 2 [*]
15. George Avakian Jazzspeak [*]
<Personnel>
Woody Herman (vocals, clarinet)
Ruby Braff (cornet)
John Bunch (piano)
Wayne Wright (guitar)
Michael Moore (bass)
Jake Hanna (drums)
Producer George Avakian
Engineer Jon Bates
Recorded in New York City,12&13,March,1980