French Toast / French Toast
アルバムとの出会いは人それぞれ、人によってそのアルバムに対しての印象や思い入れは異なるものだ。
しばらく前に、サドメル&VJOのレパートリーだけを演奏するメイクミースマイルオーケストラのライブに行った。今年のライブのお題は「20周年」。このオーケストラの設立20周年記念ということであった。そして、その日のプログラムはこのグループの範とするメルルイスオーケストラの”20 Years at the Village Vanguard”のアルバムに収められている全曲であった。なかなか洒落っ気のあるプログラム構成であった。
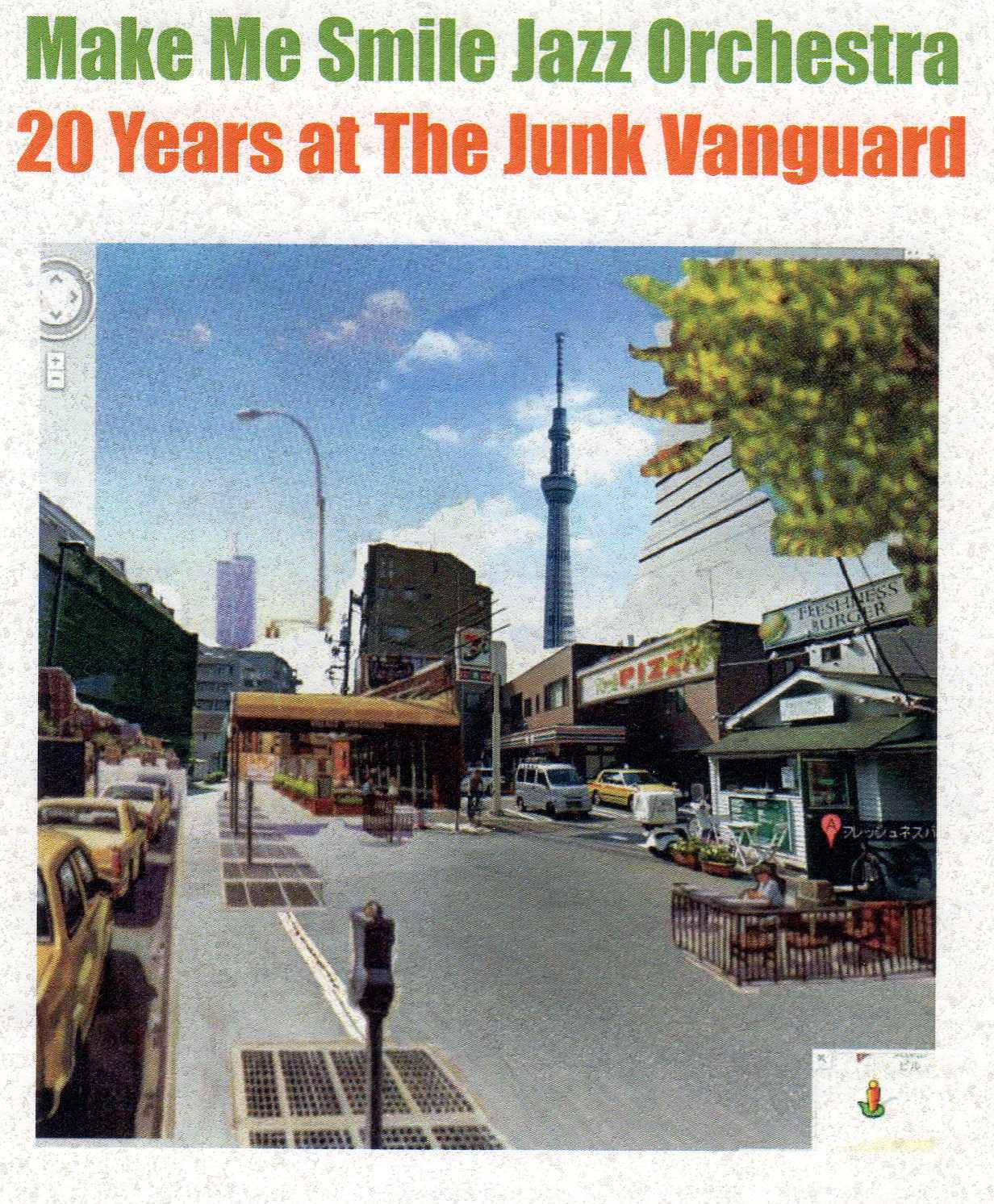
演奏の途中のMCの中で、その日のプログラムの元となったメルルイスオーケストラのアルバムのジャケットが紹介された。そして、次に登場したジャケットが、この“French Toast”のジャケットであった。一瞬、何でその場で紹介されたのか意味が分からなかったが、話を聞くとこのアルバムに収められている”Butter”という曲が、ジェリーダジオンの作曲で、このメルルイスオーケストラのアルバムにも収められているということであった。
このメルルイスのアルバムは1985年の録音、そしてフレンチトーストの録音は前年の1984年の録音。フレンチトーストの方が先に世に出ていたということになる。そして、このフレンチトーストにはジェリーダジオン本人も加わっていた。
サドメルのコアメンバーであったジェリーダジオンだが、サドメルのレパートリーでダジオンの作編曲は決して多くはない。サドメルファンとすれば、珍しいダジオンの曲のお披露目の場としてこのアルバム「フレンチトースト」が印象に残ったのであろう。
さて、自分にとって、このフレンチトーストというアルバムは?というと、ピアノで参加しているミシェルカミロのデビューアルバムとしての印象の方が強い。自分自身もサドメルファンでありながら、このアルバムにジェリーダジオンが参加していたのも忘れていたくらいだ。
当時のカミロ写真を見ると実に若い、まだ30歳になったばかり。ドミニカ出身のカミロがニューヨークに来たのが1979年。ジュリアードで学びプロとしての活動を始めた頃だ。この演奏を聴き返しても、ラテンの血とクラシックに裏打ちされたテクニックは今のカミロを予見させるような個性を感じさせる。
後に、カミロのトリオのメンバーとなった、ベースのアンソニージャクソン、ドラムのデビッドウェックルもこの頃から一緒に演奏していた仲間であったことが分かる。
そしてカミロの名曲Why Not?が収められているが、マンハッタントランスファーであり、このアルバムであり、カミロ自身の同名アルバムの前にすでに曲としても有名になっていた。演奏だけでなく、共演メンバー、そして曲ともにカミロのデビューアルバムとして相応しい内容だ。
このアルバムはそもそもフレンチホルンのピーターゴードンがリーダー格を務めるグループのアルバムであった。ギルエバンオーケストラのメンバーであったゴードンがメンバー仲間のルーソロフなどに加え、当時のニューヨークの若手(後の大物)達を集めて、グループとしては5年近く活動をしていた。当時は無名であったが実力あるメンバー達が地道に行っていた演奏をアルバムに残したのには感心する。
内容は、フュージョンであり、ラテン調であり、そしてコンベンショナルなジャズの要素も取り入れ、まさにクロスオーバーの極みといった内容だ。見方、聴き方によって色々な顔を持つアルバムだ。
そして、このアルバムを制作したのは日本のレーベル「エレクトリックバード」。日本が元気であった頃の置き土産がこんな所にもあったのを久々に聴き返して再認識した次第。
グループ自体は、この一枚で解散。メンバーはそれぞれの道を歩むことになるが、何か時代の節目を感じるアルバムだ。
1. Why Not? Michel Camilo 5:46
2. Joe Cool Rod Mounsey 6:42
3. Ion You Peter Gordon 9:11
4. B.A. Express Carlos Franzetti 6:24
5. Butter (Tribute to Quentin Jackson) Jerry Dodgion 6:52
6. Calentado Man Michel Camilo 9;04
Peter Gordon (fhr)
Lew Soloff (tp)
Jerry Dodgion (as)
Michel Camilo (p)
Anthony Jackson (b)
David Weckl (ds)
Stev Gadd (ds) #3,4
Arranged by Michel Camilo #1,6 Peter Gordon #2,3,Jerry Dodgion #5,Carlos Franzetti #4
Produced by Shigeyuki Kawashima
Engineer : Bill Sheniman
Recorded at Skyline Studio, N.Y. on April 7,8 &9,1984
アルバムとの出会いは人それぞれ、人によってそのアルバムに対しての印象や思い入れは異なるものだ。
しばらく前に、サドメル&VJOのレパートリーだけを演奏するメイクミースマイルオーケストラのライブに行った。今年のライブのお題は「20周年」。このオーケストラの設立20周年記念ということであった。そして、その日のプログラムはこのグループの範とするメルルイスオーケストラの”20 Years at the Village Vanguard”のアルバムに収められている全曲であった。なかなか洒落っ気のあるプログラム構成であった。
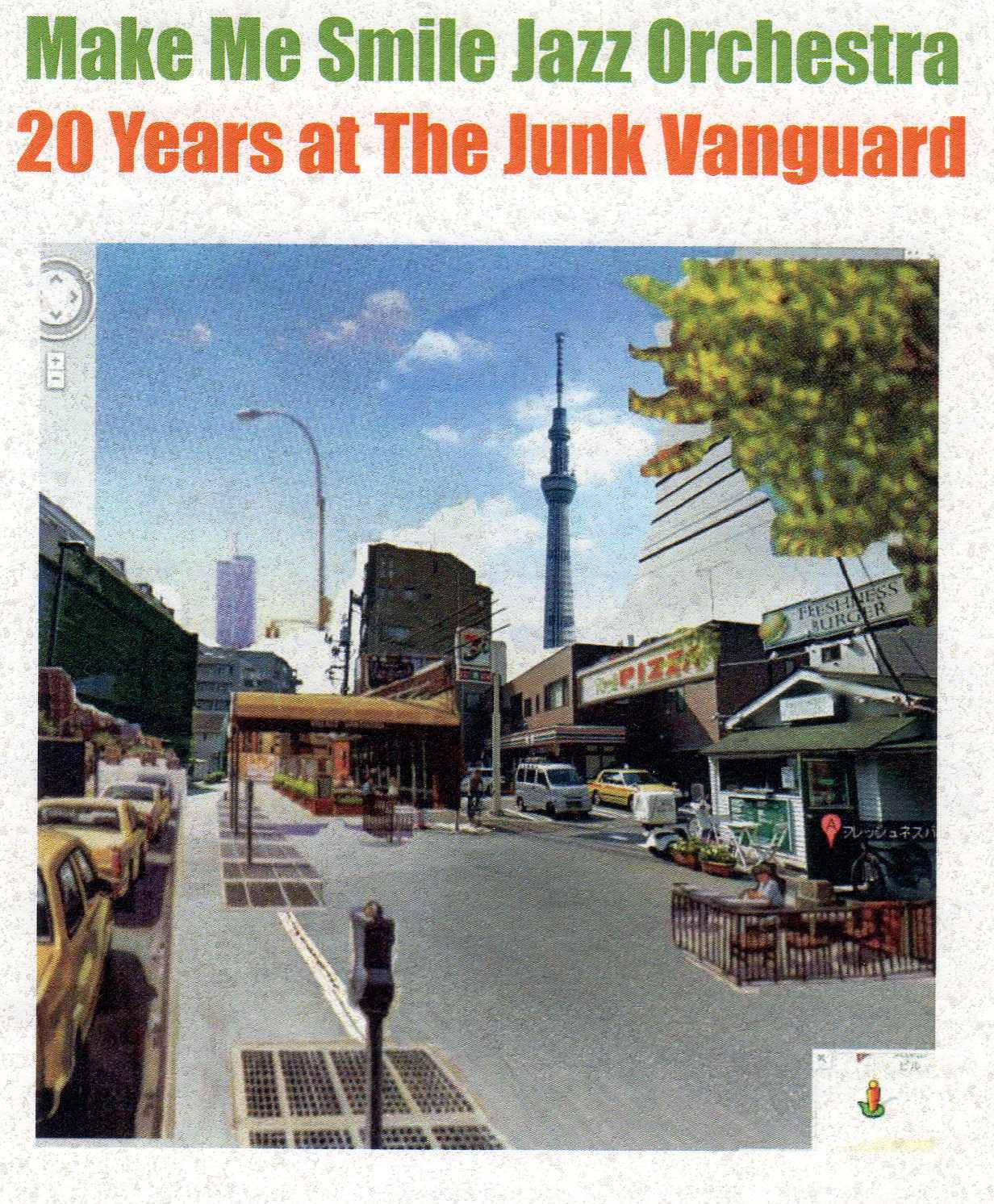
演奏の途中のMCの中で、その日のプログラムの元となったメルルイスオーケストラのアルバムのジャケットが紹介された。そして、次に登場したジャケットが、この“French Toast”のジャケットであった。一瞬、何でその場で紹介されたのか意味が分からなかったが、話を聞くとこのアルバムに収められている”Butter”という曲が、ジェリーダジオンの作曲で、このメルルイスオーケストラのアルバムにも収められているということであった。
このメルルイスのアルバムは1985年の録音、そしてフレンチトーストの録音は前年の1984年の録音。フレンチトーストの方が先に世に出ていたということになる。そして、このフレンチトーストにはジェリーダジオン本人も加わっていた。
サドメルのコアメンバーであったジェリーダジオンだが、サドメルのレパートリーでダジオンの作編曲は決して多くはない。サドメルファンとすれば、珍しいダジオンの曲のお披露目の場としてこのアルバム「フレンチトースト」が印象に残ったのであろう。
さて、自分にとって、このフレンチトーストというアルバムは?というと、ピアノで参加しているミシェルカミロのデビューアルバムとしての印象の方が強い。自分自身もサドメルファンでありながら、このアルバムにジェリーダジオンが参加していたのも忘れていたくらいだ。
当時のカミロ写真を見ると実に若い、まだ30歳になったばかり。ドミニカ出身のカミロがニューヨークに来たのが1979年。ジュリアードで学びプロとしての活動を始めた頃だ。この演奏を聴き返しても、ラテンの血とクラシックに裏打ちされたテクニックは今のカミロを予見させるような個性を感じさせる。
後に、カミロのトリオのメンバーとなった、ベースのアンソニージャクソン、ドラムのデビッドウェックルもこの頃から一緒に演奏していた仲間であったことが分かる。
そしてカミロの名曲Why Not?が収められているが、マンハッタントランスファーであり、このアルバムであり、カミロ自身の同名アルバムの前にすでに曲としても有名になっていた。演奏だけでなく、共演メンバー、そして曲ともにカミロのデビューアルバムとして相応しい内容だ。
このアルバムはそもそもフレンチホルンのピーターゴードンがリーダー格を務めるグループのアルバムであった。ギルエバンオーケストラのメンバーであったゴードンがメンバー仲間のルーソロフなどに加え、当時のニューヨークの若手(後の大物)達を集めて、グループとしては5年近く活動をしていた。当時は無名であったが実力あるメンバー達が地道に行っていた演奏をアルバムに残したのには感心する。
内容は、フュージョンであり、ラテン調であり、そしてコンベンショナルなジャズの要素も取り入れ、まさにクロスオーバーの極みといった内容だ。見方、聴き方によって色々な顔を持つアルバムだ。
そして、このアルバムを制作したのは日本のレーベル「エレクトリックバード」。日本が元気であった頃の置き土産がこんな所にもあったのを久々に聴き返して再認識した次第。
グループ自体は、この一枚で解散。メンバーはそれぞれの道を歩むことになるが、何か時代の節目を感じるアルバムだ。
1. Why Not? Michel Camilo 5:46
2. Joe Cool Rod Mounsey 6:42
3. Ion You Peter Gordon 9:11
4. B.A. Express Carlos Franzetti 6:24
5. Butter (Tribute to Quentin Jackson) Jerry Dodgion 6:52
6. Calentado Man Michel Camilo 9;04
Peter Gordon (fhr)
Lew Soloff (tp)
Jerry Dodgion (as)
Michel Camilo (p)
Anthony Jackson (b)
David Weckl (ds)
Stev Gadd (ds) #3,4
Arranged by Michel Camilo #1,6 Peter Gordon #2,3,Jerry Dodgion #5,Carlos Franzetti #4
Produced by Shigeyuki Kawashima
Engineer : Bill Sheniman
Recorded at Skyline Studio, N.Y. on April 7,8 &9,1984
 | フレンチ・トースト |
| クリエーター情報なし | |
| キングレコード |


























