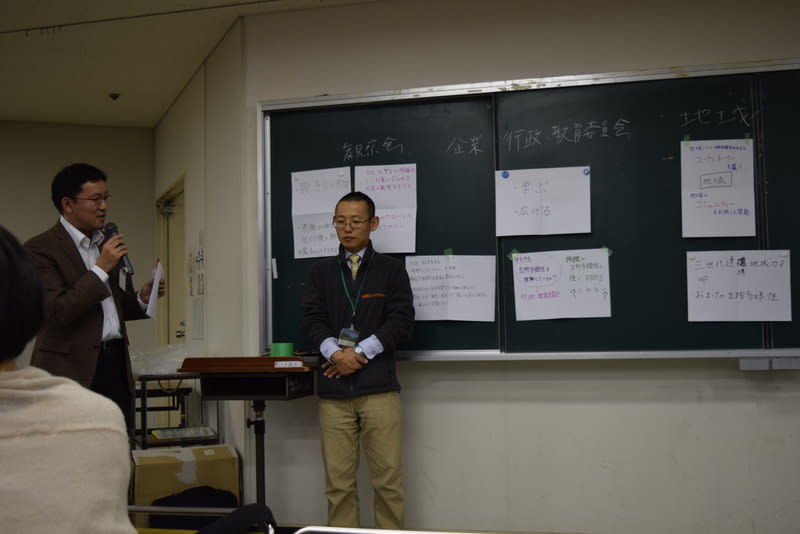寒くなりましたねえ。 てなことで温泉ですよ。

寒の地獄に行ったら 冷泉で ブルブル ここは見るだけにして 暖かい方に入りました。
次の日はタデ原湿原にGO!

この時期に来たのは初めてです。 花は咲いてませんが なかなか良いですねえ。木道の回りは野焼きに備えて 刈られています。

木々も葉を落として 枝が空を切り分けています。 いいなあ。
森を歩くと普段気が付かない樹木の樹皮の様子に目が行きます。

ナツツバキ 美しいです。

こっちはリョウブ 似てるけど違います。 違いを見て歩いていたらだんだん訳わからなくなって、まあ人それぞれ 木もそれぞれ

オトコヨウゾメの実が 誰か食べてくれんかなあ というように下がってます。 これ甘くなかったわ。

キノコも生えてますよ。 これとても美味しそうなシメジの匂いがしました。 でも見るだけ。

林の根元には 真っ赤なツルシキミの実が クリスマスの飾りのようについてます。 もう12月だなあ。

ヤシャブシの木にたくさん小鳥が来て実をついばんでいます。マヒワです。
なんというかお行儀がいいというか さえずり無しで一心不乱静かに食べているのです。
誰とは言わんけど ○○カラとか○ゲラとかの集団は やかましいもんねえ。

一緒に眺めていたKさん曰く カニの食べているときの無言状態 そうか~ ヤシャブシの種ってすごウマなのかも。
うっとりしてるように 見える? あ~うまうま~

冬を迎える九重の草原 名残のススキ

寒の地獄に行ったら 冷泉で ブルブル ここは見るだけにして 暖かい方に入りました。
次の日はタデ原湿原にGO!

この時期に来たのは初めてです。 花は咲いてませんが なかなか良いですねえ。木道の回りは野焼きに備えて 刈られています。

木々も葉を落として 枝が空を切り分けています。 いいなあ。
森を歩くと普段気が付かない樹木の樹皮の様子に目が行きます。

ナツツバキ 美しいです。

こっちはリョウブ 似てるけど違います。 違いを見て歩いていたらだんだん訳わからなくなって、まあ人それぞれ 木もそれぞれ

オトコヨウゾメの実が 誰か食べてくれんかなあ というように下がってます。 これ甘くなかったわ。

キノコも生えてますよ。 これとても美味しそうなシメジの匂いがしました。 でも見るだけ。

林の根元には 真っ赤なツルシキミの実が クリスマスの飾りのようについてます。 もう12月だなあ。

ヤシャブシの木にたくさん小鳥が来て実をついばんでいます。マヒワです。
なんというかお行儀がいいというか さえずり無しで一心不乱静かに食べているのです。
誰とは言わんけど ○○カラとか○ゲラとかの集団は やかましいもんねえ。

一緒に眺めていたKさん曰く カニの食べているときの無言状態 そうか~ ヤシャブシの種ってすごウマなのかも。
うっとりしてるように 見える? あ~うまうま~

冬を迎える九重の草原 名残のススキ