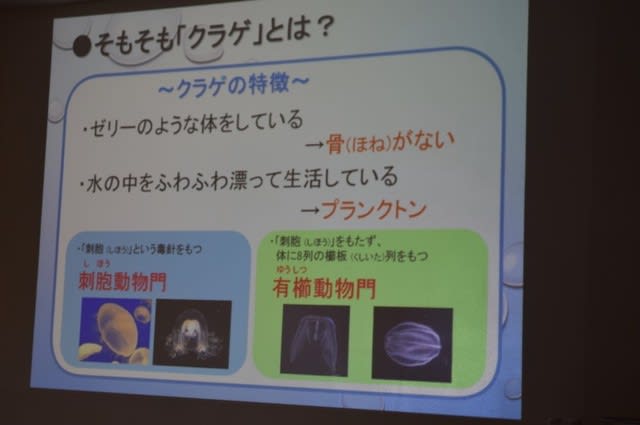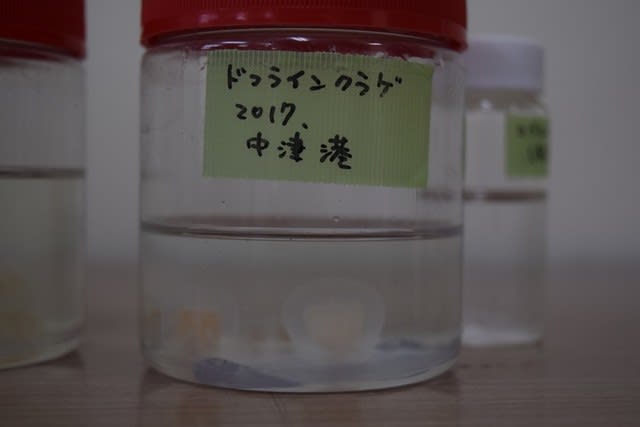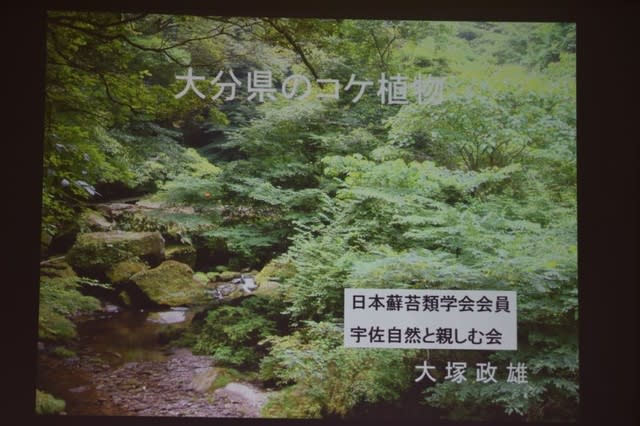秋空 ピーカン 今日は化石掘りにいい日

この斜めに走る地層は 白亜紀の地層

まずはY先生にお話を聞いて みんな掘りたくてうずうず ちゃんと聞いてよね
この場所は 「イノセラムス ホベツセンシス」 という貝の化石と アンモナイト化石が出ます

これが イノセラムス ホベツセンシスの化石 センセの秘蔵品
イノセラムスはもっと盛り上がった貝なんだけど 化石になるとき圧力や熱が加わって 変形するんだそうです。
そうか 化石って ぺっちゃんこな物が多いのは 潰されていたのか。知らんかったなあ。

これがアンモナイト アンモナイトは タイヤサイズから 5mmサイズまで いろいろとございます

お話聞いて それっと ガレ場に

今回活躍した 小学生軍団 水泳帽にゴーグルして もう準備からスバラシイ!
そしてどんどん見つけるのです。 回りの大人たちが悔しがっています。

Y先生が 欲が有ったらいかん。無心で! と言われる。
私なんか大きな布のバックや包んで帰るタオルをいっぱいもってきたので欲の塊 みつからんよ~ 化石欲しいよ!
で、小さなアンモナイト(5mmサイズ)とイノセラムスのかけらを見つけました。
層になった石をパンと割ると 化石が出てくるとめちゃ嬉しいです。
でもその瞬間!!息を吸い込んで!! 9390万年前の空気が出ているのです。 白亜紀チューロニアンの時代の空気を吸おう!