

 松山市青少年育成市民会議
松山市青少年育成市民会議今日は、同会議の常任理事会に出席してまいりました。
同会議は、平成16年4月にできた松山市子ども育成条例を契機に立ち上がったものです。
また、同条例は地域が一体となって子どもの見守りや育みを行っていくというもので、先進的な取り組みではなかったかと思います。(私が来たときには既に出来上がっており、制定までの生みの苦しみは相当なものだったと聴いています。)
そして、昨年、教育基本法の中(第13条)に新たに学校・家庭・地域が一体となって子育てに取り組むということが付け加えられました。
つまり、松山では国に先駆けて地域が一体となった取り組みの必要性を条例化したのです。
そして、同会議はさまざまな行動を起こしています。
この行動には、時間のかかるものばかりですが、つなげていくことで確実な成果が出てくるものばかりです。
そんな中、新規事業提案として「チャイルド・サポートセンター」なる、簡単に言えば子育て相談のワンストップ窓口をつくろうというものです。
あるようでなかったものが提案されました。
対象は、妊娠時からのサポートということで、年齢で縦割りになっている行政の限界に市民団体の組織がチャレンジしようというものかと思われます。
また、行政の関係機関と張り合うものではなく、むしろ行政の限界である縦割りの壁を中間組織としてつなげようというものだと理解しました。
凄いことです。
こういう発想が市民から出てきてもらえるようになった。
行動指針の方向付けとなる法令や制度(ここでは「松山市子ども育成条例」)が必要だということを改めて認識しました。
そして、常々考えていたさまざまな分野で地域社会の中に中間組織がないということをこの提案が具現化しようとしています。
例えば、相談業務は行政がやるものだという既成概念があります。
でも、相談の中身を見ていると大方が軽微な相談なのです。
この中間組織が出来上がれば、行政機関もすごく楽になると思います。
そして、何よりも専門知識を必要とする相談事に特化することができます。
私たちは、まず目の前にある課題を細分化し、それが誰ならできるのかを一度検討してから行動を起こしていく、いい事例になると期待しています。














 教育の原点
教育の原点

 読み書き、算盤
読み書き、算盤







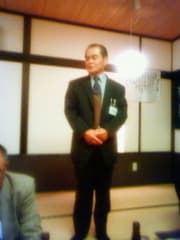



 評価されるということ
評価されるということ



















