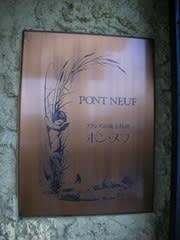地方公務員は、1975年の調査以来最少の約285万人との結果に不安が
地方公務員は、1975年の調査以来最少の約285万人との結果に不安が
昨日の新聞各紙に、地方公務員が減少しているとの、時事通信の配信記事が掲載されていた。
「総務省は28日、今年4月1日現在の地方公務員の定員調査結果を公表した。各自治体の行政改革により、地方公務員総数は前年比4万4272人(1.5%)減の285万5106人で、19755年の調査開始以来の最少記録を2年連続で更新した。
全自治体は、2010年度までの5年間で05年度比6.4%の職員純減目標を掲げているが、純減率は4年目で6.2&達したことになる。
内訳は、都道府県が同1万8050人(1.2%)減の154万2705人、市町村が同2万6222人(2.0%)減の131万2401人。各自治体では、業務の民間委託などで新規採用職員を抑制し、職員純減を図っている。」とある。
今、民主党政権は、「脱官僚政治」を掲げており、国民のみなさんの中にも全体的雰囲気として、国や地方の職員をある意味「目の敵(かたき)」にしている傾向があるのではと感じている。
私は、国や自治体職員役割の大きさ、そして公共の大切さを身に染みて感じており、国政でも自治体行政でも、職員の力を十分に引き出し発揮させてこそと思っている。その意味で、「地方公務員が調査開始以来の最少」ということに、大きな不安を感じている。
私が地方行政の末端を担わせていただいたが、以前も現在も、「市役所は市民の役に立つ所」であり、かつ「市役所=市民の役に立つ職員がいる所」と信じている。今その「役に立つ職員」が大幅に減っている。そのことを不安に思い、かつ憂う。それは何より、「市役所が市民の役に立たない所」に変わってゆく、つまり自治体が市民のみなさんの暮らしを守る役割が発揮できなくなる事態だと感じるからである。心が痛む。
自治体職員を減らすことだけが全てではなく、必要な部署への適正配置、今それが求められていると考える。