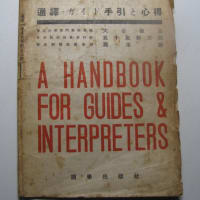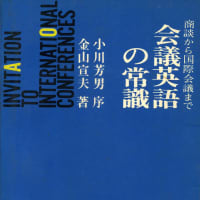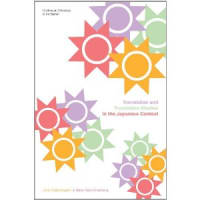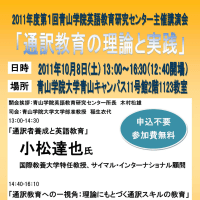■古い話になるが、東大出版会のPR誌『UP』の昨年の2月号に、亀山郁夫の新訳『カラマーゾフの兄弟』に触れた沼野充義の文章が掲載されていたようだ(「薄餅とクレープはどちらが美味しいか?-翻訳について」)。これについてはいろんな人が言及しているので詳しくはそちら(mmpoloの日記、お楽しみはこれから!、横浜逍遙亭など)を見てほしい。同じロシア文学で、それぞれの主張をぶつけ合った1970年代の「原=北御門論争」とは違い、沼野は亀山訳をはっきりと批判しているわけではない。そのことは毎日新聞に載った沼野の書評でもわかる。そして「原=北御門論争」とは論点が異なっているとはいえ、沼野が言っていることには特に新味があるわけでもない。しいて新しい論点といえば「異化的」foreignizingな翻訳でも、「同化(馴化)的」domesticatingな翻訳でもない、「媒介的な」タイプの翻訳を提案していることだろう。その部分だけ引用しておく。
「第三の「媒介的」なタイプは、翻訳者の母語と外国語の間を媒介し、そこにいわば第三の言語を作ろうとするものだ。無論、この第三の言語とはユートピア的なもので、現実にはベンヤミンのいう「純粋言語」同様、存在しないのかも知れないが、私はその媒介的な場で展開するものこそが「世界文学」と呼ばれるに相応しいと考えている。」
しかしこれでは何のことかさっぱり分からない。もっとはっきり書くべきだし、書けないなら最初から書かないほうがいい。(ついでにベンヤミンをこういう風に使うのはいいかげんやめたらどうか。)「同化」と「異化」にしても、もはやVenutiやBermanが問題にした規範や言語の政治学や翻訳者の倫理を抜きにしては語れないだろう。沼野は『罪と罰』の新訳を出すそうだから、おそらくそこに第三の「媒介的」翻訳の実例が見られるのかもしれないが。なお沼野は毎日新聞の書評で、Richard PevearとLarissa Volokhonsky夫妻の「カラマゾフ」の新英訳に言及しているが、その2人のインタビューが面白い(これはトルストイの時のだが)。OEDに基づく歴史的翻訳原則だそうで、「翻訳賞味期限論」もかたなしである。