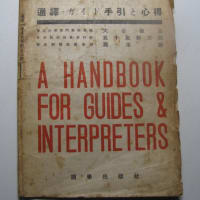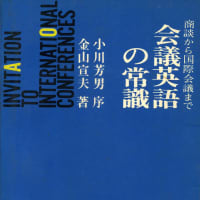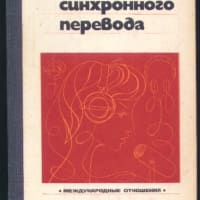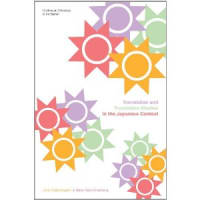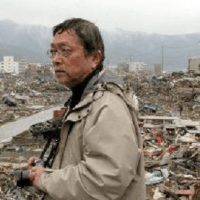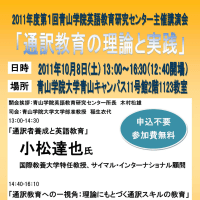■小山亘『記号の系譜 社会記号論系言語人類学の射程』(三元社)。
立教で同僚だった小山先生の新著である。(第2章だけ榎本君・永井君と共著。)1月末に出た本だが、まだAmazonのレビューはもとより、紹介したブログも見あたらない。(タイトルあるいは目次だけの紹介ならあるが。)それには理由があって、おそらく、言語人類学という日本ではあまりなじみのない学問をベースに、パース、ヤコブソンの「記号論の亡霊を呼び覚ま」しつつ、「反・全体化」の言説に抗して、個別性を維持しながら全体を模索するという壮大な「反時代的営み」の書であるためだろう。つまり、多くの前提的知識が必要なため、その理論的内実と構想が簡単には理解できないのである。(僕も理解できないため全部は読んでいませんので悪しからず。)時が経てばしかるべき人がしかるべき紹介なり書評をすると思うが、ここでは先行的におざなりな紹介と自分の関心に引きつけての感想を記しておくことにする。
■540ページの大著で全体は5章から構成される。「パース記号論、ボアス人類学、フンボルトの宇宙誌、あるいは「文化と自然」について」という短い「序」に続いて、第1章「社会記号論と言語人類学:全体、再帰、批判、歴史」では現代言語人類学の特徴と系譜を概観。第2章「言語人類学・社会記号論とは何か?」では現代言語人類学におけるコミュニケーションモデルと名詞句階層の問題などを扱っている。第3章「メタ言語学としての史的社会記号論:社会、教育、言語理論の近現代、あるいは、言語帝国主義と言語ナショナリズムの系譜学」では言語イデオロギー、言語教育理論の変遷を記号論的に分析する。第4章「記号言語理性批判序説:記号論の「可能性=終焉」のかくも長き不在」はロックやニュートンなどの言語、コミュニケーション・イデオロギー、社会文化イデオロギーの分析にあてられている。第5章「意味と出来事:現代記号論の系譜」はカント以降の言語研究、社会言語研究の歴史とアメリカ言語人類学の歴史を俯瞰する。(詳細目次はこちらを参照。)
■以下ランダムに感想を記していく。パースの記号論については「指標化作用」「類像性」「象徴性」が中心的に取り上げられていて、僕の関心事である「対象」と「解釈項」の問題は主題的には取り上げられていない。しかし、第2章のシルヴァスティンをもとにした社会文化史的コミュニケーション・モデル(p.222-227)は、現代翻訳研究の強力な一潮流である「社会的転回」Social Turnのモデルに転用できる可能性がある。翻訳は、ある社会文化史的文脈にあるテキストが別の社会文化史的文脈に転移される一種の社会文化史的コミュニケーションと考えることができる。翻訳によって原テキストの社会文化史的意味は変容し、さらに翻訳テキストがそれがおかれた社会文化史的文脈の中でその文脈自体を変容させていく、というように。(つづく)