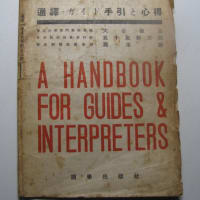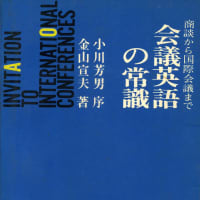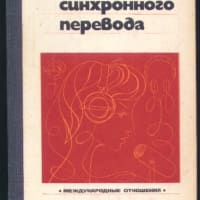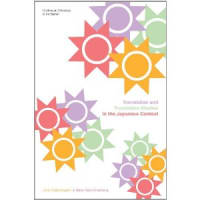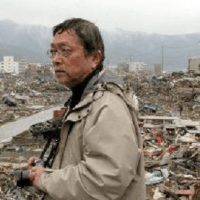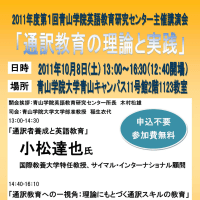■『聖書翻訳を考える:「新改訳聖書」第三版の出版に際して』の続き。
Van Leeuwenの文章は、一読すれば分かるように、理論的な内実はほとんどない。この文章は2001年に書かれているが、その後たとえばTimothy Wilt (Ed.) (2003) Bible Translation (St. Jerome)のような研究もあるわけで、『聖書翻訳を考える』にその点についての言及がないということは、翻訳研究をふまえた聖書翻訳ではないのではないかという疑念も生まれる。Wiltの本を見れば、聖書翻訳研究の世界では「ナイダ以後」を見据え、機能主義、記述的研究、テキスト言語学、関連性理論、ポストコロニアル理論、リテラリスト、外化vs.内化など、多様な翻訳研究の進展を取り込んだ聖書翻訳研究が行われていることがわかる。単にリテラルな視点を対置するだけでは理論的反動にしかならないだろう。そのリテラリズムに戦略的視点がなければ、現在ではほとんど価値がない。そもそもナイダの理論は「普通の人のための聖書」をめざした反逆的翻訳であったとされているし、従ってその理論は(少なくとも最初は)戦略的なものだったと思う。
■韓国会議通訳学会KSCIからConference Interpretation and Translation, Vol. 7 (1) (2005)が届く。論文のテーマは、媒介者のしてのダイアログ通訳者の機能、異文化コミュニケーションとしての諺の翻訳、言語の類似性が通訳と翻訳に及ぼす影響、異なる読者層に向けての翻訳:「不思議の国のアリス」を事例に、通訳教育で「実際の会議のセッティング」を作ることの利点、外国語への翻訳において学生の問題解決能力を強化する、翻訳における創造性、翻訳教育と技術的談話、翻訳能力のためのWriting Skillsを学ぶ、など。ただし、英語論文は2編のみ。
■紹介が遅れたがBabel, Vol. 50 No. 4 (2004).発行がかなり遅れている。この雑誌はつまらない論文が多いのだが、今回はちょっといい…かもしれない。abstractが読める目次はこちら。
■小坂貴志さんからの頂き物2点。
小坂貴志(2005)『90分で学べるSEの英語力』(日経BP社)
小坂貴志・小坂洋子(2005)『アメリカの小学校教科書で英語を学ぶ』(ペレ出版)
いずれもユニークな内容だ。後者はアイディアとしては以前からあることはあったが、実際に読みやすい本にまとめた功績は大きい。通訳・翻訳ではよく背景知識の重要性が指摘されるが、この本にあるような知識はその背景知識のさらに背景となっていて、学習者にとって盲点となりがちな知識だと思う。同じ出版社から(別の著者で)中学校教科書のシリーズも出ている。