ごく最近の話です。
私の趣味の中にトミカ集めというのがあるのですが、同好の士の雑談の中で、最近出たあるミニカー(マニア向け細密トミカ)の事を書いた時にあるトミカでアンテナや補助灯なんかが別パーツ化され、ユーザーが後付けする形態について「個人的には(ディテールアップ)パーツの後付けというのはやめてほしい」というコメントを頂きました。
トミカでは最近こういうパターンが結構あるのですが、後付けパーツで細密感を上げるというのは鉄道模型では以前から常套手段なので、この辺りNゲージで鳴らしたトミーテックらしい発想だなと思っていました。
実際、私自身この点には違和感を感じていませんでした。が、こうして指摘されてみれば「なるほどそういう見方もあるな」と気づいたのも確かです。

これはコレクターというよりモデラー寄りの発想なのも確かでコレクターの方が圧倒的に多いミニカーのやり方としてはそぐわない面もあります。
ミニカーの場合は鉄道模型と異なり玩具としてだけでなく古くからコレクションアイテムとして発達してきた側面が強い(何しろ英国首相だったチャーチルもミニカーコレクターだったそうですし)のであくまで発売時のオリジナリティが重視されます。
すくなくともこちらではモデルの加工というのは全体で見れば傍流ですし、加工されたモデルは余程よく出来ていないと価値を認めないコレクターというのも確かに存在します。
翻って考えてみると、その昔「テツドウモケイの趣味」といえばその大半は「作ること」にプライオリティが置かれていました。
Oゲージはもとより十六番がメインの時代までは完成品のモデルは当時の物価レートを勘案しても無闇に高かったですし、完成品のモデルが出ていても予算的な問題からキットメイクか自作に頼らざるを得なかったことは当時の専門誌でも読めば容易に想像できます。
(加えて地方では「そもそも完成品のモデル自体がそんなに置かれていなかった」という現実が涙)
その現状が変わったのがNゲージの登場と普及にあったことはご存知の通りです。
完成品の価格が16番のそれよりも安価だった事もありますが、加えて初期のNゲージモデルは動力系が精密機械扱いされ分解が推奨されなかった事もあって、動力の自作や改造がそれほど普及しなかった事、何よりNゲージのコンセプトが車両工作よりもレイアウト作りを推奨するものだった事もあって「Nゲージモデルは完成品を走らせる方向」主体になって行きました。

が、その後の普及に伴う完成品車両モデルの急速なラインナップ拡充はNゲージモデルのコレクション化というベクトルを後押しすることになります。
それまで完成品車両のコレクションは16番モデルでは一部富裕層を除けばあまり普及しなかったのと対照的に、それまでメジャーにならなかった「コレクションとしてのテツドウモケイ趣味」の側面が確立することとなりました。

また、Nゲージのレイアウト製作という方向性が当初考えられていたほどには普及せず、運転の楽しみがお座敷運転、最近はレンタルレイアウトでの運転という方向性に進んだ事が「運転=自慢のコレクションのお立ち台」的な側面になってきた感もあります。
上述のトミカの例などは、かつての鉄道模型趣味の行き方とは逆の方向の発想ではありますが、個人的には趣味の本質という点でそれほど違いがあるとは思えません。
実を言いますと、このブログを始めた頃の時点で「テツドウモケイの工作派から見たコレクター志向への危惧」についてあちこちのブログやSNSでのやりとりで随分と聞かされてきましたが、その割に逆の立場から工作派に対する反論というのをあまり聞いた事がありません。
そんな折に聞いた上述のトミカのコメントに私個人としては「虚を突かれた思い」がした事も確かです。
作る楽しみもあれば集める楽しみもある。そしてどちらの要素も趣味としては重要な要素ではないかと思えます。

「鉄道模型には色々なジャンルがある。大きく分ければ車両を楽しむ行き方と、レイアウトと運転を楽しむ行き方がある。
この両方を適当にミックスするのが一般的なファンであろう」
(山崎喜陽著 保育社カラーブックス「鉄道模型」P2より引用)
これはカラーブックスの名著(と私が勝手に思っている)「鉄道模型」の冒頭の一節です。
この「適当にミックスする」と言う部分に深い含蓄を感じています。
実際、レイアウトの存在がある事で鉄道模型の趣味としての拡がりは他のジャンルに比べて相当に広くなっており、考えようによっては「鉄道模型をやる事で他にない見識を広げる事ができる」と言う事も出来るかもしれません。
そしてその過程の中で一種のバランス感覚を身につけ、融通無碍な楽しみを通して大人になって行く事も出来る様な気がします。
これと同じ事は「作る」事と「集める(コレクション)」についてもいえると思います。
それまでの「作る鉄道模型」という面と最近の「集める鉄道模型」という面は全く両立しないものでしょうか。
趣味の本質の一つには「クリエイター性」というものがあると思います。他人と同じものを持つ。他人と同じ事をするのを潔しとせず、自分独自の何かを自らの手で勝ち取って行く過程とでも言いましょうか。
そのプライオリティは工作の成果かもしれないし、コレクションの中の集め方への拘りかもしれない。いずれにせよ何かしら自分独自の何かがそこに表現されるものではないでしょうか。
例えば新車を入線させても自分の好みの改造を加えたり、そこまでとは言わなくても付属のナンバープレートをつける、方向幕を貼るというレベルでもそこにユーザーの主張が現れるのならある意味クリエイティブな行為とはいえます。
(ですが一方では「ビスやナット以外を全て作らなければ自作とは言わない」という考えというかこだわりが存在するのも事実ですが)

また、コレクションにも「なぜ集めるか」「その人の集め方のポリシーがどこにあるか」という点にユーザーの主張やオリジナリティが出る事は言えると思います。他のジャンルのコレクションで有名なコレクターがそうした観点から名著(本を著すというのはコレクターの自己表現手段としてもっともポピュラーな形態です)をものしている例は多いですし。
ですが不思議とモデラーサイドでその点はあまり評価されませんし、逆にコレクターサイドから見るとモデラーのポリシーが煙たがられる事もあったりします。
どこまでが工作でどこからがコレクションか。
近年の鉄道模型の世界ではその間のグレーゾーンがとても広くなっている感があります。

「購入したモデルを全く手付かずのまま保存し運転もせずに単に持っている事に満足する場合」は流石に「作る鉄道模型」とは言わないでしょうがそんなのは現在でも少数派だと思います(それが利殖として成立するほど鉄道模型がメジャーな高級趣味になったとは思えないですし)
逆に工作派を自認している人がたまたま気に入って購入した完成品を手を加えずに飾ったり走らせたりする様な事もあるかもしれません。
誰しもコレクター的側面というものは持ち合わせていると思いますし一方ではクリエイティブな側面もまた然りです。そう思うと作る事と集める事をあまり厳格に分けて捉えない方が精神衛生上は良い様に思えます。
むしろ作る要素と集める要素の狭間にあって「どれだけそのユーザーの顔が見えるか、あるいは主張があるか」というのが趣味の世界でのユーザーのアイデンティティではないかと。
それは自らを「工作派」「コレクター」と枠にはめて規定してしまうよりも大事な事の様な気がします。
(尤も、現実には特に車輛派を中心にゲージやスケール、特定地域やジャンルの範囲を狭小化させそれらの小分けされた小さなコップの中で、スノビッシュなエリートごっこに終始している事の方が問題かもしれませんが)
「色々やってみる事や他のジャンルに興味を持つ事でそれまで凝り固まった概念から解放され、世界が拡大して感じられるという経験の楽しさ」を実生活で感じるのは色々なしがらみから困難でしょうが、趣味の世界ならそれができる可能性が高い。
むしろ「作る」と「集める」を両立させつつ趣味と見識を深める事ができるというのも鉄道模型の趣味の新しい御利益と言えるかもしれません。
なんだか取り留めのない駄文になってしまいましたがご勘弁を。














































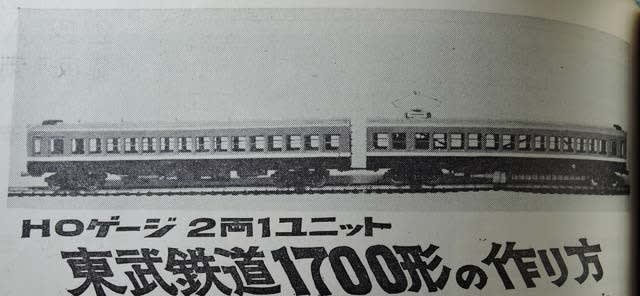















 とか言いながら現時点でうちのレイアウトで唯一本作をリスペクトしているのは「モジュール内のマウントドラゴン状態の第一形態ゴジラ」位なものですが(汗)
とか言いながら現時点でうちのレイアウトで唯一本作をリスペクトしているのは「モジュール内のマウントドラゴン状態の第一形態ゴジラ」位なものですが(汗)





