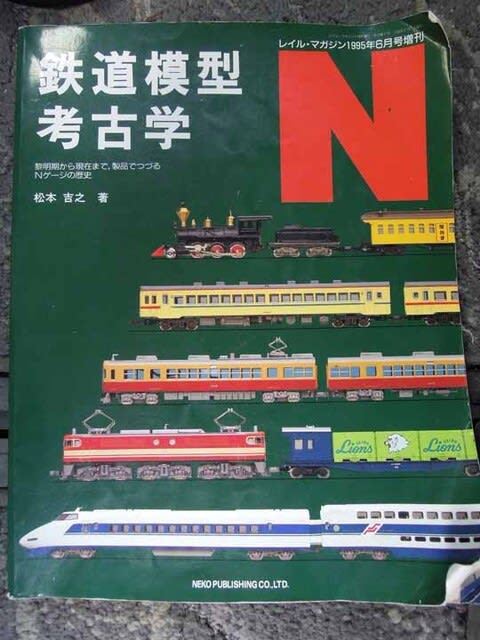今回はトレインフェスタにまつわる「酒の上のしくじり」という残念な話から。

前夜祭の帰りに真夜中の駿河屋で見つけたのはマイクロのEH10、試作型です。
EH10は試作型と量産型とでは車体の長さが微妙に異なり、パンタの位置も違うのですが、それゆえにマイクロ辺りが出しそうな題材です。

実はこの時同じ個体が2両ありまして、お値段も適当(因みに駿河屋は当時レジで1割引というセールをやっていた)と思ったので2両を試走させて比較した上で、ちゃんと走る方をレジに持っていった…はずなのです
ですが、これを買った時のわたしときたら「クラブのトレインフェスタ前夜祭でしたたか酔っ払っていて、正常な判断ができない状態」でした。
それでいて本人は「そこまで酔っていない」という強気さでしたから、その時はそれで済んでいたのです。

馬脚が出たのは翌日のトレインフェスタでのデビュー兼試運転の時。
まず外見では「カプラーが片方欠損」車体を持ち上げると動力ユニットがずり落ちそうになるという微妙なコンディション。
まあ、この辺りならリペアできそうな感じだったのですが、
レールオンで通電した途端「モータが空回りを始め、クラッチの滑ったMT車みたいな走りを始めた」のには参りました。

そう、レジに持って行った際に、よりにもよって「悪いコンディションのモデルの方を出してしまった」のです。
アルコールに頭を毒されていたわたしの見落としとしか言い様がありません。

そう考えると6千円弱のお値段は如何にも高い。
やはり酒が入っていると碌なことがありません。
結局、翌日もう1両の方と交換して事なきを得ましたが、酔っぱらい状態での買い物は危険だという教訓だけが残りました。
代わりに来たモデルは走行性については問題なし。手持ちのPS22仕様と異なり片側が無動力となっているのが目を惹きますが、軽量になった反面ダイカストブロックがオミットされたらしく窓の向こうがスカスカに良く見えます(笑)

前夜祭の帰りに真夜中の駿河屋で見つけたのはマイクロのEH10、試作型です。
EH10は試作型と量産型とでは車体の長さが微妙に異なり、パンタの位置も違うのですが、それゆえにマイクロ辺りが出しそうな題材です。

実はこの時同じ個体が2両ありまして、お値段も適当(因みに駿河屋は当時レジで1割引というセールをやっていた)と思ったので2両を試走させて比較した上で、ちゃんと走る方をレジに持っていった…はずなのです
ですが、これを買った時のわたしときたら「クラブのトレインフェスタ前夜祭でしたたか酔っ払っていて、正常な判断ができない状態」でした。
それでいて本人は「そこまで酔っていない」という強気さでしたから、その時はそれで済んでいたのです。

馬脚が出たのは翌日のトレインフェスタでのデビュー兼試運転の時。
まず外見では「カプラーが片方欠損」車体を持ち上げると動力ユニットがずり落ちそうになるという微妙なコンディション。
まあ、この辺りならリペアできそうな感じだったのですが、
レールオンで通電した途端「モータが空回りを始め、クラッチの滑ったMT車みたいな走りを始めた」のには参りました。

そう、レジに持って行った際に、よりにもよって「悪いコンディションのモデルの方を出してしまった」のです。
アルコールに頭を毒されていたわたしの見落としとしか言い様がありません。

そう考えると6千円弱のお値段は如何にも高い。
やはり酒が入っていると碌なことがありません。
結局、翌日もう1両の方と交換して事なきを得ましたが、酔っぱらい状態での買い物は危険だという教訓だけが残りました。
代わりに来たモデルは走行性については問題なし。手持ちのPS22仕様と異なり片側が無動力となっているのが目を惹きますが、軽量になった反面ダイカストブロックがオミットされたらしく窓の向こうがスカスカに良く見えます(笑)