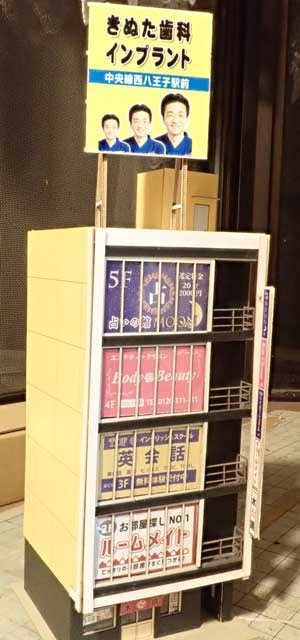今年のレイアウト改修の作業のひとつとして「フレキシブル線路敷設区間のバラスト散布」を目標に掲げておりました。
いつまでもコルク道床にフレキシブルレールでは様にならないですし(汗)

これまでにもレイアウトのバラスト散布はやっていたのですが(恐らく)今回の工程は前より規模が大きく手間もかかると思われたので作業の開始のエンジンがなかなか掛かりません(汗)
(何しろ緩いカーブを描いたフレキシブルレールを2本、変則的な間隔の複線にしているので実質単線2本と同じ事、おまけに既存のレイアウトの改修なので既設部の台枠や配線も邪魔になる)
従来は木工ボンドを水で薄め中性洗剤を垂らしたバラストボンドを自製してやってきたのですが、今回は新兵器としてホビーセンターカトーの「バラスト糊」を使ってみる事にしています。
ですがこれでいきなり本番というのも怖い気がするので、糊の性能チェックを兼ねて予行演習をしてみる事にしました。
改修区間と同様にベースの板にレールを貼り付けその上からバラストを散布、バラスト糊で固着させるプロセスです。

最初の散布ではバラストをいきなり多くこぼし過ぎた為、後から均すのが大変でした(わたしは平筆とコーヒー屋にある木製のマドラーをへら代わりに使用)
本番では指で少しづつ撒いて行った方が良いのかもしれません。

バラスト糊は説明書通りスポイトで注入しました。ボンド水と同様にスポイト先端がバラストに近すぎるとバラストがだまになりやすいところは同様ですが、バラスト糊はボンド水よりもバラストに沁み込みやすいので上からギリギリの低さで垂らして行った方が良く染み込む様です。
(今回はスポイトを使いましたが、Nゲージの場合は出来れば注射器を使った方がもう少し細かに対応できるかもしれません)

曇天下で5時間ほどかけて乾燥した後はバラストも固着し、板を何かにぶつけてもバラストがこぼれる事は殆どありませんでした。
ですので固着性と強度については今のところ合格点だと思います(但し、長期にわたる固着力は未知数。ボンド水の場合は濃さにもよりますが、早ければ2年くらいでぽろぽろ剥がれる所がありました)
今回の試験ではバラスト糊の威力が大きい事を確認できたので、今回の反省点を生かして本番に臨みたいと思います。
いつまでもコルク道床にフレキシブルレールでは様にならないですし(汗)

これまでにもレイアウトのバラスト散布はやっていたのですが(恐らく)今回の工程は前より規模が大きく手間もかかると思われたので作業の開始のエンジンがなかなか掛かりません(汗)
(何しろ緩いカーブを描いたフレキシブルレールを2本、変則的な間隔の複線にしているので実質単線2本と同じ事、おまけに既存のレイアウトの改修なので既設部の台枠や配線も邪魔になる)
従来は木工ボンドを水で薄め中性洗剤を垂らしたバラストボンドを自製してやってきたのですが、今回は新兵器としてホビーセンターカトーの「バラスト糊」を使ってみる事にしています。
ですがこれでいきなり本番というのも怖い気がするので、糊の性能チェックを兼ねて予行演習をしてみる事にしました。
改修区間と同様にベースの板にレールを貼り付けその上からバラストを散布、バラスト糊で固着させるプロセスです。

最初の散布ではバラストをいきなり多くこぼし過ぎた為、後から均すのが大変でした(わたしは平筆とコーヒー屋にある木製のマドラーをへら代わりに使用)
本番では指で少しづつ撒いて行った方が良いのかもしれません。

バラスト糊は説明書通りスポイトで注入しました。ボンド水と同様にスポイト先端がバラストに近すぎるとバラストがだまになりやすいところは同様ですが、バラスト糊はボンド水よりもバラストに沁み込みやすいので上からギリギリの低さで垂らして行った方が良く染み込む様です。
(今回はスポイトを使いましたが、Nゲージの場合は出来れば注射器を使った方がもう少し細かに対応できるかもしれません)

曇天下で5時間ほどかけて乾燥した後はバラストも固着し、板を何かにぶつけてもバラストがこぼれる事は殆どありませんでした。
ですので固着性と強度については今のところ合格点だと思います(但し、長期にわたる固着力は未知数。ボンド水の場合は濃さにもよりますが、早ければ2年くらいでぽろぽろ剥がれる所がありました)
今回の試験ではバラスト糊の威力が大きい事を確認できたので、今回の反省点を生かして本番に臨みたいと思います。