■ 下鴨神社
正式な名前は賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)。星の数ほどお寺がある京都でも、最古参の部類に入る由緒正しいお寺さんとのこと。説明員の方が、境内である糺の森(ただすのもり)から、弥生時代のものと見られる品々が発掘されているとお話しされていました。この糺の森(ただすのもり)というのが広い。鬱蒼と木々が茂る12万4千平米の敷地(甲子園球場の3倍の広さ)の中に、下鴨神社とその末社が点在しています。


楼門をくぐった先が本殿。結婚式が何組が予定されておりました。

本殿には、祭ってあるのが賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)と玉依姫命(たまよりひめのみこと)。川から流れてきた矢を拾って持って帰った玉依姫命が身ごもり男の子(賀茂別雷命)が生まれた。賀茂別雷命が成人し、その祝宴の席で祖父の賀茂建角身命が「お前のお父さんにもこの酒をあげなさい」と言ったところ、賀茂別雷命は屋根を突き抜け天に昇っていったので、この子の父が雷神であることがわかったという言い伝え。
期間限定の特別拝観で見ることができた一つは大炊殿(おおいどの)。こちらも重要文化財。

京都のお寺は拝観料を取るが、神社は取らないと言う。そのためか、下鴨神社のトイレには紙が置いておらず、自販機で購入することになっている。昔の鉄道駅のトイレみたいに。ちょっといただけない。
■ 河合神社
糺の森の中にある神社。神武天皇の母を祭っているという。


方丈記で有名な鴨長明は、この河合神社の禰宜の職に就任を望んだが叶わず、出家して閑居生活を行った折に書き記したのが方丈記だとか。鴨長明は不遇な人生を送ったらしく、下鴨神社の神事を統率する禰宜の次男として生まれながら、神職としての出世の道を閉ざされ、その後源実朝の和歌の師として鎌倉へ下向したものの、受け入られず失敗しているのだそうだ。方丈記のベースに流れる無常観は、こんな人生から生まれたのだろう。
■ 京都御所
総面積65ヘクタール(65万平米)の京都御苑の中心部にあり、南北450メートル、東西250メートルの築地塀で囲まれた中にある、昔の皇居ですね。塀はこんな感じ。

天皇しか通れな正式な門である建礼門。退位された現上皇も、退位された後はこの門ではなく、東側にある建春門を使われるとのこと。

日常の生活の場であった清涼殿。

こちらは大正天皇がお越しになる際に作られた新御車寄。自動車が横付けできるようになっている他、御所の中で電気の照明が入っている唯一の建物なのだそうだ。

御学問所

御学問所前の庭園。

日本国のトップが暮らされ、政をされていた場所であるだけに、きびしい身分の分け隔てがあちこちに見られる。例えば、殿上の間という控え室が3つ続きであるのだが、右2つ(虎と鶴の間)は車寄から入れるのに対して、諸太夫の間は車寄から歩いて軒先まで行き、履物を脱いでしか部屋に入れない構造になっている。出入りする門が厳格に定められていることは先に書いたとおり。
面白かった情報として、御所の屋根には3種類ある。瓦と銅版葺き、そして檜皮葺(ひわだぶき)。高貴な方が暮らされる建物には瓦は使われないとのこと。理由は、人が足で踏んだ土を材料にして作った瓦を頭の上に置くことは高貴な方には相応しくないからとのこと。そう言われて門を見てみると、天皇しか通れない建礼門の屋根は檜皮葺であったのに対して、我々が使用した清所門の屋根は瓦葺でした。
また、御所の北東(鬼門)には小さな凹みがあり、鬼門を守る猿が据えられている。北東方向には比叡山があり、これも京都を守るためにここに延暦寺が建てられた。なぜ猿なの?と訊いたら、一説では北東と逆の方向(申の方角)とすることで、鬼門がどんどん遠くに外れていくことを期待したという説と、災いが「去る」に引っ掛けたという説があると説明員が教えてくれました。
■ 京都迎賓館
何ヶ月か前に、NHKでこの京都御所の番組を観て、ぜひ訪れてみたいと思っていました。宮内庁HPから予約が必要ですが、空きがあれば当日でも受け付けてくれます。日本という国、そして千年の都である京都という意地、この2つが重なり合って、それはそれは見事な建物と調度品でした。
正面の車寄せ。

正面玄関扉。檜の一枚板、そして七宝焼きでつくられた手すりが見事

扉が開くと、庭園が正面に見通せる設計です。

建物に入って右に折れた廊下がこんな感じ。和紙を通した柔らかい明かりに照らされて、ほっと肩から力が思わずに抜けてしまうような感覚に陥ります。


その先にあるのが聚楽の間。控えのための空間です。ここには外の明かりが入らないために、椅子は、色が鮮やかな赤を基調とした西陣織の布を使って作られている。

椅子の前には、京都美術館から訪問する賓客に合わせて絵が借り出して展示される。観覧した際に展示されていた1対の絵はこちら。波の揺らぎが立体的に表現されていて、思わず「欲しい!」と感じてしまいました。

一つ目の大広間は夕映えの間です。

二つ目の大広間は藤の間。絨毯敷きで、洋食に対応できるようテーブルセッティングが部屋の片隅に展示してありました。

テーブルの上には食器類が展示されており、

カトラリー類も見事としか言い様がない。

部屋の全景はこんな感じですが、天井の照明も3段に上げ下げができるようになっている。

部屋奥の扉には、金とプラチナ箔が伝統技能「截金」という技術で装飾されている。人間国宝の故 江里佐代子さんの作品で、金と銀が互いの美の長所を引き立て合いながら、二つの色が交差するさまに、「人と人との出会いもそうありたい」との願いが込められているのだとか。作品名は、「響流光韻(こうるこういん)」。その華麗さには思わず目をみはるとともに、製作している間は途轍もない緊張感だったろうという想いと、半端ない熟練の技ゆえの作品だと思うと、思わずため息が漏れる

三つ目の大広間である桐の間は和室。掘りごたつ風になっており、その上には見事な漆塗りの大テーブル。

正面から見た様子。

椅子の背には、五七の桐の紋が蒔絵になって入っています。この五七の桐は、元々は皇室の裏紋として使用されていたものが今では日本国政府の紋章として使用されており、そのため京都御所だけでなく御所を紹介するHPにもしっかり入っています。各椅子の背にも紋が入っているのですが、椅子ごとに色合いが少しずつ違っているという手の懲りよう。

そして庭園がこちら。隠されて見えないが、底の浅い和舟で舟遊びができるようになっている。

一つ目の大広間前の廊下の上段から覗く庇に、庭園の池に反射した光があたり、えも言われぬ風情を醸し出していたのが今でもまじまじと蘇ってきます。眼福という言葉はこのためにあるのかと思えるほどの至福の時間を過ごすことができました。場所は、京都御苑の中、京都御所の東側です。
■ 仙洞御所
京都御所の南東、京都迎賓館の南側にある御所。京都御所は天皇が暮らし、政を執り行うための場であるために、退位して上皇となられた方々が暮らすための場として作られたのが仙洞御所です。
こちらも塀に囲まれています。

生活をされる場である建物がこちら。元々は、当たり前ですが和風だったものを、英国エドワード皇太子が訪問された折に、内装を洋風に変えたのだそうです。今でもベッドが設えてあり、エアコンも完備されているとのこと。今でも皇室の方がお泊りされるそうです。


庭園は回遊式で、どの位置から見ても愉しめる設計になっていることと、紅葉が多いために秋には事の外綺麗に色づくそうです。



藤棚のある橋、そして所々に南天が植えられており、藤色に染まる中での赤はさぞかし印象的な風景なんでしょうね。この御所も、京都御苑の中にあり、京都御所の南東に位置している。
正式な名前は賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)。星の数ほどお寺がある京都でも、最古参の部類に入る由緒正しいお寺さんとのこと。説明員の方が、境内である糺の森(ただすのもり)から、弥生時代のものと見られる品々が発掘されているとお話しされていました。この糺の森(ただすのもり)というのが広い。鬱蒼と木々が茂る12万4千平米の敷地(甲子園球場の3倍の広さ)の中に、下鴨神社とその末社が点在しています。


楼門をくぐった先が本殿。結婚式が何組が予定されておりました。

本殿には、祭ってあるのが賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)と玉依姫命(たまよりひめのみこと)。川から流れてきた矢を拾って持って帰った玉依姫命が身ごもり男の子(賀茂別雷命)が生まれた。賀茂別雷命が成人し、その祝宴の席で祖父の賀茂建角身命が「お前のお父さんにもこの酒をあげなさい」と言ったところ、賀茂別雷命は屋根を突き抜け天に昇っていったので、この子の父が雷神であることがわかったという言い伝え。
期間限定の特別拝観で見ることができた一つは大炊殿(おおいどの)。こちらも重要文化財。

京都のお寺は拝観料を取るが、神社は取らないと言う。そのためか、下鴨神社のトイレには紙が置いておらず、自販機で購入することになっている。昔の鉄道駅のトイレみたいに。ちょっといただけない。
■ 河合神社
糺の森の中にある神社。神武天皇の母を祭っているという。


方丈記で有名な鴨長明は、この河合神社の禰宜の職に就任を望んだが叶わず、出家して閑居生活を行った折に書き記したのが方丈記だとか。鴨長明は不遇な人生を送ったらしく、下鴨神社の神事を統率する禰宜の次男として生まれながら、神職としての出世の道を閉ざされ、その後源実朝の和歌の師として鎌倉へ下向したものの、受け入られず失敗しているのだそうだ。方丈記のベースに流れる無常観は、こんな人生から生まれたのだろう。
■ 京都御所
総面積65ヘクタール(65万平米)の京都御苑の中心部にあり、南北450メートル、東西250メートルの築地塀で囲まれた中にある、昔の皇居ですね。塀はこんな感じ。

天皇しか通れな正式な門である建礼門。退位された現上皇も、退位された後はこの門ではなく、東側にある建春門を使われるとのこと。

日常の生活の場であった清涼殿。

こちらは大正天皇がお越しになる際に作られた新御車寄。自動車が横付けできるようになっている他、御所の中で電気の照明が入っている唯一の建物なのだそうだ。

御学問所

御学問所前の庭園。

日本国のトップが暮らされ、政をされていた場所であるだけに、きびしい身分の分け隔てがあちこちに見られる。例えば、殿上の間という控え室が3つ続きであるのだが、右2つ(虎と鶴の間)は車寄から入れるのに対して、諸太夫の間は車寄から歩いて軒先まで行き、履物を脱いでしか部屋に入れない構造になっている。出入りする門が厳格に定められていることは先に書いたとおり。
面白かった情報として、御所の屋根には3種類ある。瓦と銅版葺き、そして檜皮葺(ひわだぶき)。高貴な方が暮らされる建物には瓦は使われないとのこと。理由は、人が足で踏んだ土を材料にして作った瓦を頭の上に置くことは高貴な方には相応しくないからとのこと。そう言われて門を見てみると、天皇しか通れない建礼門の屋根は檜皮葺であったのに対して、我々が使用した清所門の屋根は瓦葺でした。
また、御所の北東(鬼門)には小さな凹みがあり、鬼門を守る猿が据えられている。北東方向には比叡山があり、これも京都を守るためにここに延暦寺が建てられた。なぜ猿なの?と訊いたら、一説では北東と逆の方向(申の方角)とすることで、鬼門がどんどん遠くに外れていくことを期待したという説と、災いが「去る」に引っ掛けたという説があると説明員が教えてくれました。
■ 京都迎賓館
何ヶ月か前に、NHKでこの京都御所の番組を観て、ぜひ訪れてみたいと思っていました。宮内庁HPから予約が必要ですが、空きがあれば当日でも受け付けてくれます。日本という国、そして千年の都である京都という意地、この2つが重なり合って、それはそれは見事な建物と調度品でした。
正面の車寄せ。

正面玄関扉。檜の一枚板、そして七宝焼きでつくられた手すりが見事

扉が開くと、庭園が正面に見通せる設計です。

建物に入って右に折れた廊下がこんな感じ。和紙を通した柔らかい明かりに照らされて、ほっと肩から力が思わずに抜けてしまうような感覚に陥ります。


その先にあるのが聚楽の間。控えのための空間です。ここには外の明かりが入らないために、椅子は、色が鮮やかな赤を基調とした西陣織の布を使って作られている。

椅子の前には、京都美術館から訪問する賓客に合わせて絵が借り出して展示される。観覧した際に展示されていた1対の絵はこちら。波の揺らぎが立体的に表現されていて、思わず「欲しい!」と感じてしまいました。

一つ目の大広間は夕映えの間です。

二つ目の大広間は藤の間。絨毯敷きで、洋食に対応できるようテーブルセッティングが部屋の片隅に展示してありました。

テーブルの上には食器類が展示されており、

カトラリー類も見事としか言い様がない。

部屋の全景はこんな感じですが、天井の照明も3段に上げ下げができるようになっている。

部屋奥の扉には、金とプラチナ箔が伝統技能「截金」という技術で装飾されている。人間国宝の故 江里佐代子さんの作品で、金と銀が互いの美の長所を引き立て合いながら、二つの色が交差するさまに、「人と人との出会いもそうありたい」との願いが込められているのだとか。作品名は、「響流光韻(こうるこういん)」。その華麗さには思わず目をみはるとともに、製作している間は途轍もない緊張感だったろうという想いと、半端ない熟練の技ゆえの作品だと思うと、思わずため息が漏れる

三つ目の大広間である桐の間は和室。掘りごたつ風になっており、その上には見事な漆塗りの大テーブル。

正面から見た様子。

椅子の背には、五七の桐の紋が蒔絵になって入っています。この五七の桐は、元々は皇室の裏紋として使用されていたものが今では日本国政府の紋章として使用されており、そのため京都御所だけでなく御所を紹介するHPにもしっかり入っています。各椅子の背にも紋が入っているのですが、椅子ごとに色合いが少しずつ違っているという手の懲りよう。

そして庭園がこちら。隠されて見えないが、底の浅い和舟で舟遊びができるようになっている。

一つ目の大広間前の廊下の上段から覗く庇に、庭園の池に反射した光があたり、えも言われぬ風情を醸し出していたのが今でもまじまじと蘇ってきます。眼福という言葉はこのためにあるのかと思えるほどの至福の時間を過ごすことができました。場所は、京都御苑の中、京都御所の東側です。
■ 仙洞御所
京都御所の南東、京都迎賓館の南側にある御所。京都御所は天皇が暮らし、政を執り行うための場であるために、退位して上皇となられた方々が暮らすための場として作られたのが仙洞御所です。
こちらも塀に囲まれています。

生活をされる場である建物がこちら。元々は、当たり前ですが和風だったものを、英国エドワード皇太子が訪問された折に、内装を洋風に変えたのだそうです。今でもベッドが設えてあり、エアコンも完備されているとのこと。今でも皇室の方がお泊りされるそうです。


庭園は回遊式で、どの位置から見ても愉しめる設計になっていることと、紅葉が多いために秋には事の外綺麗に色づくそうです。



藤棚のある橋、そして所々に南天が植えられており、藤色に染まる中での赤はさぞかし印象的な風景なんでしょうね。この御所も、京都御苑の中にあり、京都御所の南東に位置している。










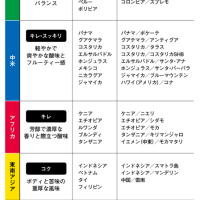
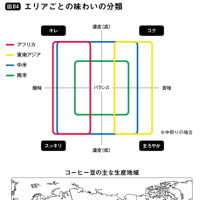













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます