チェコ・スロバキア・ウクライナ合作の映画でまぎれもない傑作だけど、
約3時間の長さの映画で、さらにその100倍くらい疲れました。
残虐描写がこれでもかと地味なリアリティで続いて、冒頭からずっと全身緊張して見ました。
ヴェネツィア映画祭史上最大の問題作!と書かれるだけのことはある。。。
誰にでもはオススメはできないですね。
ほんま疲れて帰りの電車の中でもまだ息切れしてるくらいでした。
この映画のポスターと邦題は良いです。英語の題がペインデッドバードで、
映画の中に出てくるエピソードから取られています。
羽に色をつけられた鳥は群れに帰っても仲間と認識してもらえず攻撃され
落ちて死んでしまうのですが、これは大変わかりやすく
主人公の人生と重なるところがあって平易でいいタイトルだけど、
このヘビーさには「異端」という強く重い言葉の方が合うと思う。
駄目邦題ばかりの中にあって、これはでかした、と珍しく思いました。
極端にセリフの少ない映画で、説明的なところは全くなく
モノクロ35mmで撮られたフィルムの映像は、それは美しいです。
残虐なシーンさえ美しさはあるし、汚いシーンにも美しさがある。
お話も壮絶なら、映像の美しさも壮絶でした。
時代は第二次世界大戦末期、ホロコーストから逃げ延びた少年は
親と逸れて親戚のおばあさんの家に避難します。
というのもそう思われるというだけで説明がないので、このおばあさんとの関係も
どこからどう逃げ延びたのかもよくわからないのですが、ともかく
おばあさんが死んでしまったあと、家に帰りたい両親に会いたいと放浪することになります。
全部で九つの章に分かれてて、それぞれの章にそこに出てくる人の名前がついています。
ここは以前見た、やや不穏ながら明るさのある不思議なロシア映画
「神聖なる一族24人の娘たち」を思い出しました。
全く内容の違う映画だけど、こちらも女性の名前で章がわかれている。
そしてロシアや東欧のどこか寓話的な奥行きが、西側の映画とは違う趣で似ています。
「神聖なる」の方は短い章でそれぞれの女性がスケッチ風に描かれますが
「異端の鳥」は各章で必ず主人公がひどい目に遭います。
ひどい目、というと柔らかく聞こえるけど、壮絶というか陰惨というか
肉体的な痛み以上に、普通の人々の悪意や敵意の攻撃が凄まじいのです。
これは、確かに見てられなくて退席する人続出というのも頷けるわ。
わたしも何度も目を手で覆いました。
目を手で覆うと過激なシーンを目で見ないことはできるけど、
人の悪意や敵意やずるさや浅ましさや卑しさは、視覚でなくても伝わって
見ている側にはそちらのダメージもかなりのものです。
差別、排除、欲望、吝嗇、嫉妬・・・人間がいやになりますねぇ。地獄です。
そして少年の心が荒んでいき死んでいくのも当然としか思えなくなります。
最後の章の名前がラストに出てきますが、そこはうまくできていて唸りました。
お父さんの手首に入ってた番号を見せるだけでそれまでの年月をわからせて
そこで少年が自分の名前を取り戻すという回収は、見事。
長くなるけど公式サイトからイントロダクション部分を引用します。
昨年のヴェネツィア国際映画祭において、『ジョーカー』以上に話題を集めた作品が『異端の鳥』だ。第二次大戦中、ナチスのホロコーストから逃れるために、たった一人で田舎に疎開した少年が差別と迫害に抗い、想像を絶する大自然と格闘しながら強く生き抜く姿と、異物である少年を徹底的に攻撃する“普通の人々”を赤裸々に描いた本作は、ヴェネツィア国際映画祭のコンペティション部門で上映されると、少年の置かれた過酷な状況が賛否を呼び、途中退場者が続出。しかし、同時に10分間のスタンディングオベーションを受け、ユニセフ賞を受賞し、同映画祭屈指の話題作となった。本作はその後も多くの批評家から絶賛を浴び、アカデミー賞®国際長編映画賞のチェコ代表にも選ばれ、本選でもショートリスト9本に選出。第32回東京国際映画祭においても「ワールド・フォーカス」部門で上映され、高い評価を得た。
原作は自身もホロコーストの生き残りである、ポーランドの作家イェジー・コシンスキが1965年に発表した代表作「ペインティッド・バード(初版邦題:異端の鳥)」。ポーランドでは発禁書となり、作家自身も後に謎の自殺を遂げた“いわくつきの傑作”を映画化するために、チェコ出身のヴァーツラフ・マルホウル監督は3年をかけて17のバージョンのシナリオを用意。資金調達に4年をかけ、さらに主演のペトル・コトラールが自然に成長していく様を描く為、撮影に2年を費やし、最終的に計11年もの歳月をかけて映像化した。
撮影監督を務めたウラジミール・スムットニーは、『コーリャ 愛のプラハ』でアカデミー賞®国際長編映画賞を受賞し、チェコのアカデミー賞であるチェコ・ライオン賞最優秀映画賞を7度も受賞しているチェコ映画界の巨匠である。舞台となる国や場所を特定されないように使用される言語は、人工言語「スラヴィック・エスペラント語」を採用。シネスコ、モノクロームの圧倒的な映像美で描かれる約3時間の物語は、映画的な驚異と奇跡に満ちている。
迫害を生き抜くうちに徐々に心を失っていく少年を体当たりで演じ切ったのは、新人のペトル・コトラール。他にもステラン・スカルスガルド、ハーヴェイ・カイテル、ジュリアン・サンズ、バリー・ペッパー、ウド・キアーなどのいぶし銀の名優たちが顔を揃えている。
人はなぜ異質な存在を排除しようとするのか? ホロコーストの源流を辿り戦争と人間の本性に迫る、美しくも残酷な衝撃作は、観る者の心を激しく揺さぶり問いかけてくる。
主人公は無名の新人少年らしいけど、素晴らしい演技でした。
彼の眼差しは忘れられない。
ステラン・スカルガルドやハーヴェイ・カイテル、ジュリアン・サンズなど
いい俳優も要所要所に出ていてその点でも見応えがあります。
あと、残虐シーンは他にもたくさんあったけど、印象に残ったのは
ネズミのシーンで、あ、「1984年」だ!と、あのディストピア小説の中で
想像を超えてゾッとしたシーンを思い出しました。
そういうわけで誰にでもお勧めはできない映画だけど、
文芸映画が好きで、過酷な描写に耐える自信のある人は見てほしいです。
映画としては本当に傑作なので。












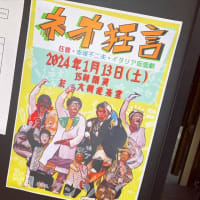





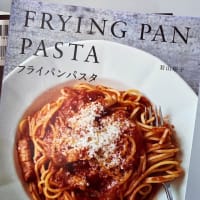

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます