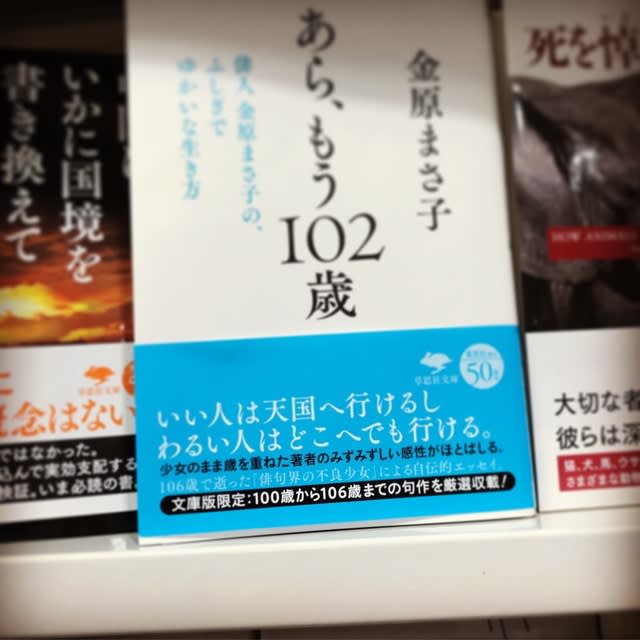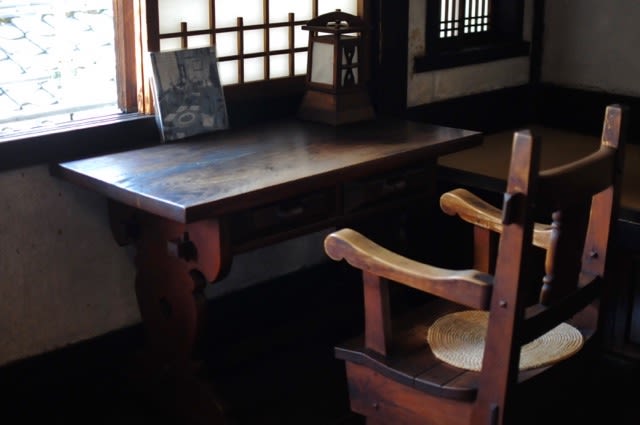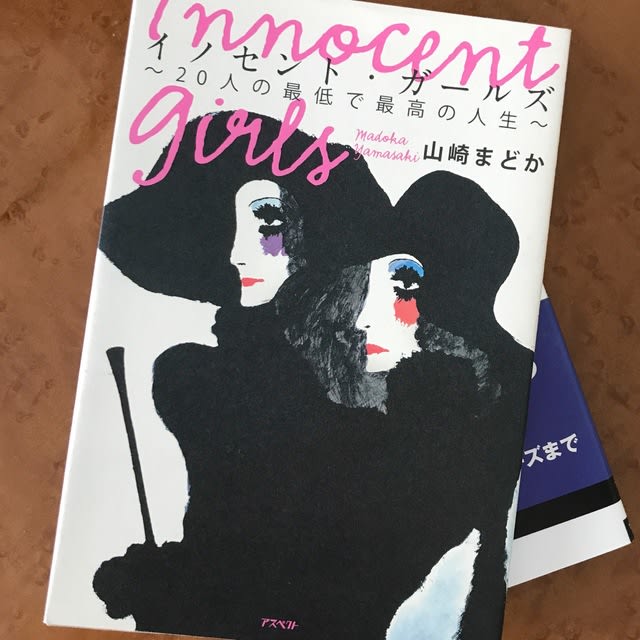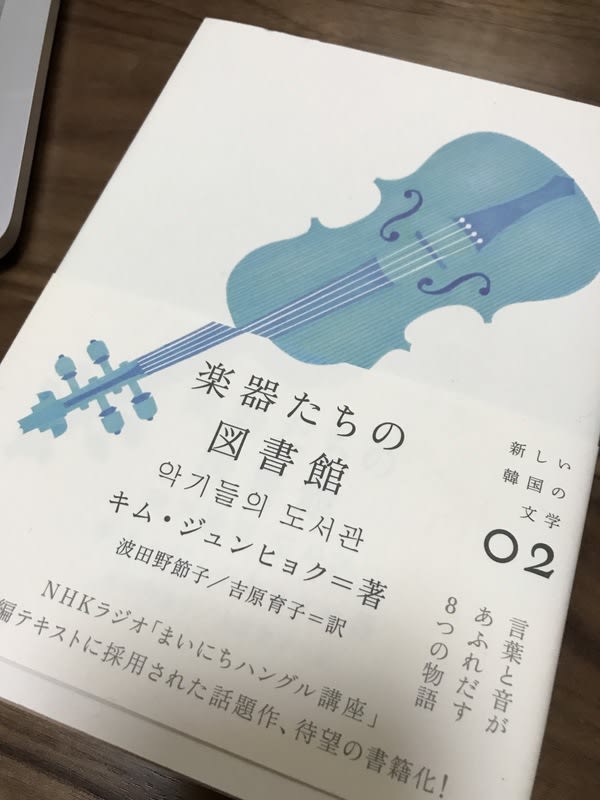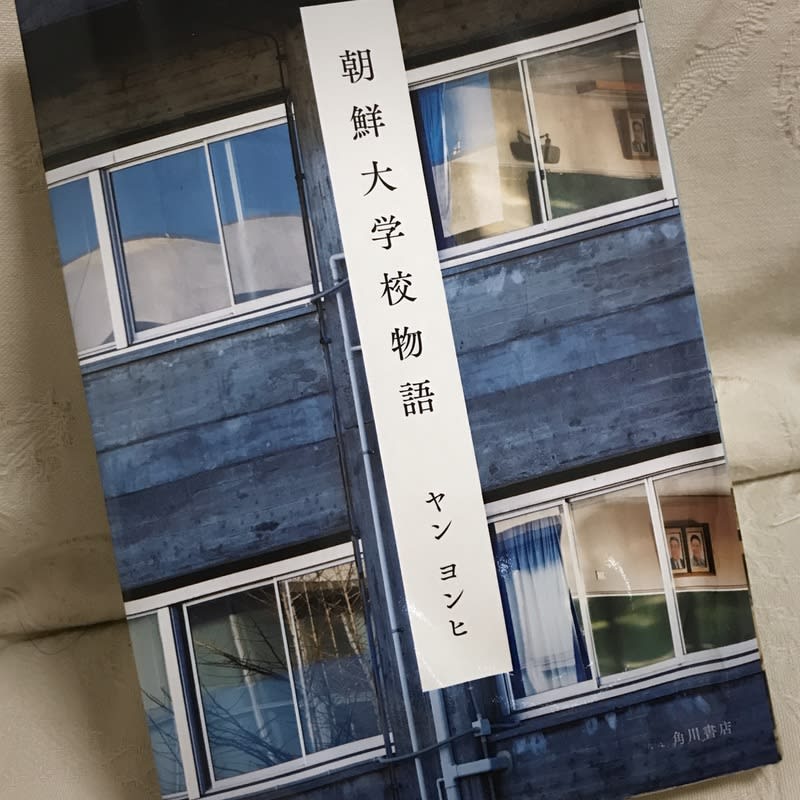石牟礼道子さんの本を初めて読みました。苦海浄土を読みたかったんだけど
ちょっと中身も量も大きすぎて、手頃な1冊を最初に手に取った。そして、
ああ、ああ、と、この世界の豊饒に最初の2ページからもう酔いしれることになった。
中上健次を思い出すほどの濃密な世界だけど、
いわゆる男と女の違いの典型を見るような違いがある。
もっと澄んでいてもっと柔らかくもっと分け隔てのない世界だなぁ。
お風呂で読んでいるので、少しずつ読み終わるのにはひと月くらいかかりそうと思い、
これからひと月も、この世界を味わえるのかと思うと幸せな気分になった。
以前本を読めなくなったことがあって、今は随分回復したけどやっぱり読むのが遅くて
一行を何度も読まないと意味が入ってこなくて、
先に進めないのが腹立たしい時もあるんだけど、この本は、それが全然気にならない。
同じところに好きなだけ止まっていても、幸せで落ち着いていられました。
ゆっくりゆっくり読んで、明日読み終わるというときには寂しくなった。
そして、苦海浄土も読んでいない自分のお馬鹿さを心底反省した。絶対読むぞ。
雪うろ、馬の足音、残された香り高い蘭の花ひとつ、垣根を越える自由なものの魂、
見えない客人たちの素晴らしいイメージ。
真に普遍的なものは均一で薄っぺらなグローバルの中ではなく
土着の独自の地域性の中にあるのではないかと思ってるけど、まさにそういう本。
すべてのものについている音の精。
雪の夜には、何年分も休む「もの」たち。
雪をかぶって転がる中身のないどんぐりの帽子のかわいさ。猫貝。
最初は、ただただここに書かれている世界の純度の高い濃密さにうっとりしていたけど、
後半になると現実世界の切なさが胸を突いて、
小さいみっちんの心の痛みがつらくて切なくて
愛おしくてたまらなくて胸がきゅうきゅう苦しくて涙が出る。
虐げられている人たちの強く優しく大きな魂をすっぽり感じることのできる
小さな女の子みっちんの魂。
みっちんは、3つ4つの女の子。
見えない人の気配や音に気付き、心が遠くに行く盲目の祖母や、
いつも犬の子をふところに入れてるさっちん、
挨拶が誰よりも上手な片目のヒロム兄やん
片足の仙造やん、火葬場の岩殿(いわどん)、など
「すこし神様になりかけて」いて
人からは叩かれたり唾を吐かれたりすることのある優しい人達の側にいつもいる。
そしてこんなに小さいのに、見える世界の美しさも、見えない世界の豊かさも、
人や世の切なさも、感じてしまう子。
睡蓮の葉っぱの露の玉や、小川の岸の草の葉先で、今にもこぼれ落ちそうになっている露の玉を見かけると、息が止まるかと思うほど、胸がどきんとすることがありました。
(生まれる前のわたしかもしれん!)
と思ってしまうからです。生まれる前の自分、ああなんとその自分に逢いたいことか。みっちんが、水とか露とかを見て魂がとろとろなるのは、そういうわけなのです。
お風呂のお湯まで優しく思えるほどこの世界に浸った後に、お風呂を出て耳をすますと
ここは、片足の蘭取りじいさんが馬で行く雪におおわれた地方ではなく、
駅と国道に面したうるさくてつまらない郊外都市で、
雨の音より、雨を轢いてジリジリ言うタイヤの音が大きい街なかなのだった。
車の減る夜中もうるさいだけで、星の音も聞こえやしない。ちぇ。
でも、お風呂上りのしばらくだけ、わたしも良い魂の人になれているような気がする。
わたしが良い人間になるための、大事な宝物のひとつだなぁ。
そして、
読んでいるとき、このものすごく懐かしい世界は何だろうと
ずっと記憶を探ってたことを、半分くらい読んだところで思い出した!
子供の頃に読んだ庄野英二の「星の牧場」だ。
この本の、幻想的なシーンだ。とんでもなくやさしい。それと同じ稀有なやさしさ。
もう絶版だけど、そのうち中古で買って読み直そうかなぁ。
ちょっと中身も量も大きすぎて、手頃な1冊を最初に手に取った。そして、
ああ、ああ、と、この世界の豊饒に最初の2ページからもう酔いしれることになった。
中上健次を思い出すほどの濃密な世界だけど、
いわゆる男と女の違いの典型を見るような違いがある。
もっと澄んでいてもっと柔らかくもっと分け隔てのない世界だなぁ。
お風呂で読んでいるので、少しずつ読み終わるのにはひと月くらいかかりそうと思い、
これからひと月も、この世界を味わえるのかと思うと幸せな気分になった。
以前本を読めなくなったことがあって、今は随分回復したけどやっぱり読むのが遅くて
一行を何度も読まないと意味が入ってこなくて、
先に進めないのが腹立たしい時もあるんだけど、この本は、それが全然気にならない。
同じところに好きなだけ止まっていても、幸せで落ち着いていられました。
ゆっくりゆっくり読んで、明日読み終わるというときには寂しくなった。
そして、苦海浄土も読んでいない自分のお馬鹿さを心底反省した。絶対読むぞ。
雪うろ、馬の足音、残された香り高い蘭の花ひとつ、垣根を越える自由なものの魂、
見えない客人たちの素晴らしいイメージ。
真に普遍的なものは均一で薄っぺらなグローバルの中ではなく
土着の独自の地域性の中にあるのではないかと思ってるけど、まさにそういう本。
すべてのものについている音の精。
雪の夜には、何年分も休む「もの」たち。
雪をかぶって転がる中身のないどんぐりの帽子のかわいさ。猫貝。
最初は、ただただここに書かれている世界の純度の高い濃密さにうっとりしていたけど、
後半になると現実世界の切なさが胸を突いて、
小さいみっちんの心の痛みがつらくて切なくて
愛おしくてたまらなくて胸がきゅうきゅう苦しくて涙が出る。
虐げられている人たちの強く優しく大きな魂をすっぽり感じることのできる
小さな女の子みっちんの魂。
みっちんは、3つ4つの女の子。
見えない人の気配や音に気付き、心が遠くに行く盲目の祖母や、
いつも犬の子をふところに入れてるさっちん、
挨拶が誰よりも上手な片目のヒロム兄やん
片足の仙造やん、火葬場の岩殿(いわどん)、など
「すこし神様になりかけて」いて
人からは叩かれたり唾を吐かれたりすることのある優しい人達の側にいつもいる。
そしてこんなに小さいのに、見える世界の美しさも、見えない世界の豊かさも、
人や世の切なさも、感じてしまう子。
睡蓮の葉っぱの露の玉や、小川の岸の草の葉先で、今にもこぼれ落ちそうになっている露の玉を見かけると、息が止まるかと思うほど、胸がどきんとすることがありました。
(生まれる前のわたしかもしれん!)
と思ってしまうからです。生まれる前の自分、ああなんとその自分に逢いたいことか。みっちんが、水とか露とかを見て魂がとろとろなるのは、そういうわけなのです。
お風呂のお湯まで優しく思えるほどこの世界に浸った後に、お風呂を出て耳をすますと
ここは、片足の蘭取りじいさんが馬で行く雪におおわれた地方ではなく、
駅と国道に面したうるさくてつまらない郊外都市で、
雨の音より、雨を轢いてジリジリ言うタイヤの音が大きい街なかなのだった。
車の減る夜中もうるさいだけで、星の音も聞こえやしない。ちぇ。
でも、お風呂上りのしばらくだけ、わたしも良い魂の人になれているような気がする。
わたしが良い人間になるための、大事な宝物のひとつだなぁ。
そして、
読んでいるとき、このものすごく懐かしい世界は何だろうと
ずっと記憶を探ってたことを、半分くらい読んだところで思い出した!
子供の頃に読んだ庄野英二の「星の牧場」だ。
この本の、幻想的なシーンだ。とんでもなくやさしい。それと同じ稀有なやさしさ。
もう絶版だけど、そのうち中古で買って読み直そうかなぁ。