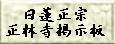平成十六年十二月度 広布唱題会の砌
(大日蓮 平成17年1月号 第707号 転載)
広布唱題会は、毎月、第一日曜日にそれぞれの寺院において行われておりますので、皆様方も所属されておる寺院に参詣されておることと思うのであります。総本山においても毎月、行っておりますが、この広布唱題会こそ、正法を真に受持し、弘宣して、その功徳をもって多くの人々を救済していき、さらに乱れた世の中に対して真の正法の功徳、清風を送って正しくしていくところの一番の本であるということを深くお考えいただきたいと思うのであります。
さて、顧みますれば、皆様方も既に御承知の如く、本年は大変な、いわゆる天変地夭等が盛んな年でありました。これを仏法の鏡にかけて見るならば、その原因が必ず存するのであります。世間の人々は眼前のことしか見ることができないために、その本当の原因をはっきり知ることができないのであります。しかし、人の心が悪ければ、必ずそれなりの天変地夭が起こるということは、大聖人様が『立正安国論』にお示しであり、また、あらゆる仏教の経典にも説かれておるところであります。
このようななかで、この世の中を真に浄化していく根本が宗祖日蓮大聖人様の大正法を正しく伝えるところの日蓮正宗の教えにある、また、その自行化他の唱題にあるということをお互いにしっかり認識し、その上からこの唱題行の意義にのっとって、自行化他の行業に邁進すべきであると存ずるのであります。 (中 略)
妙法の信行の功徳を確信して自ら行ずるとともに、また他の人々に、たとえひとことなりとも折伏を行ずる、すなわち一年に一人が一人の折伏を必ず行おうという覚悟を持って信心修行することが、お互いの真の成仏得道と信じる次第であります。
平成十六年十一月度 広布唱題会の砌
(大日蓮 平成16年12月号 第706号 転載)
大聖人様は「南無妙法蓮華経を唱えよ」ということを常に仰せあそばされました。法華経を説かれたのは釈尊で、法華経のなかにその修行として受持・読・誦・解説・書写という五種の修行は説かれております。しかし、釈尊は「南無妙法蓮華経を唱えよ」ということを、法華経の一部八巻のなかのどこにもおっしゃってはおりません。また、その後、天台、伝教その他、ありとあらゆる聖者が現れて、法華経の深い意義を述べましたけれども、やはり「常に南無妙法蓮華経を唱えよ」ということをはっきり言われた方はいないのであります。しかるに大聖人様は御出現あそばされて、宗旨建立の初めから「南無妙法蓮華経と唱えることが最も大切である」ということを常に御指南であります。
そこには身口意の三業という意義が当然あります。我々の生活のことごとくが、身体と口と意の三つで成り立っております。これ以外に我々の生活の内容はないのです。常になんらかのことを考えておるのは意であります。なんらかの行動を起こすのは身体であります。また、実際にそれを表すのが口であります。したがって、口で正しい仏法の内容をはっきり顕していくということが最も大切であり、大聖人様も、
「口業の功徳を成就せり」(御書一一五頁)
ということを仰せであります。口業、すなわち口で唱えるということです。 (中 略)
口をはっきり開けてお経を読み、また、お題目をしっかり唱えるということこそ大切なのです。よって、まず口業の功徳が成就することによって、さらに身体への功徳、また意への功徳がはっきりしてくるという意味が当然、存するのであります。
ですから、特にこの唱題行は我々自身の信心修行上からも、鍛錬の上からも非常に大切であるとともに、自行化他にわたっての道であるということをよくお考えいただきたいと思います。
平成十六年十月度 広布唱題会の砌
(大日蓮 平成16年11月号 第705号 転載)
御会式に出席することは、いわゆる本因妙の修行の一環であり、過去遠々劫以来の謗法罪障を消滅し、また何より肝心なことは末法下種の主師親三徳、宗祖大聖人様への真の御報恩の行業となるのであります。(中 略)
大聖人様は、
「閻浮の内の人は病の身なり、法華経の薬あり、三事すでに相応しぬ、一身いかでかたすからざるべき」(御書八九一)
と高橋入道に御指南であります。この御書を拝してみますと、高橋殿はお身体の健康を害されておったようですが、よく考えますれば、末法における日本国乃至世界の衆生はことごとく病の身であります。
この病には心の病、身体の病と二つありますが、特に心の病が大きな罪障として世界中に様々な不幸を呼んでおる姿があります。我々の生活のなかでも大変な謗法罪障が色々な面で存在し、そしてそのなかで、創価学会のように正法を見失って邪法に転落していくような姿もあります。 (中 略)
特に例月の唱題会は本当に正しい大聖人の大仏法を持つ、ただ一つの宗団において、この妙法を受持する功徳をしっかり顕しつつ、自らも幸せになり、また多くの人々を正しく導いていくところの、広宣流布への我々の信心と志の表れであります。
皆様方も、末寺においても、各月における唱題会に多くの人々を誘いつつ必ず参加して、これからも毎月、この唱題会が立派に行われるように御精進を願いたいと思います。
平成十六年九月度 広布唱題会の砌
(大日蓮 平成16年10月号 第704号 転載)
今朝、皆様が大勢お集まりになって、御本尊様に向かい奉り一時間の真剣な唱題を行いました。これは皆様方一人ひとりが、この客殿において久遠元初根本の法華経を行ぜられたのであります。ここに深い、大切な意義と功徳が存するのであります。
下種仏法を頭で考え、「これがこうだ、あれがああだ」といって、いくら頭をひねくり回しても、世界中のなかの一人として、本当の宇宙森羅万象のすべてに通ずるところの大真如の姿を知る人はいないのであります。また、これを悟る人もありません。ただ、目の先において色々なことを多少学び、それによって自分がある程度解ったような顔をしており、また、そのような考えを持っておりますが、結局、本当の法界の大真如というものを知ることはできません。(中 略)
皆さん方一人ひとりが何も御存じなくとも、また、特に少しでも勉強されている方はなお結構でありますけれども、やはり仏法は行ということがあくまで根本であります。その行の元は信によるのでありますから、信をもって御本尊様に唱題し奉るところに、未来永劫の上からの我々の真の成仏の意義が、功徳がそこに必ず顕れるということを深く確信していただきたいと思います。そして、そこにまた我々の真の成仏の意義が、功徳がそこに必ず顕れるということを深く確信していただきたいと思います。そして、そこにまた我々の生活の様々な在り方の上からの真の離苦得楽、様々な意味の大きな功徳を生ずることを確信すべきであります。
御法主日顕上人猊下御講義 第53回全国教師講習会の砌
事の戒壇の本義について
平成16年8月26日(於総本山大講堂)
平成十六年八月度 広布唱題会の砌
(大日蓮 平成16年9月号 第703号 転載)
総本山においてもただいま唱題会を執り行いましたが、本日は少年部大会が行われるということで、坊ちゃん、嬢ちゃん方、また付き添いの方など大勢の方々が集まって、ここに唱題行をにぎにぎしく執り行った次第であります。(中 略)
子供さん達のなかには、わけが解らないでここに来ておる人も多いと思います。よって一時間の唱題行はずいぶんつらかったと思うのです。毎日、親御さんと一緒に唱題行を行っておる人もいると思いますが、それでも一時間というのは子供にとっては長かったと思います。あちらこちらで居眠りをしたり、あるいは足が痛いためにしょっちゅう身体を動かしたり、色々なことをしていた人もいると思います。今、こうして話していても、私の話を聞いていないで「早くどこかへ行きたいな」と思っている人もいると思うのです。しかし私は、どんなにつらくても、あるいはおもしろくなくても、また足が痛くて足を崩してでも、こうして御本尊様の前に座っておるということは、三大秘法のなかの「所践の義」に当たると思うのであります。 (中 略)
小さな子供ですから、信心の気持ちはあまりない人もいるかも知れません。しかし、とにかく親御さんに従って、あるいは友達と一緒にこうして来ておるというなかにおいて、おのずと霊場に身体を投じ、この客殿において御本尊様の前で一時間の唱題をするというところに、おのずからその人の未来永劫に向かっての命のなかに尊い「戒」の功徳、つまり「防非止悪」の功徳が生まれていくと思うのであります。 (中 略)
正法を受持し、解らなくてもよいからお題目を唱えていくなかにおいて、必ず御本尊様の大きな功徳を身に当てて受けていくことができると思うのであります。
平成十六年七月度 広布唱題会の砌
(大日蓮 平成16年8月号 第702号 転載)
立正安国の「正」という字は「一に止まる」と書きます。すなわち『立正安国論』におきましても、
「実乗の一善に帰せよ」(御書二五〇頁)
ということを仰せになっております。「実乗の一善」とは、一代五十年のあらゆる諸経のなかにおいてただ法華経のみが真の実乗の一善であります。ここに帰するところに初めて、正法治国の実が挙がるのであるということを御指南であり、これはまた当時のみならず、末法万年を通ずる、すべての時期にわたる指導原理であります。 そのために大聖人様は「一に止まる」ところの根本の法体であるところの法華経の教えを、権実相対、本迹相対、種脱相対、三重の秘伝の上から、本門の大御本尊としてお顕しになりました。これが法華経の根本であります。その法華経の根本のところに一切衆生を真に成仏得道に導くところの大法の利益、功徳が存するのであります。この大法を間違いなく、正しく受け継いで信心修行しておるのが、我が日蓮正宗の僧侶であり、御信徒であります。世界広しといえども、これ以外に真の正法を受持信行するところの団体はないということを皆様方がしっかりと確信されるべきであると思うのであります。(中 略)
一人でも多くの人が真の正法に目覚めるところに広宣流布の一歩一歩が進んでいくのであるということを深く確信されまして皆様のいよいよの信行倍増を心からお祈りいたし、今晩の挨拶とする次第であります。
本日はご苦労様でした。
平成十六年六月度 広布唱題会の砌
(大日蓮 平成16年7月号 第701号 転載)
考えますれば、今夕の唱題行も実に尊い行であると思うのであります。この講習会は色々な面で大聖人様の仏法を行じ、また学ぶということを目的として行っておるのであります。おそらく、ここにいらっしゃる皆様方、一人ひとりの方々が御承知であると思いますが、『諸法実相抄』の最後に、
「行学の二道をはげみ候べし。行学たへなば仏法はあるべからず。我もいたし人をも教化候へ。行学は信心よりをこるべく候。力あらば一文一句なりともかたらせ給ふべし」(新編六六八頁)
という御文があります。
私が思いますのに、行学ということのなかにおいて、力あらば他の人に向かって一文一句でも説いていくということ、ここに行学の二道の結論としての、すなわち我々が日常において仏法を行ずる一番根本の心掛けが示されておると思うのであります。一生懸命に勉強しても、それをただ自分の肚のなかだけにしまっておくのではなく、尊い仏法の意義をたとえひとことなりとも他に向かって説いていくということこそ本当に大切であり、それが正しく法を行ずる姿であると存じます。 (中 略)
今回の講習会に当たり、総本山においでになった皆様方こそ、世界唯一の真の正法である大聖人様の大法を受持し、また、これを行じ、学んでおる方々であります。したがって、この法を行ずるところにおいて、必ず正しい功徳が生ずることは間違いありません。
平成十六年五月度 広布唱題会の砌
(大日蓮 平成16年6月号 第700号 転載)
皆様も御承知のように、五月は田植えの季節であります。総本山周辺を歩いておりますと、農家の方々が五月の初旬から中旬にかけて一斉に田植えを行っております。この植えられた苗は、夏の太陽の恵みによって秋に豊かな実を結び、秋収冬蔵という形になるのであります。
これがもし間違って、秋に田植えをする、あるいは冬に田植えをしたらどうなるかと言えば、稲は全く生長せず、実を結ぶこともなく、収穫は全くなくなるのであります。
大聖人様は『教機時国抄』という御書において、
「仏教を弘めん人は必ず時を知るべし」(御書二七〇)
と仰せであります。稲においても、その他、世の中のあらゆる事柄は時に順じて初めて成就するのであり、時に逆らい、また狂ったならば、これは全くその成果を得ることができないのであります。
私どもの生活のなかにおいても全くそのとおりでありまして、朝になったら起きるのであります。そしてしっかりと勤行、唱題をする。これも一つの時であります。この時を外したならば、その報いが様々な誤った形となって現れてまいります。 (中 略)
皆様におかれましては、この世の中を真に救っていく道、また三世にわたる即身成仏の道は、大聖人の三大秘法を受持信行するとともに、他に向かってこれを勧めていく、すなわちその人の誤った宗教観を対話の上に破折しつつ、この正法を護持せしめていくという自行化他の信心修行にあるということをお互いに深く感じられて、いよいよの御精進をお祈りする次第であります。
平成十六年四月度 広布唱題会の砌
(大日蓮 平成16年5月号 第699号 転載)
我々が唱え奉る南無妙法蓮華経は、申すまでもなく大聖人様が、
「日蓮がたましひをすみにそめながしてかきて候ぞ」(新編御書六八五頁)
と仰せあそばされたところの本門戒壇の大御本尊様、そして、その本義を受けて御歴代上人が衆生化導のために御書写申し上げたところの御本尊様の御当体、すなわち「南無妙法蓮華経 日蓮」の御当体、御名がそのまま南無妙法蓮華経であります。つまり、日蓮大聖人様の下種本仏としてのお悟りの一切が、この題目に篭められておるのであります。ですから、我々が御本尊様を拝することにおいて初めて南無妙法蓮華経の法体、そして実体が明らかに拝せられるのであります。
邪宗教では過去帳を拝んだり、ただお題目を唱えればよいというような考えから、末法の上の成仏の法体を知らず、空虚な題目になっております。ですから、根本の法体をはっきりするということは、正法正義の所以を拝して本尊を簡び、正しい御本尊に向かって唱題をすることが最も大切であります。いわゆる妙法蓮華経の大きな法の当体、そして功徳はことごとく日蓮大聖人様の御所持の妙法であるということの上から我々が拝するときに、我々が仏様の功徳をそのまま受けることができるのであります。(中 略)
皆様方にはこの仏法に縁せられたことを深く喜ばれ、臨終の夕べに至るまでこの妙法を受持して、そして来世においてはさらに真の成仏の境界を得つつ、未来に向かっての永劫の生命の上に用きを起こしていくということが大切であります。
平成十六年三月度 広布唱題会の砌
(大日蓮 平成16年4月号 第698号 転載)
本日は、全国の各寺院においても一斉に唱題会を執り行っております。これは、いわゆる広布のための唱題行でありますが、また、一人ひとりの僧侶ならびに信徒が、自己自身の命を本当に正しく鍛えていく行であり、それによって成仏の道につながる功徳が顕れていくという意味において、この唱題行が執り行われるのであります。(中 略)
薬王菩薩本事品において、
「渡に船を得たるが如く(中 略)貧しきに宝を得たるが如く」(法華経開結五三五頁)
と、様々な意味での功徳がたくさん説かれております。一切の人々の悩み、苦しみ、またそれによるところの願い、欲するところの心は無量でありますが、要するに、自己自身の過去の謗法の悪業によって今日の悩みがあるということをしっかり知っておけば、そこに本末究竟が常に迷いと悩みのなかで繰り返されることはなく、さらに妙法をしっかり信ずるところに、そのまま仏の体が顕れ、その体の上に用きとして、本末の末のほうの、あらゆる意味での諸願成就、罪障消滅したところの真の幸せな姿が、その人の生活、心のなかに顕れてくるのであります。ここのところを我々はしっかり見定めつつ、修行していくことが肝心であります。(中 略)
日蓮正宗において大聖人様が顕された大御本尊様を根本とする三大秘法の在り方を、常に衆生に向かって説き示していかなければならないのであります。このところにこそ、我々の広宣流布へ向かっての道が存するのです。
平成十六年二月度 広布唱題会の
(大日蓮 平成16年3月号 第697号 転載))
唱題をするということ、また広宣流布に進むということの目的は、まず我々一人ひとりが正法によって真の成仏を遂げていくということにあるのであります。(中 略)
南無妙法蓮華経を強く信じ、「この御本尊のほかに成仏の道はなし」と深く心得て、いかなる難をも、また、あらゆる境遇のなかにおいても、この法が根本の法であるということを固く信じて、信心修行、唱題をしていくその人の当体がそのまま仏であるということであります。そして、それをそのまま自行化他の上から、自らも信ずるとともに他をも勧め、導いていくということが大切であります。
世の中の人々は実に様々で不完全な人生観、世界観のなかにおける自我に執われております。正しい宗教とは仏法であり、いわゆる日蓮大聖人様の三大秘法であります。そして、その三大秘法を信ずるあなた方が「正しい信仰をしましょう。正しい信心をしなさい」と、人に向かって勧めていき、また自分も常に信じつつ共に進み、そのなかでいかなる大難が来ようとも、けっして崩れることなく、あらゆるものを跳ね返していくところの強い信心の姿が、そのまま当体蓮華の仏であるということを大聖人様が御指南であります。
そこからさらに、未来永劫に向かっての大きな妙法の功徳が、皆様一人ひとりの大善業のなかに顕れていくことを確信いたしましょう。
広宣流布のためにも、我々一人ひとりの身分において妙法を固く受持し、自行化他に励むところに即身成仏の大功徳がそのまま成じていくということを固く信じて、進むことが大切と思うのであります。
平成十六年一月度 広布唱題会の砌
(大日蓮 平成16年2月号 第696号 転載)
「破邪顕正」ということについては皆様も既に御承知と思いますが、まず破邪ということは邪を破すということであります。 (中 略) 世界の多くの人々は、色々な間違った宗教や思想、誤った人生観、低い人生観のなかにおける我欲、謗法等の罪障によって不幸になっております。しかるに、どのような人でもこの仏法において必ず救っていこうということが大聖人様の大きな御慈悲でありますから、それを体するときには、我々はいかなる人に対しても、縁のあるところ、よくこの正法の意義を説き、すなわち南無妙法蓮華経の功徳を説いて、しっかり信心に向かって進むべく、教えることが大切と思うのであります。 (中 略) 御承知と思いますが、法華経譬喩品における法華誹謗の罪業、邪悪を妙楽大師という方が紹介されております。これはいわゆる「十四誹謗」と言われておりまして、憍慢・懈怠・計我・浅識・著欲・不解・不信・顰蹙・疑惑・誹謗・軽善・憎善・嫉善・恨善という十四であります。 (中 略) 我々は自分自身の懈怠を打ち破り、しっかり唱題行を行っていくところに、世間の道も必ず正しく開かれ、また信心の上から本当の功徳を成就して、現当二世にわたる真の幸福を獲得していくことができると信ずるものであります。
本日ここにお集まりになった皆様には、本年度の「破邪顕正の年」の意義を深く考えられて、いよいよ御精進せられることを心からお祈り申し上げます。