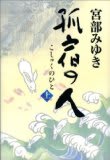いつもお世話になっている山の会から、今回お誘いいただいた山は滋賀県東近江市にある表題の山々を縦走するというコースです。
箕川と黄和田に車を置いて、8時半ごろ出発です。どこが登り口かな?と見渡していたら標識も目印もなにもない車道の脇をひょいと山の中に入るのでした。どうしたらこんな登り口を見つけることができるのですか?地図を熟知すればわかるのでしょうか?(すみません、初歩的な疑問で・・・)
なんとなくひょいと入った登山道ですが、キ、キツイ。いきなりの急登で、足の筋肉が悲鳴をあげています。
山の中なのにすごい強風のおかげで?キツイ登りにもかかわらず汗ひとつかくこともなく、キトラ・東山と到着しましたが、山の道標も、三角点もなく、GPSでこのあたりだろうと見当をつけての登頂です。

お地蔵様がお出迎え。
次の旭山でやっと三角点があり、「あっ、やった!」とひとり登頂の喜びをかみしめるのでした。
今朝は家から近いこともあり、それほど早かったわけでもないのに途中えらくお腹が空いてきました。と思っていると頃合いにフランスパンにカマンベールチーズをはさんだパンをいただいて、ちょっとお腹の虫をなだめました。おいしかった~~

旭山と手書きの看板が。
送電線の巡視路に沿ってその後目指すは岳(だけ)だけ。その前に風をよけられる場所でランチをいただきました。
除けたつもりが風は容赦なかったです。皆さん持ち寄りのたくさんのご馳走も飛んでくる枯れ葉を除けながらいただきました。春先は強い風が吹きつけますね。

気持ちの良い開けた場所。
いくつか通過する鉄塔の下は素晴らしい展望で、相変わらず山の名前はよくわかりませんが、「あれは○山、あれが前行った○山」と教えてくださるのを横でふむふむと聞いています。

鉄塔の下で展望を楽しむ。
岳もちゃんと三角点があり、昔は山頂に山の神が祀られていて、黄和田の人たちは年に一度、岳参りといって太鼓を叩きながら登られていたそうですが、今では面影もありません。

岳頂上。
下りてくると神社の鳥居があったり、大きな木にしめ縄がはってあったり、あたりは静寂につつまれていて何だか厳かな雰囲気です。少し行くと黄和田城祉の石積みが残っています。前もって勉強してくればもっと興味深く見られたのにな、と反省です。

神聖な木なんでしょうね。

山を下りたとたん、猪の仕掛けを目にして地元の人たちの獣害対策を思い、いっぺんに現実に引き戻されました。
三月半ば過ぎだと油断して、防寒対策が甘くちょっと寒い思いをしましたが、お天気は良く素晴らしい展望も望めましたし、ひとりでは絶対行くことのできない山歩きができて楽しい一日でした。
ご一緒いただいた皆さん今回もありがとうございました。
平成24年3月21日(水)
キトラ・747m / 東山・790m / 旭山・755m / 岳・781m
箕川と黄和田に車を置いて、8時半ごろ出発です。どこが登り口かな?と見渡していたら標識も目印もなにもない車道の脇をひょいと山の中に入るのでした。どうしたらこんな登り口を見つけることができるのですか?地図を熟知すればわかるのでしょうか?(すみません、初歩的な疑問で・・・)
なんとなくひょいと入った登山道ですが、キ、キツイ。いきなりの急登で、足の筋肉が悲鳴をあげています。
山の中なのにすごい強風のおかげで?キツイ登りにもかかわらず汗ひとつかくこともなく、キトラ・東山と到着しましたが、山の道標も、三角点もなく、GPSでこのあたりだろうと見当をつけての登頂です。

お地蔵様がお出迎え。
次の旭山でやっと三角点があり、「あっ、やった!」とひとり登頂の喜びをかみしめるのでした。
今朝は家から近いこともあり、それほど早かったわけでもないのに途中えらくお腹が空いてきました。と思っていると頃合いにフランスパンにカマンベールチーズをはさんだパンをいただいて、ちょっとお腹の虫をなだめました。おいしかった~~

旭山と手書きの看板が。
送電線の巡視路に沿ってその後目指すは岳(だけ)だけ。その前に風をよけられる場所でランチをいただきました。
除けたつもりが風は容赦なかったです。皆さん持ち寄りのたくさんのご馳走も飛んでくる枯れ葉を除けながらいただきました。春先は強い風が吹きつけますね。

気持ちの良い開けた場所。
いくつか通過する鉄塔の下は素晴らしい展望で、相変わらず山の名前はよくわかりませんが、「あれは○山、あれが前行った○山」と教えてくださるのを横でふむふむと聞いています。

鉄塔の下で展望を楽しむ。
岳もちゃんと三角点があり、昔は山頂に山の神が祀られていて、黄和田の人たちは年に一度、岳参りといって太鼓を叩きながら登られていたそうですが、今では面影もありません。

岳頂上。
下りてくると神社の鳥居があったり、大きな木にしめ縄がはってあったり、あたりは静寂につつまれていて何だか厳かな雰囲気です。少し行くと黄和田城祉の石積みが残っています。前もって勉強してくればもっと興味深く見られたのにな、と反省です。

神聖な木なんでしょうね。

山を下りたとたん、猪の仕掛けを目にして地元の人たちの獣害対策を思い、いっぺんに現実に引き戻されました。
三月半ば過ぎだと油断して、防寒対策が甘くちょっと寒い思いをしましたが、お天気は良く素晴らしい展望も望めましたし、ひとりでは絶対行くことのできない山歩きができて楽しい一日でした。
ご一緒いただいた皆さん今回もありがとうございました。
平成24年3月21日(水)
キトラ・747m / 東山・790m / 旭山・755m / 岳・781m