昨夜、BSで「私の青鬼」という山形発のドラマが放映されました。
私は番宣をチラ見しただけで誤解して、浜田廣介氏の「泣いた赤鬼」続編が放映されるのかと早合点して友人にLINEしまくってしまいましたが、実際は「青鬼のその後」の物語の出版をめぐる女性編集者の再生物語といった趣でした。
まあ、それはそれでいいんですけれども、女子生徒のいじめの構造やトラウマなど、ちょっと「表参道高校合唱部」のエピソードとかぶるなあ。。。などと、やや拍子抜けでした。
それにしても、青鬼の消息って、やはりみんな気になってるんですね。節分の時期になると思いだすコアな鬼の物語ながら、自分を悪者にしてまで親友の望みを叶え、その望みを永遠にするために自分は姿を隠す。そんな青鬼くんの消息。
どこでどのような人生を送ったのか、幸せだったのか、知りたい。
山のような要望がありながら浜田廣介氏が続編を書かなかったのは、「あとは読者の想像力に委ねる」ということだったようですから、作家の思惑は見事に当たったというところなのでしょう。
青鬼がその後どういう道をたどったのか。。。
私は、なんとなく、この「鬼」たちは異国の人だったんじゃないかなあと思ったりします。日本に着いて、日本の風土が好きになり、村人たちとも仲良くなりたい。でも風貌も体格も文化も、もしかしたら言葉も違ったかもしれないよそ者をなかなか受け入れられないのはちょっとわかるかな。
青鬼くんが外国の人だったとしたら、村人たちと馴染んだ赤鬼くんの幸せを祈りつつ、またこの日本で根付いていくことを祈りつつ、帰国して母国で家族を作り、自分の人生を歩んだと思いたいです。
ドラマでは、「青鬼その後」を絵本にして出版するというところで終わって、一般公募で入選した作品の内容は語られませんでした。挿絵が青鬼・赤鬼そのものから、「赤鬼・青鬼、それぞれの鬼のお面をつけた人間」に差し替えられたところがこのドラマの核心にもなっていますが、私のとは違うなあ。
読者ひとりひとりのイメージの世界を大事に。。と、いうことなのかなあと思い、それはそれで成功しているんだなと感じました。










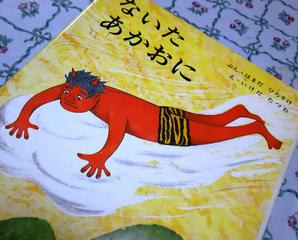

 だめだめ
だめだめ 」とのたまわった時に、「なに、いまどきそんな森進一みたいな色気だしちゃって。」と発言してドン引きされたものでした
」とのたまわった時に、「なに、いまどきそんな森進一みたいな色気だしちゃって。」と発言してドン引きされたものでした 彼女、気を使ってその時はエレキテルとは言わず、のちに私が彼女らの存在を知って「もしや。。。」と切り出したところ、「あ~知らないんだわpippiさん。。と思って口にはだしませんでした。
彼女、気を使ってその時はエレキテルとは言わず、のちに私が彼女らの存在を知って「もしや。。。」と切り出したところ、「あ~知らないんだわpippiさん。。と思って口にはだしませんでした。 」と微笑み返してくれました。
」と微笑み返してくれました。 でも、不思議な存在感のある方だなあとは思ってました。
でも、不思議な存在感のある方だなあとは思ってました。 又吉氏が敬愛するあの作家か
又吉氏が敬愛するあの作家か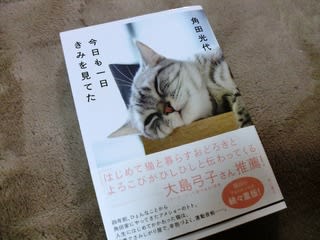

 シモベっぷり
シモベっぷり







 な・・・なんで近藤マッチの歌の後にこの曲が
な・・・なんで近藤マッチの歌の後にこの曲が と思ったら、この曲はジム・スタインマンの
と思ったら、この曲はジム・スタインマンの













 あれは、この作品がモチーフらしいです。
あれは、この作品がモチーフらしいです。




