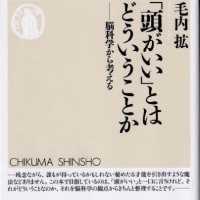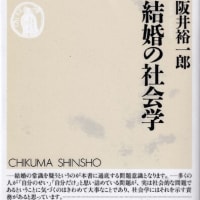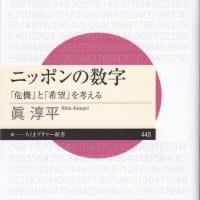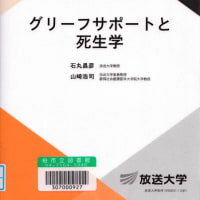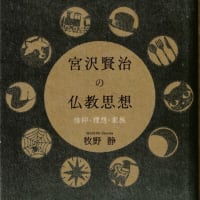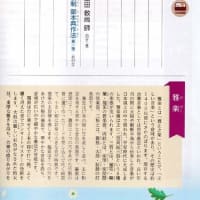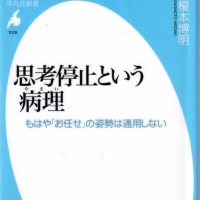『中外日報』(2024.5.8日号)掲載の記事です。
女性の「主婦化」落合教授が講演
京派の解放運動推進本部女性室は4月24日に第23回「女性会議」をしんらん交流館で開代京都産業大現代社会学部現代社会学科の落合恵美子教授が「家父長制/女性差別とは何か」の演題で講演した=写真。約40人の参加者が意見を交わした。
宗派の制度上は女性も住職になることができるが、主に長男に継承されている。「宗門現勢の報告」では2023年7月現在、住職・主管者は男性7116人に対し、女性は206人。寺院や組単位でも役職者は男性が占め、女性が経験を積む機会を得られていない。
西受秀文参務は「男性中心の宗門であることは否めない。『ジェンダー協働』との観点で意識改革が進められる背景には労働力を確保し、社会を維持する生存戦略がある。宗派はそのように女性活躍を進めるのではなく、仏教の平等の精神、御同朋御同行として出遇うことはどういうことかを考えたい」と述べた。
落合教授は講演で、女性の「主婦化」は近代の発明であると紹介した。ドイツの社会学者マリア・ミースを引用し、主婦化とは女性を経済の伜の外に置いた上で、出産や育児、家事など命の維持に関する仕事を意図的に「労働」と見なさず、資本家が負担しなければならないコストを外部化することだと解説。少子化も、女性たちの労力・命を水や空気のように無料で使える天然資源と同様に蕩尽した結果だとの見方を示した。
日本における女性差別は、中東やインドなど「父系制的家父長制」の地域で起こる女性に対する暴力や苛烈な人権侵害とは異なるとも指摘した。(以上)
女性の「主婦化」落合教授が講演
京派の解放運動推進本部女性室は4月24日に第23回「女性会議」をしんらん交流館で開代京都産業大現代社会学部現代社会学科の落合恵美子教授が「家父長制/女性差別とは何か」の演題で講演した=写真。約40人の参加者が意見を交わした。
宗派の制度上は女性も住職になることができるが、主に長男に継承されている。「宗門現勢の報告」では2023年7月現在、住職・主管者は男性7116人に対し、女性は206人。寺院や組単位でも役職者は男性が占め、女性が経験を積む機会を得られていない。
西受秀文参務は「男性中心の宗門であることは否めない。『ジェンダー協働』との観点で意識改革が進められる背景には労働力を確保し、社会を維持する生存戦略がある。宗派はそのように女性活躍を進めるのではなく、仏教の平等の精神、御同朋御同行として出遇うことはどういうことかを考えたい」と述べた。
落合教授は講演で、女性の「主婦化」は近代の発明であると紹介した。ドイツの社会学者マリア・ミースを引用し、主婦化とは女性を経済の伜の外に置いた上で、出産や育児、家事など命の維持に関する仕事を意図的に「労働」と見なさず、資本家が負担しなければならないコストを外部化することだと解説。少子化も、女性たちの労力・命を水や空気のように無料で使える天然資源と同様に蕩尽した結果だとの見方を示した。
日本における女性差別は、中東やインドなど「父系制的家父長制」の地域で起こる女性に対する暴力や苛烈な人権侵害とは異なるとも指摘した。(以上)