昨朝(24.2.26)、NHKラジオ「文学のしずく」(小説の朗読)は、夏目漱石「吾輩は猫である」でした。“吾輩は猫である”の冒頭部分だけで、読んだことはないので興味がありました。そして最後の「吾輩は死ぬ。死んでこの太平を得る。太平は死ななければ得られぬ。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。ありがたいありがたい。」に浄土真宗的な味わいを感じました。
ネットでみると、夏目家の所属寺は、真宗大谷派の末寺本法寺で、明治14年1月に母、20年3月に長兄、6月に次兄が本法寺に葬られた。それ以来、漱石はしばしば小日向を訪れているとあります。蓮如の「御ふみ」の言葉を友人子規に書き送ったり、作家となってからは「坊ちゃん」の清の墓をここに設けるなど縁が深かったようです。また境内には、漱石の句碑もあるという。
漱石は幼い時なら、南無阿弥陀仏を耳にしていたのでしょう。
「吾輩は猫である」の最後の部分は、主人公の猫が水に落ちて死んでいく描写で終えています。その部分を紹介してみましょう。
その時苦しいながら、こう考えた。こんな呵責(かしゃく)に逢うのはつまり甕から上へあがりたいばかりの願である。あがりたいのは山々であるが上がれないのは知れ切っている。吾輩の足は三寸に足らぬ。よし水の面(おもて)にからだが浮いて、浮いた所から思う存分前足をのばしたって五寸にあまる甕の縁に爪のかかりようがない。甕のふちに爪のかかりようがなければいくらも掻(が)いても、あせっても、百年の間身を粉(こ)にしても出られっこない。出られないと分り切っているものを出ようとするのは無理だ。無理を通そうとするから苦しいのだ。つまらない。自(みすか)ら求めて苦しんで、自ら好んで拷問(ごうもん)に罹(かか)っているのは馬鹿気ている。
「もうよそう。勝手にするがいい。がりがりはこれぎりご免蒙(めんこうむ)るよ」と、前足も、後足も、頭も尾も自然の力に任せて抵抗しない事にした。
次第に楽になってくる。苦しいのだかありがたいのだか見当がつかない。水の中にいるのだか、座敷の上にいるのだか、判然しない。どこにどうしていても差支(さしつか)えはない。ただ楽である。否(いな)楽そのものすらも感じ得ない。日月(にちげつ)を切り落し、天地を粉虀(ふんせい)して不可思議の太平に入る。吾輩は死ぬ。死んでこの太平を得る。太平は死ななければ得られぬ。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。ありがたいありがたい。(以上)
自らの願いに縛れて自分を苦しめている。その願うという縛りから解放されたとき平安がおとずれる。この構図は仏教的でもあり、逆に一歩間違えば、主観的な心を抹殺して、社会や権力者に従属させるといった考え方だとも言えます。
核心は「無能なる自己をどう受け入れるか」と言うことかもしれません。最後は「南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。ありがたいありがたい。」で終わっているので、無能なる自己を洞察せしめ、無能なる自己のままで平安に至らしめたものこそ、最後の南無阿弥陀仏であったとなれば浄土真宗の念仏者の相と重なります。
さて皆さんは、どう受け止められますか。
ネットでみると、夏目家の所属寺は、真宗大谷派の末寺本法寺で、明治14年1月に母、20年3月に長兄、6月に次兄が本法寺に葬られた。それ以来、漱石はしばしば小日向を訪れているとあります。蓮如の「御ふみ」の言葉を友人子規に書き送ったり、作家となってからは「坊ちゃん」の清の墓をここに設けるなど縁が深かったようです。また境内には、漱石の句碑もあるという。
漱石は幼い時なら、南無阿弥陀仏を耳にしていたのでしょう。
「吾輩は猫である」の最後の部分は、主人公の猫が水に落ちて死んでいく描写で終えています。その部分を紹介してみましょう。
その時苦しいながら、こう考えた。こんな呵責(かしゃく)に逢うのはつまり甕から上へあがりたいばかりの願である。あがりたいのは山々であるが上がれないのは知れ切っている。吾輩の足は三寸に足らぬ。よし水の面(おもて)にからだが浮いて、浮いた所から思う存分前足をのばしたって五寸にあまる甕の縁に爪のかかりようがない。甕のふちに爪のかかりようがなければいくらも掻(が)いても、あせっても、百年の間身を粉(こ)にしても出られっこない。出られないと分り切っているものを出ようとするのは無理だ。無理を通そうとするから苦しいのだ。つまらない。自(みすか)ら求めて苦しんで、自ら好んで拷問(ごうもん)に罹(かか)っているのは馬鹿気ている。
「もうよそう。勝手にするがいい。がりがりはこれぎりご免蒙(めんこうむ)るよ」と、前足も、後足も、頭も尾も自然の力に任せて抵抗しない事にした。
次第に楽になってくる。苦しいのだかありがたいのだか見当がつかない。水の中にいるのだか、座敷の上にいるのだか、判然しない。どこにどうしていても差支(さしつか)えはない。ただ楽である。否(いな)楽そのものすらも感じ得ない。日月(にちげつ)を切り落し、天地を粉虀(ふんせい)して不可思議の太平に入る。吾輩は死ぬ。死んでこの太平を得る。太平は死ななければ得られぬ。南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。ありがたいありがたい。(以上)
自らの願いに縛れて自分を苦しめている。その願うという縛りから解放されたとき平安がおとずれる。この構図は仏教的でもあり、逆に一歩間違えば、主観的な心を抹殺して、社会や権力者に従属させるといった考え方だとも言えます。
核心は「無能なる自己をどう受け入れるか」と言うことかもしれません。最後は「南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏。ありがたいありがたい。」で終わっているので、無能なる自己を洞察せしめ、無能なる自己のままで平安に至らしめたものこそ、最後の南無阿弥陀仏であったとなれば浄土真宗の念仏者の相と重なります。
さて皆さんは、どう受け止められますか。












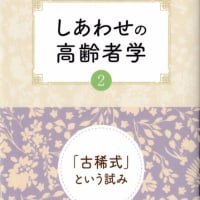


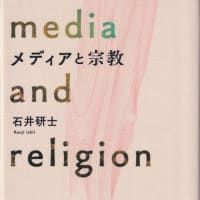

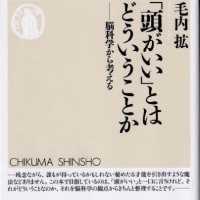
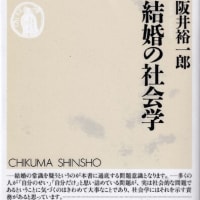
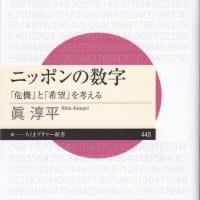








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます