明治維新後5人の天皇がいる。
明治天皇、
大正天皇、
昭和天皇、
平成天皇、
令和天皇。
5人の天皇誕生日のうち、
明治天皇と昭和天皇は、日本の四季のなかで、いちばんいい季節に生まれたから、
今も祝日として残っている。←これは個人見解。
特に平成天皇の祝日には少し困った。
12月23日はXマス、月末、年末、年度末で忙しかった。はっきり言って業務に支障・負担があった。
大正天皇のように、祝日を移動してほしい気持ちがあった。
なお、次期の天皇誕生日は5月1日、
その次の天皇誕生日は9月6日。
そのまた次の天皇誕生日は現時点では空白。(男性や、男系とか言っていると)永遠に埋まらないかもしれない。
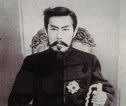
(アラカン)
・・・・・
「太平洋戦争下の学校生活」 岡野薫子 平凡社 2000年発行
※著者は昭和4年(1929)生まれ。
天長節
小学校に入学して初めての式は、4月29日の天長節であった。
この日、校門には、大きな日の丸国旗が交叉して立てられた。
その下をくぐる時、幼い私はいつもと違って晴れがましい気分になった。
友達の顔も、いつもと違って見えた。
「天長節」
〽
今日のよき日は 大君の
うまれたまひし よき日なり
式の当日、校庭の一角に建てられた奉安殿の扉がひらかれる。
奉安殿というのは、天皇、皇后両陛下の写真と教育勅語がしまってある小さな蔵で、
建物自体、神社のつくりになっている。
その周囲は柵で囲み、玉砂利を敷き詰め、神聖な区域とされていた。
私が通学していた小学校の場合、奉安殿の位置が校門からかなり離れたところにあったので、登校下校時に最敬礼をするには無理があって、
普通は省略されていた。
その奉安殿から式場まで、勅語を運んでくるのは、教頭先生の役目だった。
教頭先生は、紫のふくさに覆われた教育勅語の箱を黒い漆塗りの盆にのせ、それを頭上高くかかげながら、
しずしずと運動場を横切って講堂まで歩いてくる。
やがて「最敬礼!」
号令がかかって、私たちは頭を深く下げる。
静かに「直れ」の号令がかかり、やっと頭をあげる。
フロックコートの礼装で絹の白手袋をはめた校長先生は、おもむろに紫のふくさをひろげ、
箱から教育勅語をとりだすと、巻物の紐をといてひろげ、押しいただく。
この時、私たちはまた、頭を下げる。
勅語を読み終わるまで、そのままの姿勢でいなくてはならない。
やがて、
「朕惟フニ、・・・・」
と、重々しい奉読の声が聞こえてくる。--というよりは、頭の上におりてくる。
何しろ、神主が祝詞をあげるときのような荘重な節回しで読まれるので、
子どもにとっては、耐え難く長い時間に思われた。
やっと終わって、元の姿勢に戻る時、あちこちから鼻水をすすりあげる音がおこる。
まわりはほっとした空気につつまれる。
新校長は、緊張のあまり手がふるえ、声がうわずる。
明治天皇のお言葉を代読することになるわけで、緊張するのも無理はなかった。
やがて、意味はわからぬまま、部分部分を暗記するようになった。
明治天皇、
大正天皇、
昭和天皇、
平成天皇、
令和天皇。
5人の天皇誕生日のうち、
明治天皇と昭和天皇は、日本の四季のなかで、いちばんいい季節に生まれたから、
今も祝日として残っている。←これは個人見解。
特に平成天皇の祝日には少し困った。
12月23日はXマス、月末、年末、年度末で忙しかった。はっきり言って業務に支障・負担があった。
大正天皇のように、祝日を移動してほしい気持ちがあった。
なお、次期の天皇誕生日は5月1日、
その次の天皇誕生日は9月6日。
そのまた次の天皇誕生日は現時点では空白。(男性や、男系とか言っていると)永遠に埋まらないかもしれない。
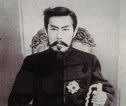
(アラカン)
・・・・・
「太平洋戦争下の学校生活」 岡野薫子 平凡社 2000年発行
※著者は昭和4年(1929)生まれ。
天長節
小学校に入学して初めての式は、4月29日の天長節であった。
この日、校門には、大きな日の丸国旗が交叉して立てられた。
その下をくぐる時、幼い私はいつもと違って晴れがましい気分になった。
友達の顔も、いつもと違って見えた。
「天長節」
〽
今日のよき日は 大君の
うまれたまひし よき日なり
式の当日、校庭の一角に建てられた奉安殿の扉がひらかれる。
奉安殿というのは、天皇、皇后両陛下の写真と教育勅語がしまってある小さな蔵で、
建物自体、神社のつくりになっている。
その周囲は柵で囲み、玉砂利を敷き詰め、神聖な区域とされていた。
私が通学していた小学校の場合、奉安殿の位置が校門からかなり離れたところにあったので、登校下校時に最敬礼をするには無理があって、
普通は省略されていた。
その奉安殿から式場まで、勅語を運んでくるのは、教頭先生の役目だった。
教頭先生は、紫のふくさに覆われた教育勅語の箱を黒い漆塗りの盆にのせ、それを頭上高くかかげながら、
しずしずと運動場を横切って講堂まで歩いてくる。
やがて「最敬礼!」
号令がかかって、私たちは頭を深く下げる。
静かに「直れ」の号令がかかり、やっと頭をあげる。
フロックコートの礼装で絹の白手袋をはめた校長先生は、おもむろに紫のふくさをひろげ、
箱から教育勅語をとりだすと、巻物の紐をといてひろげ、押しいただく。
この時、私たちはまた、頭を下げる。
勅語を読み終わるまで、そのままの姿勢でいなくてはならない。
やがて、
「朕惟フニ、・・・・」
と、重々しい奉読の声が聞こえてくる。--というよりは、頭の上におりてくる。
何しろ、神主が祝詞をあげるときのような荘重な節回しで読まれるので、
子どもにとっては、耐え難く長い時間に思われた。
やっと終わって、元の姿勢に戻る時、あちこちから鼻水をすすりあげる音がおこる。
まわりはほっとした空気につつまれる。
新校長は、緊張のあまり手がふるえ、声がうわずる。
明治天皇のお言葉を代読することになるわけで、緊張するのも無理はなかった。
やがて、意味はわからぬまま、部分部分を暗記するようになった。

















