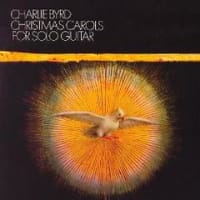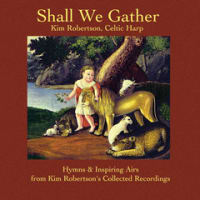ケーブルテレビの映画チャンネルで、「真夏の夜のジャズ」を見る。1959年、ニューポート・ジャズフェスティバルの記録映画。当時の第一線のジャズ・ミュージシャン総登場である。
この映画、もう何度も見る機会があったが、どれも飛び飛びに断片的な見方をしていて、おそらくはじめから最後までまともに見るのはこれがはじめてだ。
相当にお洒落な代物として製作されているのであろう事は、最初に見たときから気がついてはいた。
会場でアイスクリームを食べる女、演奏にかぶって読み上げられる気象情報や、会場で同時に行われていたヨット大会の映像、ブランコで遊ぶ子供。そして道端に転がっている空き瓶一つまで、いちいちお洒落な映像である。演奏中のミュージシャンは言わずもなが。下からあおる形の照明によって闇の多いステージに浮かび上がる彼らは、クリアに捉えられていながら、どこか強い幻想味を帯びている。
さらに、演奏に聞き入る観客の一人一人の表情までがすべて絵になっていて、これは見事なものだなあ、などと思っていたのだが、今回、じっくり見直してみると、かなり演出臭い雰囲気がある。少なくとも会場風景には、かなりの部分、”ヤラセ”の映像があるのではあるまいか。
ミュージシャンの演奏場面にしても、音と楽器の指使いが露骨に合っていない部分があったりする。演奏の”見せ所”の映像に、別の瞬間に演奏されたそのミュージシャンの”聞かせどころ”の音を強引に重ね合わせた部分もあるようだ。いわゆるジャズ・フェスティバルのドキュメンタリーというよりは、今日のプロモーションビデオの作りに、むしろ共通するものを感じる。
司会者が「ジェリー・マリガン・クインテットでした」と言っているのに、字幕には「カルテットでした」と出てしまうのはご愛嬌。それにしてもジェリー・マリガン、若い!(今、この映画を見れば、どのミュージシャンにだって”若い!”と驚かされるのだが)
ボーカルものの登場比率が、今のジャズライブものよりかなり高い。アニタ・オディ、ビッグ・メイバル、マヘリア・ジャクソンなどなど。ボーカルものの好まれていた時代だったのだろうか。この辺り、ファンにとってジャズは今とは若干、異なった存在だったのかとも想像される。
この映画に特徴的な下からの照明に、暗闇のステージ上に浮かび上がった若きチャック・ベリーの顔は、怪談を語る際の稲川淳二に良く似ている。普段はスイングでもやっているのであろう地元のバンドをバックにロックンロール。ギターの音一つ一つが実に禍々しく、血を騒がせる。
この映画を最初に見た際、非常に印象に残った、”フルートを吹くエリック・ドルフィ”の場面は、脳内で伝説化(?)されていたせいだろうか、実にあっけなく終ってしまう。ドルフィの属するチコ・ハミルトン・クインテットのサウンドがそもそもエキゾティックな志向でもあり、演奏も映像も、ある種隠微な美意識に貫かれ、私にとって、この映画最大のハイライトであるのに変りはないのだが。
司会者の求めに応じ、ヨーロッパ演奏旅行時の面白エピソードを”いかにも”な白人好みの道化者の黒人を演じつつ語り、会場の笑いを誘うルイ・アームストロング。もはや、そのような愛され方の定着した彼だったのだろう。
ここで演奏されるジャズは、自らが時代の先端にあり、”生きた音”である事を当たり前の顔で主張している。映画のすべてから、演奏会場が夏のバカンス地であるのも大いに作用していようが、”いつかの、楽しかった夏の記憶”の色を強く感じる。かって、このように生々しく社会に横行し、人々に愛されたジャズなる音楽があり、これはそんな過ぎ去った夏のある休日の記念写真・・・