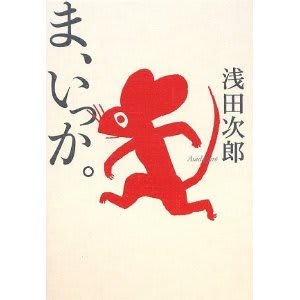
浅田次郎さんの本は読んだことがない。エッセイから入ることにした。エッセイをとおしてこの作家の人となりを、少しは理解できたように思う。
東京出身。祖父母は江戸の武家の伝統をもち、その祖母からの影響を強くうけて育ったようだ。幼少の頃から歌舞伎に毎月、連れっていってくれた、とある。また、外出のときにはきちんと「よそゆき」に着物を着換えるよう躾けられた。現在でも、その習慣は身についているとのこと。
父母はあるときから、突然いなくなり家庭崩壊。陸上自衛隊に入隊。その後、隊から足を洗い、アパレル関係の会社で仕事をするようになる。服装のことに詳しい。経験から、ネクタイの選び方、プレゼントの仕方、福袋の買い方のアドバイスをつづった文章がいくつかある。
ヨーロッパはパリを起点に活躍、アメリカのラスベガスにはときおり「満を持して」ショッピングに出かけているようだ。
当然だが、読書が好きで、これをとってしまったら生きる価値がないとまで言い切っている(毎日一冊、読破)。
夜は10時頃には寝て、早起きが習慣化していること、早寝早起きは幼いころから祖母からそうさせられ、年がいってからも自衛隊でそのように過ごしたことでそうなったと打ち明けている。老化を防ぐにはこれが一番なようである。
酒はやらない。若いころから花を愛でていたこと(失敗談も)、競馬に明るいこともチラリと垣間見える。仕事がら夏休みをとりにくい、名前が売れるにつれますます忙しくなっている、時間がたつのが早いなど、率直に本音を語っている。
とにかく、浅田次郎さんのいろいろなことが、本人の文章からわかった。
「MAQUIA]という雑誌に連載された「男の視線」というエッセイを中心に編集された本。標題の『ま、いっか。』は本書の最初のエッセイで、結婚相手には「絶対この人」ではなく、「ま、いっか。」という考え方もあり、という提言から。

大学で「社会思想史」の科目の担当教員である著者が、自身の研究生活のなかで、専門分野での直接の成果ではないが、その周辺で書き連ね、考えてきた断章。
というわけで、先学、指導教授の研究業績や人柄について書いたもの、勤務先の大学で発行している小冊子に投稿したもの、書評、辞典の項目、日記風の読み物などが混然一体となって納められている。
この中で、住谷一彦氏の研究業績をまとめた文章、同僚の高橋和男氏のそれをまとめたものが異彩をはなっている。よく書けていて、住谷氏、高橋氏の著作は読んだことがないが、何をどのように研究し、当該の研究分野で開拓者的な仕事をしたのかがわかる。
ウェーバー、大塚久雄への関心の持続は、この分野での研究者であれば当然なのであろうが、関心の持ち方が具体的に書かれているので勉強になる。
読み物としては「遊びとスポーツ」が面白かった。このようなことにも著者が関心をもち、書いていたとは知らなかった。スポーツ観戦は好きなようで、この文章以外にも、はしばしに、それがうかがえる。また読書家でもある。
そして「たばこ好き」。それが本のタイトルになった。

劇作家井上ひさしさんの前の奥さんの回顧録です。
ふたりの馴れ初め(腕時計詐欺事件)、結婚、放送作家としての出発(ひょっこりひょうたん島)、コント書きの下積み生活、劇作家としての再スタート(テアトル・エコー)、直木賞受賞、売れ子作家の私生活、こまつ座の旗揚げ、離婚、そしてひさしさんの死。
「かつて二人は濃縮された時間を共に過ごした。二人はまだ若く、貪欲で、陽気だった。「井上ひさし」を世の中に認めてもらうために二人ひとつになって生きていた。たくさんの人達と出会い、出会うたびに力を借りた。子供も三人生まれた。大きな家も建てた。断るのに苦労するほど仕事も貰えるようになった。そして、別れた。」(長女、都さんの「あとがきにかえて」より。p.379)。
妻でなければ知りえない裏話が豊富。ひさしさんの凄まじい鬼気迫る読書と資料の読み込み、あふれる才能、「遅筆堂」の実情、子育てや親戚づきあいの実態、人間関係、家庭のなかでの横暴ぶり、価値観、世界観、人生観がわかる。生い立ちがまた特殊。若干、本人が語ってはいたが、「そうだったのか」という記述がたくさんありました。
「日本人のへそ」「頭痛肩凝り樋口一葉」「小林一茶」「藪原検校」「泣き虫なまいき石川琢木」などが書かれた背景にも興味が惹かれたました。
テレビがはしりだった頃のNHK界隈での物書きの生活、小沢昭一さんたちとの劇団(「芸能座」)のたちあげ、「憲法九条の意見広告」の顛末、義母で逢った井上マスという人物の評価。
著者が座長として「こまつ座」を率いるようになってからは、夫婦の対立、亀裂が続き、破綻しました。最後は壮絶そのものです。とてもその内容をここには書けません。夫婦の破綻は、親子関係にまで影響を及ぼし、「座」のなかの軋轢に波及しました。このあたりの記述には後味の悪さがあります。
表題に「協奏曲」とありますが、「狂奏曲」に近いです。

イタリア語通訳(同時通訳)30年の経歴をもつ著者(自称シモネッタ)による、シモネタ体験記です。
「アモーレ」の国イタリアの下世話な話が満載です。しかし、不愉快な思いはしません。下品でもありません。これらの話を読むと、イタリア人気質、イタリア文化の一端が透けてみえてきます。
表題の「デカメロン」というのはもともとはボッカチオの作品で、これは14世紀のフィレンツェでベストが大流行したときに、郊外の舘に逃れた男女10人が暇つぶしに毎日一人一話、都合十話の話をして10日間を過ごした物語で、それにあやかっています。
本書の読み方はいろいろありうるが、一番最後の章「シモネッタのイタリア初夜」では著者がイタリア語を学ぶきっかけ、その後イタリア語の翻訳、通訳を始めたころのエピソードが自己紹介のように書かれているので、ここからスタートするのもひとつの方法です。
その他の各章には、「くどき上手なイタリア男たち」「カサノヴァの末裔たち」「ああ夫婦」「世界最古の職業、東西のプロたち」「ああ日本人」「ホテルにて」「かくもユニークな人たち」「イタリア人のビジネス」のタイトルがついています。
「解説にかえて」では、ロシア語同時通訳者で作家だった米原万里さんとの対談。その後の「文庫版あとがき」には癌と闘った万里さんへのお別れの言葉で、涙をさそいます。

奈良に生れた著者は農民文学者・犬田卯と結婚。
昭和10年より夫の実家である牛久沼畔に疎開,定住。以来,ここが人生の拠点となる。時とともに近代化,開発で変わっていくこの地で,著者が日々考え,問い続けたことは何か。
平易な文章で人を唸らしめます。
自然にあっては土,水,火を大切にし,食にあっては米を敬い,社会にあっては人間の平等を重んじる。嘘は絶対に許さない。それが彼女の信念。
1944年,青森の騎兵連隊にいる息子に送った5足の手編み靴下を連隊長に没収され,理性的で穏やかな彼女が連隊長に怒りの手紙を出した話,憲法を抱いて棺に入った蜷川虎三の話,「一代(ひとしろ)」というのが土地の大きさを測る単位(稲一束)であるという話,物価の高騰を測る彼女の物指しが米の値段であるという話,草むしりを罰にしている農業高校をやめた農家の高校生の話。生活の知恵,生きる哲学がぎっしり詰まった玉手箱のような本です。

著者は夏目漱石の孫で,「歴史探偵家」の半藤一利氏の妻です。
裏表紙の織り込みに写真がありますが,エッセイの内容と同じで天心爛漫そのものです。
文章はやわらかく,読みやすいです。主として身辺のことを書いたものが入っています。
価値のあるのは夏目家,漱石の周辺の出来事を書いた第1章「漱石夫人は占い好き」。
ただし,章の建て方がいまひとつ不明瞭で,各章に配される標題のひとつが章のタイトルになっているのはわかりますが,それぞれがどういう纏まりで章に括られているのかのコンセプトが分りません。
「猫」の話しが多いのは,漱石先生を意識してでしょうか?

著者は『清貧の思想』で知られる作家です。自由人としての老後の愉しみを説いています。粋人,教養人です。
囲碁,落語,骨董,書道。守備範囲は広い。傘(スウェイン・アドニーブリック社),帽子(ツイードのクロスハット),下駄(会津の柾目),カメラ(ライカ),万年筆,水滴(李朝分院窯),硯(緑縁の八稜硯)。質のよいもの,人間に馴染むものへの偏愛には感服します。わたしには新鮮であり,羨ましくもあり,しかし絶対に到達しえない世界と認識しました。
もっとも,著者はあくせずせず,自由闊達に生きる姿勢が,人生の秋である老年に実りをもたらすということを主張しているのですから,その境地に入ることが重要なのだと,溜飲をさげました。

ロシア(ソ連)旅行記です。1969年(昭和44年)6月10日から一カ月弱。最後はスウェーデン(ストックホルム)、デンマーク(コペンハーゲン)まで行っています。
F社企画の「69年白夜祭とシルクロードの旅」に添乗員を含め総勢10名。著者の夫は作家の武田泰淳ですが、その夫が妻の著者に「つれて行くから日記を書け」と言い、その言を忠実に守ってできあがったのがこの紀行文です。それが1978年(昭和53年)2月から12月まで、雑誌『海』に掲載され、その後、本書となりました。
ロシア旅行の行程は、横浜を出港して、ナホトカ、ハバロフスク、イルクーツク。ノボシビリスク、アルマ・アタを経由して、タシケント、サマルカンド、ブハラ、ヤルタ、レニングラード、モスクワまでです。そこからヨーロッパに飛んでいるのです。
実はわたしはこの年(1969年)の8月、バイカル湖でのキャンプに参加しました。武田さんのソ連旅行の2カ月後です。また、1984年には、ソ連経済視察団の一員として、タシケント、サマルカンド方面から、リトアニア、モスクワを回りました。さらに、2007年、ソ連崩壊後、ペトログラード(旧レニングラード)、モスクワに観光旅行しました。
ということがあり、武田さんのこの旅行記で追体験したり、共感することが多かったのです。とくに1969年の横浜からハバロフスク号に乗って、津軽海峡を通り、ナホトカへ、さらに、ハバロフスク、イルクーツクに向かうコースでの記述は、懐かしく記憶がよみがえりました。
ハバロフスク号船上での食事、生活には思い当たるところが多いです。タシケントに飛行機で到着する前に、「バルハシ湖」が見え(カザフスタン東部)、機内がざわめくシーンがありますが(p.68)、全くこの通りでした。バルハシ湖がみえたというだけで、機内がざわついていました。「バルハシ湖」はそれだけ魅力ある、綺麗な湖でした。
著者がたどったコースのうちシルクロード以降のコースで、わたしはブハラ、ヤルタには行きませんでしたが、オデッサ、キエフなどを訪れました。このあたりは少し違います。また武田さんたちは事情があってアルマ・アタはパスしたようですが、わたしはここに降り立ちました。
著者は、レニグラードからモスクワへは飛行機を使っていますが、わたしは寝台列車でした。一番よく記憶に残っているのは、やはりモスクワなので、ここでの著者の記述は、その団の一員になった感じで読めました。
ともあれ、この本に描かれている1969年のソ連の様子は、観光客の眼ですが、そのままのソ連人の生活です。食事の内容、絵葉書とバッチの購入、ウォッカ、クワスなどのアルコールの飲み、全くそのままです。
本書はある意味でまとまりがありません。もっと整理してわかりやすく書けないのか、と最初は思いました。しかし、このように、メモ風に思いついたこと、眼にとびこんだことをそのまま未整理のまま示すものも臨場感があっていいですね。
なお、同行者の竹内さんというのは、中国文学者の竹内好氏です。また銭高老人という人がいて、いい味をだしています。面白い、愉しい旅行団だったようです。

先日読了した「ふり返るなドクター-研修医純情物語-」は小説でしたが、この本はエッセイ風の読み物です。
自らの研修医としての一年間の体験、そこで感じたことを率直に語っています。言いたいことはひとつで、それはいまの医療が「患者のための医療」になっているのかということ、です。
有体に言えば、少なくとも著者が飛び込んだ大学病院の医療はそうなっていなかったのです。最初は「何かおかしい」「何か変」という感覚だったのですが、日がたつにつれて病院の医師たちが「患者のための医療」という視点をどこかに置き去りにしているということに気づくようになったようです。
多くの医師が患者の立場にたって考えていない、患者の身になって行動していない、彼らにとって大切なことは「自分は医師だ」というプライド守ることにきゅうきゅうとし、自己満足にひたっている、ナンセンスな教授回診、モーニング・カンファレンス、過酷過ぎる労働条件、アルバイトにあけくれる医師。
著者はこうした現状に嫌気がさし、患者とコミュニケーションをはかることに努力し、患者との話し合いに多くの時間をさきました。こうしたこと観点から感じられたこと、体験したことを、たくさんのエピソードを交え、ユーモアたっぷっりにつづられています。
著者は父が医者でしたが、存命中は医療に関心がもてず、父親にも反感をもち、距離をおいていました。その父がホテルの火災でなくなる直前に著者を食事に誘い、そのときに初めて父親の人間的な素顔に触れたのです。
医学と関わりのない学部を出て、いろいろな職を転々とし、悩み、苦労して漸く自分の進む道を探りあて、その帰結が医者としての患者のために尽くすということでした。

著者は作家北杜夫(斎藤宗吉)の娘で歌人斎藤茂吉の孫、茂吉の妻は輝子です。著者にとっては祖母にあたります。その輝子の生涯、生き方を孫娘の眼でエッセイ風にまとめのがこの本です。
輝子は浅草にあった精神科の病院の医師、斎藤紀一の娘でした。茂吉は14歳の頃に山形県南村山郡金瓶村(現在の上山市金瓶)からでてきてこの親戚の医師のところに転がりこみ、養子となりました。
茂吉と輝子は幼馴染みでしたが、茂吉31歳、輝子18歳のときに結婚。二人の仲は決してよいとはいえず、生涯で18年間、別居生活がありました。もともと輝子は活発な少女でしたが、茂吉死後、猛女ぶりを発揮します。
海外旅行です。89歳で亡くなるまでに海外渡航数97回、世界108カ国を訪れました。その中には79歳で南極、80歳でエヴェレスト山麓、81歳でエジプト、83歳でアラビアなどが入っています。
著者はその海外力熱に浮かされた輝子の猛女ぶりとそれに振り回された叔父、茂太夫妻、父宗吉とその妻の様子を面白可笑しく書き綴っています。
父である北杜夫さんのことも、すでに本人が公にしていることばかりですが、躁鬱病の顛末を中心に描写しています。一番悔やんでいるのは、著者が小学校1年生から大学4年までにつけていた日記を、就職が決まったときに、「燃えるゴミ」にだし、この世からなくなってしまったこです。
ただ、輝子死後、輝子から著者に海外から宛てたかなりの枚数の絵葉書がでてきたようで、そのことをエピローグで紹介しています。また、著者は成城大学出身ですが、卒業論文に歌人としての斎藤茂吉をとりあげたとか。しかし、その内容は構成だけが示され、どんなものになったのかは書かれていません。たいした論文にはならなかったと推測できます(何となく、そのような匂いがする著者の書きっぷりからわかるのです)。
先日(10月24日)、北杜夫さんが、84歳で亡くなりました。わたしが高校生の頃、大江健三郎さん、幸田文さんとともに、好きな作家でしたので、思うところがたくさんあります。この3人には、高校時代にファンレターを書いたことがあります。北杜夫さんからは返事がきました。印刷された読者ファンへの返信用(私用)のハガキで、簡単な挨拶が書かれていました。
北杜夫さんの小説,エッセイは高校生の頃,よく読みました。この作家の名前を眼にすると自分の青春時代を思い出します。
最初の北杜夫体験は「怪盗ジパゴ」だったと記憶しています。ゲラゲラ笑いながら読みました。そのうちこの作家が真面目な小説を書いていることを知り、『楡家の人々』『夜と霧の隅で』などを読破。前者は大河小説で、いまでも北作品では一番好きです。後者は芥川賞受賞作です。その後もマンボウシリーズをかなり読みました。このシリーズのなかでは『昆虫記』と『青春記』に惹かれています。わたし自身が子どもだったころ、昆虫採集で遊びまわり共感できたこと、『青春記』はわたし自身の青春へのノスタルジアをしばしば醸し出したからです。

さて、今日紹介する『マンボウ恐妻記』ですが、わたしは北さんの著作に『マンボウ愛妻記』というのがあるのを偶然に知り、この作家は奥さんに関することで2冊もエッセイを書いているのかと思い、後者を読み始めたのですが、何回も読んだことのある文章がでてくるので、調べると最初に『愛妻記』として出版され、その後に改題で『恐妻記』になったようで、中身は全く同じということが判明しました。わたしの読書ノートによると、2005年に「恐妻記」を読んでいました。
という事情がわかりましたが、本書は著者の40年余の夫婦生活の実態を得意のユーモアで包んで書かれた物です。
そんなことまで書いていいの,奥さんはこんなふうに書かれて大丈夫なの,と思わせる記述がテンコ盛りです。「可憐な少女から猛女となった」喜美子夫人,他人事ながら躁鬱病の著者とよく連れ添ってきたなと同情します。
ユーモアを通り越した過激な表現が多いですが,これも著者の魂胆でしょうか…。そのことを抜きにしても「歳をとるほど女は強くなる」「女性は体の仕組みも頑丈にできているが生存本能も子孫を残す本能も断然強い」と慨嘆する著者の思いは,普遍性をもった真理です。
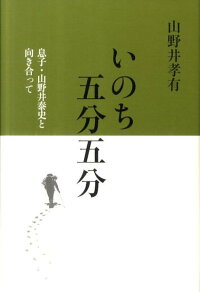
著者は世界的登山家である山野井泰史さんの父親です。
本書で山野井孝有さんは、息子である山野井泰史さんとその妻妙子さんの人生との関わりを語っています。登山家を息子にもつことの不安、苦しみ、そして生きがいが率直に書かれています。
表題の「いのち五分五分」は、自身が高齢になってきてこの世を去ることと息子さんが登山で亡くなること、どちらが先に亡くなるかの確率が五分五分でるということでつけたそうです。本書の前に「五分五分」という自費出版の本があるようです。
泰史さんは、登攀で何度も死にそうになっています。とくに2002年10月の極限のギャチュンカン登攀では悪天候のため泰史、妙子夫妻は行方不明になり、生還はほぼ絶望の状況だったとか。死力を尽くして二人は「奇跡の生還」をしました。このあたりの事情は「第6章:ギャチュンカンからの生還」に詳しいです。
しかし、夫妻は足と手の指が凍傷となり、帰還後の治療のすえ泰史さんは右足の全指を切除することになり、妙子さんは両手の指のすべてを第二関節まで失うことになりまし(「第7章:凍傷治療から再起へ」)。
泰史さんはその後も山を諦めず、2005年に7月にはポタラ峰北壁に単独登頂に成功しました。
泰史さんが登山家になったのは、著者の妻の叔父が小学生だった泰史さんをよく山に連れていったからとのことです(南アルプスの北岳など)。中高校生のときは山に夢中で、それ以外のことには全く関心がなかったようです。
高校就学時よりアルパイン・クライミングに傾倒します。卒業後はアメリカ合衆国のヨセミテなどでフリークライミングに没頭しました。
父親の孝有さんは泰史さんに登山家になってもらっては困ると思い、彼を説得し、大喧嘩になりましたが、泰史さんの強い意志に山登りになることをやめさせることを断念しました(奥さん[本書のなかでは「かみさん」と書かれている]は意外と早く泰史さんが自分の望むとおりに生きることに同意していたようです)。
以後、泰史さんは全て自力で計画をたて、登攀を成し遂げていきます(もっとも泰史さんは何度も大怪我をして両親を心配させています)。
著者は父親の眼でその成長に目を細めつつ、しかしいつ事故に遭うかもしれないギリギリの人生につきあうことになります。
植村直己冒険賞受賞の経緯、伴侶である妙子さんのこと(泰史さんより9歳年上、既に結婚前にブロードピーク[8047メートル、1991年]、マカルー[8463メートル、1991年]、ガッシャブルム峰[8035メートル、1993年]、チョー・オユー[8201メートル、1994年]の四座を制覇していました)、泰史・妙子夫妻の奥多摩での生活、女優市毛良枝さんはじめ多くの人々との付き合い、NHKの特別番組「夫婦で挑んだ白夜の大岩壁」(2007年11月放映)のこと、老年になってからの著者の息子夫妻との山行(富士山など)-父親の視点から世界の登山家の生き方を見続けた証がここにあります。

「語りおろし」です。91歳の俳人金子兜太さんが、石田陽子さんというインタビュアーに、人生観、戦中のトラック島での体験、俳句への思いを語りました。それが文章化され本になりました。
金子さんの人生観は徹頭徹尾、自然体(というより「ありのまま」)、自己流、放浪漂泊の憧れ。「純粋経験」「即物」という言葉が好きらしいです。
またこうも語っています。幸せという言葉も不幸と言う言葉もない、悔いを残しながらの自己本位、田舎者で喧嘩早い、倫理・道徳・人生観はナンセンス、胡散臭い一流の人、人生の安全弁としてカネは欲しい、組織や社会は嫌いで「人間」がいい、と。
秩父の魂にアイデンティティをもち、(あまりきれいな語ではないが)糞尿を愛し、土を好みます。
最後の章で、戦地で俳句をやめる決意をしたものの、俳句の好きな西澤實陸軍少尉と出会い、奇蹟の「陸海軍合同句会」をつくったそうです。この話が大変よいです。
何ものにも縛られず、ありのままを愛し、言いたいことを言い、歌いたいことを歌い、書きたいことを書き、そのように生きれば「悩むことはない」ということです。
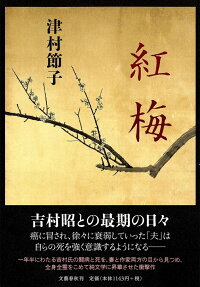
著名なふたりの作家、とくに著者の夫君であった吉村昭さんは、わたしがよく読んだ作家のひとりで、近しい気持ちをもっています。
この書は、その吉村さんの晩年の闘病の様子とそれを支えた津村節子さんの二人三脚の記録です。
夫が舌癌と診断され、その治癒が進んでいたおりの膵臓がんの発見。作家としての仕事(執筆、講演、サイン会など)をこなし、著者はあるときは気丈に、またある時は絶望のなか、家族、知人の支援も受けながら治療と介護に誠心誠意あたったことが滲み出ています。
吉村さんは自身が癌を患、入院したことを、知人に知られないように最大限の努力をはらっていたようですから、本書のような内容のものが出版されることは不本意だったかもしれませんが、著者にとっては書かずにはいられなかった鎮魂歌であったと思います。
治療の内容が克明に記録され、また吉村さんがかかさず日記を書いていたこと、死の直前まで短編小説、エッセイを書いていたこと、最期まで編集者とかかわるその姿勢が折り目正しかったこと、遺言書をしっかり遺していたことなど、いつも傍らにいた妻でなくては書けなかった吉村さんの一面が紹介されていて、好ましかったです。
吉村さんが最期に周囲の阻止を振り切って、自分で点滴の管のつなぎ目をはずし、胸に埋め込んであるカテーテルポートをひきむしった壮絶の場面もかなり詳しく、描写されていて、痛ましいです(pp.166-167)。
本書の末尾で、「育子が夫の背中をさすっている時に、残る力をふりしぼって躯を半回転させたのは、育子を拒否したのだ、と思う。情の薄い妻に絶望して死んだのである。育子はこの責めを、死ぬまで背負ってゆくのだ[著者は自分のことを本書のなかで育子としています]」(p.170)と書いていて、ここはこの本の最初から読んできたものにとっては胸に迫る文章で、思わずウルウルしました。
なお、表題の「紅梅」は、吉村さんの書斎の窓から見えていた庭の樹です。

この巻は全て対談(鼎談ないし座談)です。
第一章は「『人間ドラマ』を書く」と題して、石川達三、荒垣秀雄、秋元秀雄、松本清張との対談。
第二章は「『大阪』に住んで『大阪』を書く」。岡部伊都子、水野多津子、今東光、菊田一夫、浪速千栄子との大阪談義です。
第三章のテーマは「『消えない良心』を書く」。城山三郎、秋元秀雄、三鬼陽之助、伊藤肇、長谷川一夫、ドウス昌代、三國一朗、羽仁進が相手役です。
「山崎豊子自作を語る」シリーズの(1)(2)と重なる話が多いですが、面白かったのは、山崎さんが敬愛していた石川達三との対談。他に松本清張、ドウス昌代が迫力のある対談になっていました。
対談にもいろいろな型があり、一方が著者の話を引きだそうとするものと、対談者がお互いに意見をもっていてそれをぶつけあうというものとがありますが、後者の型をとったほうがいい対談になります。
その意味で、著者とドウス昌代との対談では、両者が日系二世、三世の意識の捉え方、442部隊での日系人の位置と役割についての認識で微妙に差があり(日系人の祖国の認識の理解など。もちろん同じ意見の個所もあるが)、読んでいてその差に興味が惹かれました。
ドウス昌代さんという人のことはしりませんでしたが、山崎さんと同じ作家を職とし、「ブリエラの解放者たち」という同じ日系人兵士を扱った小説を書いているので、対談が良い方に盛り上がっていました。
対談のあとに補章のように「『運命の人』沖縄取材記」があります。
『運命の人』は読み終えたばかりです。
4巻では弓成記者が沖縄で過ごし、記録に取り組むことになるのですが、彼がどの島にたどりついたことにするのかを決める過程、また小説のなかで大きなウエイトをしめる、かつて鉄血勤皇隊とひめゆる学徒隊に所属して戦後結婚した夫婦が沖縄戦を述懐する部分のモデルになった人との出会い、など生き生きとした取材日記で、これ自体が重要な記録のように思えました。









