○東京国立博物館 特別展『生誕150年 黒田清輝-日本近代絵画の巨匠』(2016年3月23日~5月15日)
週末に行った近代絵画展の二つ目は、黒田清輝(1866-1924)の生誕150年を記念した大回顧展。「画業修学の時代 1884-93」「白馬会の時代 1893-1907」「文展・帝展の時代 1907-24」の3期に分けて、黒田の画業と近代洋画の歩みを紹介する。
私は、2007年に東京藝大美術館の『パリへ-洋画家たち百年の夢』展で、黒田清輝のことを少し知って、好きになった。というか、この展覧会は黒田個人の回顧展だったように記憶していた(確認したら「黒田清輝、藤島武二、藤田嗣治から現代まで」という副題がついていたけど、あとの二人のことはよく覚えていない)。
黒田の絵は、どの時代の作品も好きだ。フランス留学時代の『婦人像(厨房)』は藝大美術館で、ちょい色っぽい『マンドリンを持てる女』は東博で、見かけると嬉しい作品。あまり知らなかったけど『赤髪の少女』『祈祷』『針仕事』『摘草』などもいいなあ。どれも古典でしっかり存在感のある女性像。印象派ふうの明るい色彩の風景画もいいと思った。
帰国後の黒田は、京都に滞在して日本的な風俗に魅せられ『舞妓』を描く。ん?この逸話はどこかで聞いたことがある。それから、失われた名画『昔語り』は、パーツ(登場人物)ごとの多数の下絵から、黒田の制作過程が窺える。晩年の『其の日の果て』も同様に完成品は焼失したが、いくつかの下絵が残っている。たぶんこれらは、東博の常設展のミニ特集で取り上げられたことがあるように思う。そういう小さな研究と発見を積み重ねて、特別展の企画になるのかなと、展覧会の舞台裏を覗いた気がして面白かった。
知らなかったのは、黒田が1914年開業の現・東京駅の帝室用玄関中央本屋に壁画の連作を制作していたこと。ただし構想と下絵は黒田だが、実際の制作は教え子の和田英作、田中良、五味清吉がおこなったそうだ。画題が「運輸及造船」「水難救助・漁業」「鉱業及林業」「操車・工業」等々だというのが面白い。まるで共産主義国の壁画みたいだ。小さな写真帖だけが残っているそうだが、今回の展覧会では、空間が再現されていて、興味深かった。
また、黒田にはたくさんのアーカイブ資料(手紙、日記、写真など)が残っていて、これらも見どころ。写真や自画像を見ると、若い頃から人の好さそうな丸顔が変わらなくて、かわいい。貴顕の肖像画もたくさん描いているが、晩年の、誰のために描いたのだか分からない、風景や草花のスケッチが私は好きだ。
師コランや、黒田をとりまく洋画家たちの作品も出ている。浅井忠や久米桂一郎など。山本芳翠の『花化粧』は東博所蔵だというが、記憶にない作品で面白かった。
※お土産はチョコレート(湖畔/自画像/読書)。自画像は要らないかもw
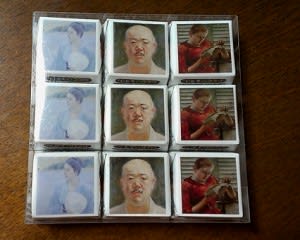
むかし、神奈川歴博で五姓田派の画家を取り上げた『五姓田のすべて』展でもチョコレートを売っていたことを思い出した。
週末に行った近代絵画展の二つ目は、黒田清輝(1866-1924)の生誕150年を記念した大回顧展。「画業修学の時代 1884-93」「白馬会の時代 1893-1907」「文展・帝展の時代 1907-24」の3期に分けて、黒田の画業と近代洋画の歩みを紹介する。
私は、2007年に東京藝大美術館の『パリへ-洋画家たち百年の夢』展で、黒田清輝のことを少し知って、好きになった。というか、この展覧会は黒田個人の回顧展だったように記憶していた(確認したら「黒田清輝、藤島武二、藤田嗣治から現代まで」という副題がついていたけど、あとの二人のことはよく覚えていない)。
黒田の絵は、どの時代の作品も好きだ。フランス留学時代の『婦人像(厨房)』は藝大美術館で、ちょい色っぽい『マンドリンを持てる女』は東博で、見かけると嬉しい作品。あまり知らなかったけど『赤髪の少女』『祈祷』『針仕事』『摘草』などもいいなあ。どれも古典でしっかり存在感のある女性像。印象派ふうの明るい色彩の風景画もいいと思った。
帰国後の黒田は、京都に滞在して日本的な風俗に魅せられ『舞妓』を描く。ん?この逸話はどこかで聞いたことがある。それから、失われた名画『昔語り』は、パーツ(登場人物)ごとの多数の下絵から、黒田の制作過程が窺える。晩年の『其の日の果て』も同様に完成品は焼失したが、いくつかの下絵が残っている。たぶんこれらは、東博の常設展のミニ特集で取り上げられたことがあるように思う。そういう小さな研究と発見を積み重ねて、特別展の企画になるのかなと、展覧会の舞台裏を覗いた気がして面白かった。
知らなかったのは、黒田が1914年開業の現・東京駅の帝室用玄関中央本屋に壁画の連作を制作していたこと。ただし構想と下絵は黒田だが、実際の制作は教え子の和田英作、田中良、五味清吉がおこなったそうだ。画題が「運輸及造船」「水難救助・漁業」「鉱業及林業」「操車・工業」等々だというのが面白い。まるで共産主義国の壁画みたいだ。小さな写真帖だけが残っているそうだが、今回の展覧会では、空間が再現されていて、興味深かった。
また、黒田にはたくさんのアーカイブ資料(手紙、日記、写真など)が残っていて、これらも見どころ。写真や自画像を見ると、若い頃から人の好さそうな丸顔が変わらなくて、かわいい。貴顕の肖像画もたくさん描いているが、晩年の、誰のために描いたのだか分からない、風景や草花のスケッチが私は好きだ。
師コランや、黒田をとりまく洋画家たちの作品も出ている。浅井忠や久米桂一郎など。山本芳翠の『花化粧』は東博所蔵だというが、記憶にない作品で面白かった。
※お土産はチョコレート(湖畔/自画像/読書)。自画像は要らないかもw
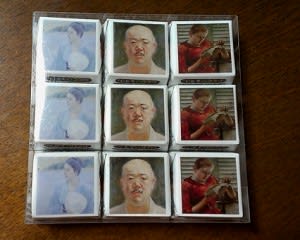
むかし、神奈川歴博で五姓田派の画家を取り上げた『五姓田のすべて』展でもチョコレートを売っていたことを思い出した。














