武将ジャパン2023/05/05
マンガでの連載が終わってもアニメでの盛り上がりが止まらない『ゴールデンカムイ』。
かつてはアシリパが大英博物館の展示ポスターに選ばれるほど評判となり(TOP画像:撮影馬渕まり)、ファンの熱は冷めるどころか加熱している勢いさえ感じます。
◆大英博物館で日本漫画展「Manga マンガ」開催 シンボルは『ゴールデンカムイ』のアシリパさん - ねとらぼ(→link)
そこで今回は、必読の参考書籍に注目!
特にオススメの3冊を紹介させていただきますので、物語を二重三重にお楽しみください。
※アシリパの「リ」はじめ、アイヌ語表記とは異なる部分がございます
『アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」』
アシリパの表紙が美しい一冊。
それが『アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」(→amazon)』です。
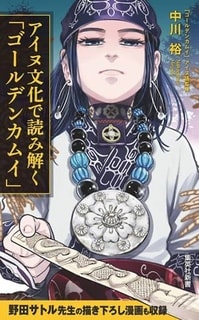
本書については、この一言で終わります。
「ゴールデンカムイファンなら読め! 以上!」
読めば読むほど、あの作品が楽しくなる、そんな必読の書。
これで終わらせてもよいところですが、具体的にドコを読むべきか、ファン以外にも価値はあるのか、併せて解説したいと思います。
◆アシリパの斬新性
中川氏も指摘しておりますように、アシリパというヒロイン像はかなり斬新だと思います。
読者ならばご理解いただけるでしょう。
彼女は従順性があるヒロインではありません。
比較対象として『サムライスピリッツ』のナコルル(アイヌの巫女)がわかりやすいかと思います。
ナコルルの特徴は、こんなところです。
・性格は聖なる巫女タイプである
・動物を含め、殺しを好まないように思える
・言葉遣いは丁寧であり、いつでも穏やかな口調だ
・表情は柔らかいことが多く、おしとやかなタイプに見える
・合理的というよりは情緒的
紫ナコルルといったバリエーションやパロディは、ここでは横に置きまして、これはどうも、こう言いたくなってしまうのです。
あ、アシリパが格闘ゲームキャラクターとして高性能である点も、ここでは関係ありません。
ナコルルは、こんな存在ではないでしょうか。
【マジカル・アイヌ】
元となる言葉は【マジカル・ニグロ】です。
◆「マジカル・ニグロ」、米ハリウッド映画に見る人種差別問題(→link)
マジョリティにとって都合良く、優れた才知があっても、あくまで手助けとなるだけであり、歯向かわない。
彼らは賢く敬愛されていないから、差別じゃない。
そういう言い逃れも通りかねません。
しかし、そういうものでしょうか?
それでいいのでしょうか?
ナコルルだって、人気キャラクターではあります。
しかし、だからといって平等な扱いをされたアイヌであるか。そこは議論の対象となるものでしょう。
ところが、アシリパは結構なバッドガール。
罠や弓矢で獲物を仕留め、杉元や白石が引くほどの残酷さで、淡々と食材にしてしまいます。
おまけに、ネタバレとなるのでここでは触れませんが、彼女には秘めた目的があるかもしれないのです。
時に狡猾であり、相手を騙し抜く手だって持っています。
無邪気で可愛い少女かって?
そりゃ違うでしょ!
この違いは、ディズニーにおけるポカホンタス、メリダやモアナの変化にも通じるものがあります。
カラー・オブ・ザ・ウィンド (ポカホンタス)
https://www.youtube.com/watch?v=fX-XQnzhmjg
映画『メリダとおそろしの森』予告編映像
https://www.youtube.com/watch?v=zczVUzM3nOQ
心優しいナコルルやポカホンタス。
それに対して、アシリパ、メリダ、モアナは武器を持って立ち上がり、不敵な笑みを浮かべて困難へと立ち向かってゆきます。
アイヌは魔法の世界に生きているのか?
そんな強くたくましく、思考回路は徹底してクールであり、合理的なアシリパ。
その源流が、本作からはみえてきます。
読めば読むほど、脳内にあったぼんやりしたアイヌ像が消えてゆくのです。
アイヌは自然を愛していて、傷つきやすく、繊細。
そんなエコロジスト的なイメージが、ぼんやりとある方も多いと思います。私もそうでした。
しかし『ゴールデンカムイ』のアイヌは違いますよね。
あの漫画は、鶴見や尾形を筆頭にして、どこか二面性があり、策略に長けている人物が多数出てきます。
アイヌも、この中に入るでしょう。
アシリパの父であるウイルク、キロランケ、インカラマッ。
本当に信頼してよいのかと疑ってしまいたくなる、そんな人物が多いものです。
まだ幼いエノノカだって、そろばんをパチパチと弾いて計算することに余念がありません。彼女は鯉登あたりより、計算高いかもしれない。
これが、本作が【マジカル・アイヌ】を否定するところではあるのです!
ただ、それは野田先生の意識だけが作り上げたものではない、そう思えて来ます。
本書で解説されるアイヌの知恵は、合理性に満ちています。
厳しい自然の中、狩猟をして生きていくからには、それもその通りだと頷けるのです。
むしろアシリパは、感傷的になる杉元を嗜めることすらあるほど。それも、アイヌの生き方だったのだな、と深く頷いてしまうのです。
エコロジカルで魔法の世界を生きる、そんなふうにアイヌを定義したいのは、和人の驕りではないか? 高慢さではないか?
そう深いところまで感じられて、もう圧倒されるばかりです。
そして、合理性と知恵だけではない、別の何かもそこにはあります。
敢えて言うのであれば、それが【カムイ】かもしれません。
なぜ、野田先生はこの作品を描いているのだろう?
なぜ、中川先生はこの作品の監修者なのだろう?
なぜ、私たちはこの作品を読み、こんなにも感動しているのだろう?
それはただの偶然ではなくて、何かの力によるものなのでは?
そんな力も、本書からは伝わって来ます。
野田先生の考証と創作テクニック
野田先生がいかに気を使っているか。その一方で、大胆に踏み外しているのか。
そこも、本書でわかってきます。
彼の作風はこれですね。
【わかった上で踏み外す】
アイヌ関連の説明は、本書にお任せするとして、一例として、鯉登関連をあげておきましょう。
◆攻撃時に「チェスト!」と叫ばない
興奮していると毛筆手書きでざざっと書いてあるため、わかりにくいのですが「きえー!」です。
これは考証的に正解。
フィクションでは「チェスト!」と叫びながら攻撃する描写が多いものです
考証的に正解である「自顕流の猿叫」
https://www.youtube.com/watch?v=hC6N_U3p2wQ
考証的には不正解でありながら、採用されることが多い「チェスト!」
・ただし、常にキエエエエ!と叫ぶのは、ただ彼の性格が残念だから
正解をわかったうえで、外す。
そんな創作テクニックがわかります。
※以下のリンクは、良くも悪くも薩摩隼人らしさをまとめた記事となります
実際の薩摩隼人はフィクション以上にならず者?漫画やアニメで検証だ
「チタタプ」や「ヒンナヒンナ!」の正しい意味は使い方もありますから、これはもう読まなきゃね!
そうそう、本作でも紹介されているアイヌ料理は、東京・大久保の居酒屋「ハルコロ」で味わえます。
一度訪れてみてください。
『アイヌ民族否定論に抗する』
『ゴールデンカムイ』は、悲惨で哀れなだけではない、強くたくましいアイヌの物語です。それはその通りです。
しかし、歴史の暗い側面を描いていないわけではありません。
アシリパはじめ、アイヌの人々には和人からの収奪と差別がつきまとっています。
杉元のような和人が違うとはいえども、和人全体からの暗い力はあるものなのです。
その歴史こそが、ウイルクやキロランケの動機でもあります。
それは明治時代の過去で終わったことなのでしょうか?
そんなはずはないのです。
アイヌに対するヘイトスピーチは今も続いている
『アイヌ民族否定論に抗する(→amazon)』は、現在進行形で続いているアイヌへのヘイトスピーチを取り上げた一冊です。
SNSにおいて、試しにアイヌ関連で検索をしてみてください。
「アイヌは存在しない!」
「アイヌは特定民族のなりすましだ!」
「アイヌは利権を狙っている!」
「アイヌ新法こそ、他国による日本侵略の手口なのだ!」
といった、とんでもない暴論がまかり通っています。
アシリパたちが直面した差別は、今も続いているのです。
成立した「アイヌ新法」も、この差別解消に至るまでには問題があると指摘されておりました。
◆先住権への配慮を欠いたアイヌ政策 - 杉田聡|WEBRONZA(→link)
私たちは、彼らのことを考えているのか?
『ゴールデンカムイ』のファンであれば、アイヌのことを考えているはず。
そう思うのは、ちょっと楽観的かもしれない。そう感じることがあります。
これは『ゴールデンカムイ』だけではありません。
オリンピックだ、イベントだ、観光の目玉だ……そう珍しいものや観光名物としてもてはやしているだけではないのか?
彼らの声をきちんと聞いているのか?
考えているのか?
考えたくありませんか?
じゃあもういいや、と言えるのだとしたら、それはあなたが和人だからではありませんか?
実際に、こんな声を目にしたこと、聞いたことがあります。
「どうせアイヌなんてもういない。漫画の中だけでしょ」
「アイヌ語なんて、もうなくなったようなものだし。どうせ誰も話せないよ
「アイヌの伝統衣装や模様だって、可愛いから使っちゃっていいものでしょ」
「あの漫画なんて、殺人と裸が出てくるんだから、ノリで受けることをしているだけ。アイヌなんてどうでもいいんだよ」
「楽しければいいじゃん、たかが漫画なんだから」
作中のアシリパやキロランケ、それに杉元が聞いたら、忿怒の形相になりそうな、そんな言葉の数々です。
違います。 アイヌは存在します。アイヌ語は危機に瀕していますが、だからといって消えていいはずもない。
あの作品を読んでも、アイヌを尊重できないのであれば、それはとても残念なことです。
本書を読まねばならない理由。それは、あなたが杉元になれるかどうか、それを問いかけてくる一冊だからです。
杉元佐一――彼のようにアイヌを理解し、戦う和人になれるか?
そのためには、何も杉元のように武装しなくてもよい。傷もいりません。
本書のような知識を身につけ、アイヌについて差別をする人がいれば、それに抗うことができるはずなのです。
杉元になるための武器。それが本書です。
丁寧に、はっきりと、くだらない否定論と陰謀論に抗う一冊です。
『大学による盗骨』
あなたの先祖のお墓から、誰かが遺骨を盗みました。
そんなことがあったらどうします?
言うまでもなく、犯罪です。
しかし、遺骨は戻りません。しかも犯人はこう言うのです。
「研究のためですから」
そんなことが許されるのでしょうか?
想像するだけで怒りと恐怖で凍りつくような話が、実際にあるのです。
どこの国のことか?って、日本ですよ。
『大学による盗骨(→amazon)』では、琉球人とアイヌの盗骨事件を取り上げています。
インチキ「骨相学」の時代
タランティーノの映画『ジャンゴ』に登場する悪役奴隷農場主・キャンディは、黒人奴隷の頭蓋骨を片手に、骨相学について語り始めます。
骨を見れば、黒人が白人と比較して劣っていることがわかる。
あいつらは奴隷にするくらいしか、使い道がないのだと。
映画『ジャンゴ 繋がれざる者』日本版予告編
https://www.youtube.com/watch?v=VYQDZ7ofEFA
胸が悪くなるような描写ですが、これがまかり通っていた時代があります。
帝国時代、植民地主義の時代です。
幕末の混乱をくぐり抜け、西洋から学び始めた和人たち。彼らはアメリカやヨーロッパで、人種差別を学びました。
西洋人だって、先住民や有色人種を差別している――そう理解したのです。
かつて、こうした人種差別を後押ししていたのは、宗教でした。
「奴隷制度は神が創ったものなのだ」
そんな意識が蔓延していたのです。
時代が下ると、その言い訳は通用しません。科学が新たなアプローチとなります。
そして生み出された学問が「骨相学」です。
アイヌの骨が盗まれた背景にも、こんな差別的な学問がありました。
アイヌの骨を調べれば、学術的な研究になる――。そんな西洋からの差別思想を持った和人が、アイヌの墓から骨を盗んでいったのです。
「骨相学」そのものは、現在では一切根拠のないものとして否定されています。
それならば、そのソースとなった骨だって戻すべき。
ところが、それがそうなっていないのです。
学問の道具ではないのに
繰り返しますが、「骨相学」には何の根拠もありません。
それなのに、大学からの骨返還は進んでいない。そんな状況があります。
本書には、大学側がいかにして変換要求を退けてきたのか。
その経緯がまとめられております。
なぜ大学側は、こんな苦しい言い訳をしてまで、変換を拒むのか?
本書の行間から、何か黒いものすら見えてくる。そんな気がします。
怒りと苦しみがドグマとしてそこにはある
一冊目は楽しい。
楽しいだけではありませんが、それはそうなのです。
しかし、二冊目、そして三冊目は読むと怒りでどうしようもなくなるほど、そんな揺さぶられる暗い感情を伴います。
杉元にせよ、鯉登にせよ、怒りのあまり絶叫する人物が劇中には存在します。
とめどない怒りを秘めたまま、策略に走る鶴見や尾形も。
そして忘れてはならない、ウイルクとキロランケ。
彼らの激烈で、犠牲をものともしない言動の数々。
その背後には、どんな苦しみや悲しみがあったのだろう?
二人の背景には、こんな歴史があったのだ。
それがわかる二冊です。
そしてそんな歴史背景を伴う怒りを知ったからこそ、あの作品にはドグマのような何かが込められたのだと。そう感じることができます。
それだけではない、生きる力、明日を目指す力も。読後感は必ずしも軽いだけではありません。
しかし、是非ともこの三冊を読んで『ゴールデンカムイ』の世界に浸かっていただければと思います!
https://bushoojapan.com/historybook/2023/05/05/122232
マンガでの連載が終わってもアニメでの盛り上がりが止まらない『ゴールデンカムイ』。
かつてはアシリパが大英博物館の展示ポスターに選ばれるほど評判となり(TOP画像:撮影馬渕まり)、ファンの熱は冷めるどころか加熱している勢いさえ感じます。
◆大英博物館で日本漫画展「Manga マンガ」開催 シンボルは『ゴールデンカムイ』のアシリパさん - ねとらぼ(→link)
そこで今回は、必読の参考書籍に注目!
特にオススメの3冊を紹介させていただきますので、物語を二重三重にお楽しみください。
※アシリパの「リ」はじめ、アイヌ語表記とは異なる部分がございます
『アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」』
アシリパの表紙が美しい一冊。
それが『アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」(→amazon)』です。

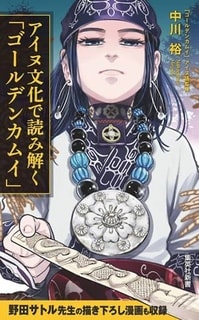
本書については、この一言で終わります。
「ゴールデンカムイファンなら読め! 以上!」
読めば読むほど、あの作品が楽しくなる、そんな必読の書。
これで終わらせてもよいところですが、具体的にドコを読むべきか、ファン以外にも価値はあるのか、併せて解説したいと思います。
◆アシリパの斬新性
中川氏も指摘しておりますように、アシリパというヒロイン像はかなり斬新だと思います。
読者ならばご理解いただけるでしょう。
彼女は従順性があるヒロインではありません。
比較対象として『サムライスピリッツ』のナコルル(アイヌの巫女)がわかりやすいかと思います。
ナコルルの特徴は、こんなところです。
・性格は聖なる巫女タイプである
・動物を含め、殺しを好まないように思える
・言葉遣いは丁寧であり、いつでも穏やかな口調だ
・表情は柔らかいことが多く、おしとやかなタイプに見える
・合理的というよりは情緒的
紫ナコルルといったバリエーションやパロディは、ここでは横に置きまして、これはどうも、こう言いたくなってしまうのです。
あ、アシリパが格闘ゲームキャラクターとして高性能である点も、ここでは関係ありません。
ナコルルは、こんな存在ではないでしょうか。
【マジカル・アイヌ】
元となる言葉は【マジカル・ニグロ】です。
◆「マジカル・ニグロ」、米ハリウッド映画に見る人種差別問題(→link)
マジョリティにとって都合良く、優れた才知があっても、あくまで手助けとなるだけであり、歯向かわない。
彼らは賢く敬愛されていないから、差別じゃない。
そういう言い逃れも通りかねません。
しかし、そういうものでしょうか?
それでいいのでしょうか?
ナコルルだって、人気キャラクターではあります。
しかし、だからといって平等な扱いをされたアイヌであるか。そこは議論の対象となるものでしょう。
ところが、アシリパは結構なバッドガール。
罠や弓矢で獲物を仕留め、杉元や白石が引くほどの残酷さで、淡々と食材にしてしまいます。
おまけに、ネタバレとなるのでここでは触れませんが、彼女には秘めた目的があるかもしれないのです。
時に狡猾であり、相手を騙し抜く手だって持っています。
無邪気で可愛い少女かって?
そりゃ違うでしょ!
この違いは、ディズニーにおけるポカホンタス、メリダやモアナの変化にも通じるものがあります。
カラー・オブ・ザ・ウィンド (ポカホンタス)
https://www.youtube.com/watch?v=fX-XQnzhmjg
映画『メリダとおそろしの森』予告編映像
https://www.youtube.com/watch?v=zczVUzM3nOQ
心優しいナコルルやポカホンタス。
それに対して、アシリパ、メリダ、モアナは武器を持って立ち上がり、不敵な笑みを浮かべて困難へと立ち向かってゆきます。
アイヌは魔法の世界に生きているのか?
そんな強くたくましく、思考回路は徹底してクールであり、合理的なアシリパ。
その源流が、本作からはみえてきます。
読めば読むほど、脳内にあったぼんやりしたアイヌ像が消えてゆくのです。
アイヌは自然を愛していて、傷つきやすく、繊細。
そんなエコロジスト的なイメージが、ぼんやりとある方も多いと思います。私もそうでした。
しかし『ゴールデンカムイ』のアイヌは違いますよね。
あの漫画は、鶴見や尾形を筆頭にして、どこか二面性があり、策略に長けている人物が多数出てきます。
アイヌも、この中に入るでしょう。
アシリパの父であるウイルク、キロランケ、インカラマッ。
本当に信頼してよいのかと疑ってしまいたくなる、そんな人物が多いものです。
まだ幼いエノノカだって、そろばんをパチパチと弾いて計算することに余念がありません。彼女は鯉登あたりより、計算高いかもしれない。
これが、本作が【マジカル・アイヌ】を否定するところではあるのです!
ただ、それは野田先生の意識だけが作り上げたものではない、そう思えて来ます。
本書で解説されるアイヌの知恵は、合理性に満ちています。
厳しい自然の中、狩猟をして生きていくからには、それもその通りだと頷けるのです。
むしろアシリパは、感傷的になる杉元を嗜めることすらあるほど。それも、アイヌの生き方だったのだな、と深く頷いてしまうのです。
エコロジカルで魔法の世界を生きる、そんなふうにアイヌを定義したいのは、和人の驕りではないか? 高慢さではないか?
そう深いところまで感じられて、もう圧倒されるばかりです。
そして、合理性と知恵だけではない、別の何かもそこにはあります。
敢えて言うのであれば、それが【カムイ】かもしれません。
なぜ、野田先生はこの作品を描いているのだろう?
なぜ、中川先生はこの作品の監修者なのだろう?
なぜ、私たちはこの作品を読み、こんなにも感動しているのだろう?
それはただの偶然ではなくて、何かの力によるものなのでは?
そんな力も、本書からは伝わって来ます。
野田先生の考証と創作テクニック
野田先生がいかに気を使っているか。その一方で、大胆に踏み外しているのか。
そこも、本書でわかってきます。
彼の作風はこれですね。
【わかった上で踏み外す】
アイヌ関連の説明は、本書にお任せするとして、一例として、鯉登関連をあげておきましょう。
◆攻撃時に「チェスト!」と叫ばない
興奮していると毛筆手書きでざざっと書いてあるため、わかりにくいのですが「きえー!」です。
これは考証的に正解。
フィクションでは「チェスト!」と叫びながら攻撃する描写が多いものです
考証的に正解である「自顕流の猿叫」
https://www.youtube.com/watch?v=hC6N_U3p2wQ
考証的には不正解でありながら、採用されることが多い「チェスト!」
・ただし、常にキエエエエ!と叫ぶのは、ただ彼の性格が残念だから
正解をわかったうえで、外す。
そんな創作テクニックがわかります。
※以下のリンクは、良くも悪くも薩摩隼人らしさをまとめた記事となります
実際の薩摩隼人はフィクション以上にならず者?漫画やアニメで検証だ
「チタタプ」や「ヒンナヒンナ!」の正しい意味は使い方もありますから、これはもう読まなきゃね!
そうそう、本作でも紹介されているアイヌ料理は、東京・大久保の居酒屋「ハルコロ」で味わえます。
一度訪れてみてください。
『アイヌ民族否定論に抗する』
『ゴールデンカムイ』は、悲惨で哀れなだけではない、強くたくましいアイヌの物語です。それはその通りです。
しかし、歴史の暗い側面を描いていないわけではありません。
アシリパはじめ、アイヌの人々には和人からの収奪と差別がつきまとっています。
杉元のような和人が違うとはいえども、和人全体からの暗い力はあるものなのです。
その歴史こそが、ウイルクやキロランケの動機でもあります。
それは明治時代の過去で終わったことなのでしょうか?
そんなはずはないのです。
アイヌに対するヘイトスピーチは今も続いている
『アイヌ民族否定論に抗する(→amazon)』は、現在進行形で続いているアイヌへのヘイトスピーチを取り上げた一冊です。
SNSにおいて、試しにアイヌ関連で検索をしてみてください。
「アイヌは存在しない!」
「アイヌは特定民族のなりすましだ!」
「アイヌは利権を狙っている!」
「アイヌ新法こそ、他国による日本侵略の手口なのだ!」
といった、とんでもない暴論がまかり通っています。
アシリパたちが直面した差別は、今も続いているのです。
成立した「アイヌ新法」も、この差別解消に至るまでには問題があると指摘されておりました。
◆先住権への配慮を欠いたアイヌ政策 - 杉田聡|WEBRONZA(→link)
私たちは、彼らのことを考えているのか?
『ゴールデンカムイ』のファンであれば、アイヌのことを考えているはず。
そう思うのは、ちょっと楽観的かもしれない。そう感じることがあります。
これは『ゴールデンカムイ』だけではありません。
オリンピックだ、イベントだ、観光の目玉だ……そう珍しいものや観光名物としてもてはやしているだけではないのか?
彼らの声をきちんと聞いているのか?
考えているのか?
考えたくありませんか?
じゃあもういいや、と言えるのだとしたら、それはあなたが和人だからではありませんか?
実際に、こんな声を目にしたこと、聞いたことがあります。
「どうせアイヌなんてもういない。漫画の中だけでしょ」
「アイヌ語なんて、もうなくなったようなものだし。どうせ誰も話せないよ
「アイヌの伝統衣装や模様だって、可愛いから使っちゃっていいものでしょ」
「あの漫画なんて、殺人と裸が出てくるんだから、ノリで受けることをしているだけ。アイヌなんてどうでもいいんだよ」
「楽しければいいじゃん、たかが漫画なんだから」
作中のアシリパやキロランケ、それに杉元が聞いたら、忿怒の形相になりそうな、そんな言葉の数々です。
違います。 アイヌは存在します。アイヌ語は危機に瀕していますが、だからといって消えていいはずもない。
あの作品を読んでも、アイヌを尊重できないのであれば、それはとても残念なことです。
本書を読まねばならない理由。それは、あなたが杉元になれるかどうか、それを問いかけてくる一冊だからです。
杉元佐一――彼のようにアイヌを理解し、戦う和人になれるか?
そのためには、何も杉元のように武装しなくてもよい。傷もいりません。
本書のような知識を身につけ、アイヌについて差別をする人がいれば、それに抗うことができるはずなのです。
杉元になるための武器。それが本書です。
丁寧に、はっきりと、くだらない否定論と陰謀論に抗う一冊です。
『大学による盗骨』
あなたの先祖のお墓から、誰かが遺骨を盗みました。
そんなことがあったらどうします?
言うまでもなく、犯罪です。
しかし、遺骨は戻りません。しかも犯人はこう言うのです。
「研究のためですから」
そんなことが許されるのでしょうか?
想像するだけで怒りと恐怖で凍りつくような話が、実際にあるのです。
どこの国のことか?って、日本ですよ。
『大学による盗骨(→amazon)』では、琉球人とアイヌの盗骨事件を取り上げています。
インチキ「骨相学」の時代
タランティーノの映画『ジャンゴ』に登場する悪役奴隷農場主・キャンディは、黒人奴隷の頭蓋骨を片手に、骨相学について語り始めます。
骨を見れば、黒人が白人と比較して劣っていることがわかる。
あいつらは奴隷にするくらいしか、使い道がないのだと。
映画『ジャンゴ 繋がれざる者』日本版予告編
https://www.youtube.com/watch?v=VYQDZ7ofEFA
胸が悪くなるような描写ですが、これがまかり通っていた時代があります。
帝国時代、植民地主義の時代です。
幕末の混乱をくぐり抜け、西洋から学び始めた和人たち。彼らはアメリカやヨーロッパで、人種差別を学びました。
西洋人だって、先住民や有色人種を差別している――そう理解したのです。
かつて、こうした人種差別を後押ししていたのは、宗教でした。
「奴隷制度は神が創ったものなのだ」
そんな意識が蔓延していたのです。
時代が下ると、その言い訳は通用しません。科学が新たなアプローチとなります。
そして生み出された学問が「骨相学」です。
アイヌの骨が盗まれた背景にも、こんな差別的な学問がありました。
アイヌの骨を調べれば、学術的な研究になる――。そんな西洋からの差別思想を持った和人が、アイヌの墓から骨を盗んでいったのです。
「骨相学」そのものは、現在では一切根拠のないものとして否定されています。
それならば、そのソースとなった骨だって戻すべき。
ところが、それがそうなっていないのです。
学問の道具ではないのに
繰り返しますが、「骨相学」には何の根拠もありません。
それなのに、大学からの骨返還は進んでいない。そんな状況があります。
本書には、大学側がいかにして変換要求を退けてきたのか。
その経緯がまとめられております。
なぜ大学側は、こんな苦しい言い訳をしてまで、変換を拒むのか?
本書の行間から、何か黒いものすら見えてくる。そんな気がします。
怒りと苦しみがドグマとしてそこにはある
一冊目は楽しい。
楽しいだけではありませんが、それはそうなのです。
しかし、二冊目、そして三冊目は読むと怒りでどうしようもなくなるほど、そんな揺さぶられる暗い感情を伴います。
杉元にせよ、鯉登にせよ、怒りのあまり絶叫する人物が劇中には存在します。
とめどない怒りを秘めたまま、策略に走る鶴見や尾形も。
そして忘れてはならない、ウイルクとキロランケ。
彼らの激烈で、犠牲をものともしない言動の数々。
その背後には、どんな苦しみや悲しみがあったのだろう?
二人の背景には、こんな歴史があったのだ。
それがわかる二冊です。
そしてそんな歴史背景を伴う怒りを知ったからこそ、あの作品にはドグマのような何かが込められたのだと。そう感じることができます。
それだけではない、生きる力、明日を目指す力も。読後感は必ずしも軽いだけではありません。
しかし、是非ともこの三冊を読んで『ゴールデンカムイ』の世界に浸かっていただければと思います!
https://bushoojapan.com/historybook/2023/05/05/122232










![[戦後80年]故郷失った先住民族 日本軍が占領したアッツ島 子孫 伝統文化の回復目指す](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/27/84/284d902630ea45f061532a937be6178d.png)














