
入院中の家族がつい最近転院し、家から遠くなってしまいました。遠いのは二の次で快適な院内生活を送らせてくれることを第一に願っています。ただ遠いので通うのはチャリでこの暑さだと心配で、バスを乗り継いだり、電車とバス2本乗り継ぐとか選択肢はいくつかありますが、すいすいとは行けない感じ。反対に考えれば普段ご縁のない土地なのでこういう機会に乗り継ぎの合間にも土地を知るとか近場の興味あるところに寄ってみることも悪くないかとも、、。
前書きが長くなってしまいました。今日も厳しい暑さでしたが、病院の面会時間の前に葛飾区青戸に寄ってきました。じつはここ、実質的な最後の今戸焼屋さんだった「内山英良さん」がお住まいだった土地なのです。言葉の綾で「あそこにまだいるじゃないか」という人もいるかと思いますが、実際の仕事の内容や使用された原料も含め掛け値なしで本当の今戸焼屋さんで最後の方になってしまった、、と私は思います。
聞けば3年以上前にお亡くなりになられたそうです。京成青砥駅と高砂駅の間に流れる中川の畔にある内山さんをお訪ねしたのは、私は当時25歳でしたから30年近く前になります。当時は葛飾区内には白井善次郎家(白井本家)の白井和夫さんが宝町に、四つ木には橋本家が操業されていました。関東大震災、東京大空襲による被災や今戸近辺の宅地化などを理由に今戸焼屋さんの多くは葛飾や足立、または関西に移住し、戦後の今戸焼の実質的な生産の中心は葛飾区内に移りました。そして最後までご活躍された3人の中で最後の今戸焼屋さんが内山さんとなったわけです。
内山さんの仕事場にはじめてお邪魔したときびっくりしました。敷地内に大きな土の山があって、「こっちはさくい(荒い)土」「こっちはねばい(粘りのある)土」で「どっちも地元の建設屋さんが運んで持ってきてくれんだよ。ふたつを練り込んで丁度いい土にして使うんだよ」と仰ってました。その時作られていた製品の多くは植木鉢と焙烙で粘土を詰めた「シッタ」を機会ろくろにセットして回転させ、こてを下ろして余分な粘土を刳りぬいて成形されていましたが、内山さんの場合当然手ろくろの技術を持った上で大量に規格を合わせて作るため機会ろくろを使われていたのでした。お邪魔すれば気さくに案内してくれました。体つきのがっしり大きなそれでいて心優しい感じのおじさんでした。
その後お寄りする機会がないうちに亡くなられたということで、これで昔ながらの今戸焼屋さんはいなくなってしまったのだな、、と思っていたのです。
逆に言えば、宝町にお住まいだった白井和夫さんにも青戸の内山さんにもお目にかかって僅かですがお話を聞くことができたというのは幸いだったなと思います。(その当時、お話の中に出てくる技術的な話とか十分に咀嚼しきれていなかったということは、今になって残念でなりません。)
さて今日青戸へ行ったのは亡くなられた内山さんがご生前お作りになられた製品が青戸に工場のある老舗の手焼煎餅屋さんである「神田淡平」さんに少しだけ残っていてそれを頒けてくださるということでお邪魔したのです。

お店は内神田にあるそうですが、作っている工場の佇まい、素敵です。お話によれば五百数十年前の応永年間からこの地(今は青戸という町名ですが昔は一帯「淡之須」と呼ばれていた)に居を構えていらっしゃるそうで、もともと武士でだったのを武を捨て「平ぜむ殿」として人々に親しまれ、自ら「淡平」と名乗られたのが今まで続く屋号のはじまりなのだそうです。今日お邪魔してご主人からお時間いただいていろいろ教えていただいたのですが、乾燥した煎餅の生地を網に乗せて焼く工程では、放っておくと熱で反り返ってしまうので鏝で力を入れて押さえるのだそうで、その鏝が昔は今戸焼製のものが普通だったのがいつからか他の素材に変わっていった。草加辺りでも昔は今戸焼製の鏝だったのだろうが、今では他の産地、例えば益子産で施釉されたものを使っているらしい、、との由。本来今戸焼の素焼きで使用されていた理由は素焼きだと熱の伝導が鈍いので熱くならないで使いやすく、施釉とか堅い焼焼き物だと熱くて使いづらいのではないかということでした。また昔はお煎餅の生地屋さんから生地を仕入れる場合、生地屋さんが今戸焼の鏝を添えて卸していたものだそうです。
「淡平」さんのお宅も今戸焼の「内山さん」のお宅も揃って中川の西岸にあり、地続きで内山さんに昔ながらの今戸焼製の鏝をお願いして以来久しく作ってもらっていたそうです。一番上の画像の向かって右が内山さん製の鏝です。お煎餅が反り返らないよう、力をうんと入れて押さえることもあり「持ち手」も部分が割れてしまったものなのだそうですが、特別に頂戴しました。壊れているといっても、これこそ実際に使われた証拠。内山さんとしては手間がかかって大変なのをお願いして作ってくださったそうです。
画像右は「淡平」さんの創業周年記念の折り、内山さんに「土器(かわらけ)」を作ってもらった残りであまり残っていないのをお譲りいただきました。「神田淡平」という陰刻(落款)が入っています。この土器(かわらけ)こそ内山さんの最後のお仕事になったのだそうです。
それにしても戦後の実質的な今戸焼の中心であった葛飾区内から最後まで操業されていた内山さんがお亡くなりになったということは実質今戸焼の終わりとも言えることで残念のひとことで片付けられない現実です。あと余断ですが、ずーっと前、それも昭和40年代頃からマスコミで取り上げられた記事の中では葛飾の今戸焼屋さんたちに光を当てるものが少なかったのではないかと思います。葛飾の今戸焼屋さんたちがまだ操業されていた当時に既に「最後に残る一軒の今戸焼屋」という形容を他の家だけが受ける記事って少なくなかったと思います。何とも皮肉で矛盾した話です。その理由のひとつとして今戸焼という言葉からのイメージというものが戦後ほとんど大衆から離れてしまったからではないかと思います。「今戸焼?今川焼のことですか?」というやりとりは単なるギャグではなくて実際に何度も耳にしています。それと戦後「今戸焼」という言葉は郷土玩具の愛好家によって「今戸焼の土人形」という狭いイメージになっていったということもあるのではないでしょうか。葛飾区内には戦前までには今戸焼屋さんで人形も作っていたという記録もありますが、実際には今戸焼屋といっても製品はさまざまで人形を作る家だけが今戸焼屋なのではなく、人形屋さんは今戸焼屋さんの中のごく一部だけでした。また今戸人形屋さんは浅草今戸町内の尾張屋・金沢春吉翁(明治元年~明治19年)を最後に伝統は途絶えてしまっています。
さびしいな、時代の流れとはいってもはじまりません。それでも今日最後の今戸焼屋さん「内山英良」さんの製品に触れることができて何よりでした。「神田淡平」さんにはお世話になりました。


「神田淡平」さんでは今戸焼の鏝にちなんだ「今戸焼」というお煎餅も出されているそうです。今日工場でお尋ねしたのですが神田のお店のほうに出荷された後のようなので、今後お店に行って買って味見してみたいと思います。奇しくも亡くなられた永六輔さんは長年にわたってこちら「淡平」さんとは御懇意だったそうで、お店の商標をはじめコピーライトも永さんによるもの。生前のお付き合いからTV局からコメントの撮影を先日受けたとのこと。浅草生まれの永さんにとって江戸東京このみのお煎餅が好物のひとつだったようです。

















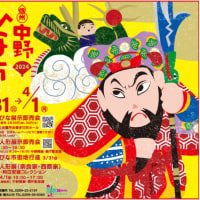


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます