
基本は、ジブリファンの池澤夏樹と鈴木敏夫の対談。場が熱くなると、鈴木が「宮崎駿とはいかに変な人間であるか」を主張し始めるのがおかしい。
高畑勲と大江健三郎が東大の仏文で同級生だったとか、「君たちはどう生きるか」の主人公が少年であることに鈴木は猛然と反対した(ジブリ作品のほとんどは少女が主役)とか、初めて知る。
なぜ少年であることに宮崎がこだわったかといえば、あの主人公こそが宮崎駿自身だから……なるほどぉ!

基本は、ジブリファンの池澤夏樹と鈴木敏夫の対談。場が熱くなると、鈴木が「宮崎駿とはいかに変な人間であるか」を主張し始めるのがおかしい。
高畑勲と大江健三郎が東大の仏文で同級生だったとか、「君たちはどう生きるか」の主人公が少年であることに鈴木は猛然と反対した(ジブリ作品のほとんどは少女が主役)とか、初めて知る。
なぜ少年であることに宮崎がこだわったかといえば、あの主人公こそが宮崎駿自身だから……なるほどぉ!

大谷の嫁篇はこちら。
「ぼくの本棚に鳥山さんの漫画はない。鳥山さんの本で持っているのはこの2冊の画集がすべてだ」
江口寿史が鳥山明の訃報を知ってインスタグラムに投稿。江口は、自分の作品とちがって、鳥山明は画で漫画本来の魅力を復権させたと評価している。
キャラクターやストーリーに傾いた時代に、大友克洋や高野文子などのニューウェイブが台頭。彼らとほぼ同時期に登場したのが鳥山明だったと総括している。
ラーメン屋のカウンターでジャンプを開いても、鳥山明の作品はもちろん掲載されていない。しかし、あの「ONE PIECE」に鳥山の影響を見るのは容易だろう。というか、彼の影響を受けなかった漫画家っているのかな。
「ばかやろう」篇につづく。

ドラゴンボールのオンエアがフジテレビで始まってから数日後、わたしはあるアニメオタクと話していた。
「どうだった?」
「……中間色がよく出てました」
さすがオタク、と感じ入った。そこにこだわるか。
彼にとっては、ドラゴンボールがそこにあるのは当然で、どこまでのレベルかだけが問題だったのだ。
Dr.スランプの連載が始まるまで、ジャンプの編集部から鳥山明は徹底的にしごかれ、何度も何度も書き直しを命ぜられたのは有名な話だ。同時に、ドラゴンボールの連載に彼が疲れ果て、早く終わらせてくれと主張したのにそっちも拒否されたと。
わたしはドラゴンクエストを気を失うまでやりまくった人間なので、鳥山明の訃報には呆然としている。
いろんな経緯から、彼の画風は最初から完成されていた。縁取りがきっちりとしていて、同時に丸っこいキャラはなんとも愛らしかった。その究極がスライムだろうと思う。完璧。
つくづくと思う。彼はマンガ家としてすばらしいのはもちろん、“日本の画風”すら鳥山明に誘導したではないか。
銀行の椅子に座りながら、スマホで彼の訃報に驚愕。
「44番の番号札でお待ちのお客様あ」
ちょっと自分が呼ばれたのか判然としない。あたふた。
「何をそんなにあわててるんですか」と銀行のお姉さん。
「鳥山明が死んだのにびっくりしてたんだよ」
「え」
日本全国が、あるいは全世界が驚くことになった。

アニメ製作のお話。とくれば製作配給が東映なのもうなずける。「白蛇伝」「太陽の王子ホルスの大冒険」「長靴をはいた猫」などの東映動画の伝統もあるわけだし(この東映動画の労働組合で活動していたのが高畑勲と宮崎駿)。
その、アニメの話でハケンとくれば、きっと派遣アニメということでアニメーターのひどい労働環境とかが描かれる……と思ったら、覇権アニメだったんですね。そのクールにおける№1となったアニメだけが覇権を名のれるというならわしが背景にあるみたい。同クールどころか土曜日の5時(わたしの世代にとってはファーストガンダムだ)に直接対決する。
ヒロインの瞳(吉岡里帆)は、県庁を退職してアニメの業界に飛び込んだ。自分の理想とする作品を希求するが、予算や、保守的なスタッフなどによって妥協を迫られていく。
対決相手の王子(中村倫也)は圧倒的な才能をもちながら、気分屋であるためにまわりは振り回されてばかりだ。アニメ対決に世間は盛り上がるが……
辻村深月の原作がよほど周到なのだろうと想像できる。そうです読んでないんですわたし(笑)。暴走するヒロインと冷徹な貴公子、という単純な図式にしていないあたりがすばらしい。
結果的に興行はふるわなかったようだが、その出来と熱狂的なファンの支持もあって評価は高い。よほど手練れの監督による作品かと思ったら、まだ長編映画は2作目の若手、吉野耕平の手によるものだった。
この作品がステップとなって、「沈黙の艦隊」に抜擢されたのだろう。納得の娯楽作。
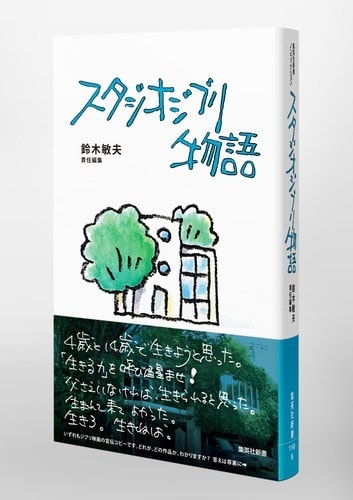
いきなりですが、ここでクイズ。次の三作品のなかで、スタジオジブリの作品ではないのはどれでしょう。
①「風の谷のナウシカ」
②「平成狸合戦ぽんぽこ」
③「天空の城ラピュタ」
……正解はナウシカ。これは宮崎駿にとって、ジブリを立ち上げる前の作品です。この「スタジオジブリ物語」は、ジブリに在籍していたライターが、鈴木敏夫の依頼によって編年体で会社の過去をつづったもの。社史ですかね。これが面白いんだ。知らないネタがたくさん仕込んであった。
たとえばそのナウシカ。この映画の製作は困難を極めた。特に資金面。
「原作のないアニメ映画はありえない」
とされたため、鈴木敏夫が在籍していた雑誌「アニメージュ」に宮崎駿がコミック連載開始。つまり原作の方があとから追いかけたのである。その単行本全部買ってますわたし。すばらしいですよあの展開は。
また、およそヒットが見込めないと予想されたため、その予想を上回るヒットとなったので宮崎駿には6千万円もの金が転がり込んだとか。その使いみちに困った宮崎は、こちらは確実にヒットが見込めないジブリの盟友である高畑勲の「柳川堀割物語」につぎこんだというオチがついている。
それにしても宮崎駿というのは業の深いクリエイターだと思う。日航機内での上映が予定されていた「紅の豚」は次第に大作となり、あのように自意識丸出しの作品に仕上がることになった。妻はどうにも肌に合わないらしいのだが、「もののけ姫」はやはり時代を象徴していたんだと思う。文句なく名作。
一方で興味深かったのは、考えてみれば当然のことなのだが、ジブリにだってボツ企画はいくつもあったのだった。わたしが観たかったのは高畑勲の「平家物語」かな。まあ、この構想が「かぐや姫の物語」に結実したのだから文句はないんですけど。

えーと、公開までまったく情報を明かさなかったんだよね。それは宣伝の手法としてありだと思います。同じような形をとったTBSの「VIVANT」だって、きっと視聴率以外のところで元を取るんでしょうから。っていうか見たいけれども「どうする家康」をまとめるので精一杯の時間なんですよ(笑)
にしてもこの上から目線のタイトルはどうだろう。吉野源三郎の書にインスパイアされたという形になっているんだけど、これほど見たくないと思えるタイトルはなかなかない。
しかも見た経緯が情けない。どうしたって宮崎駿の新作を見逃すわけにはいかない。上から目線のタイトルでも、たとえばあの「魔女の宅急便」ですら大冒険活劇にした人だよ宮崎駿。
ほんとは10時35分のフォーラム東根で「名探偵ポワロ ベネチアの亡霊」を見て、それから13時15分の宮崎駿に行くはずだったの。ところが、国道13号線を右折しようと思ったら、あれ?なんでとこにヤマザワが。道を間違えたのか……
そんなこんなでポワロは断念。そして山形まで丸文ラーメンを食べに行き、初めてイオンシネマ天童に入ってこの作品を観た。
断言します。すばらしい作品でした。あの“母との本当の別れ”に泣けない人はいないと思う。
主人公のこれからの生活を、どう生きるかと想像させるエンディングがいい。
これまでの宮崎作品の引用もうれしくて(あのパンの切り方、あの追っかけ、異形のおばあちゃん、波の形)宮崎駿の、ひょっとして最後の挨拶……いやありえないな。あの人が創造をやめるものか。
えーと、言いたいことはもっといっぱいあるけどとりあえずネタバレになってないですよね。

いくらなんでもSONYはスパイダーマンつくり過ぎでしょ、と思っていたら、MARVELとの契約の関係でハイペースに製作しないと映画化権を失ってしまうらしい。たいへんだなあ。
にしても近年のスパイダーマンは連戦連勝である。トム・ホランドがピーター・パーカーを演じる本線はもちろん(それにしても「ノー・ウェイ・ホーム」はヒットしましたねえ)、スピンオフの前作「スパイダーバース」は、興行が成功したうえにアカデミー賞(長篇アニメーション賞)までとるハイレベルな作品となっていた。
今回もすばらしい。練りに練られた脚本と、圧倒的な映像表現。めまぐるしいアクションと、ある事情で“涙が上に落ちていく”叙情。いやはや見終わってへとへと。おおいに満足はしましたが。
日本でもある程度のヒットはしているものの、アメリカでのバカヒットには遠くおよばない。あの人たちは体力ありそうだもんなあ。

その1はこちら。
12時からの回は3D吹替版。3D料金がかかる上に、メガネも持っていなかったので400円上乗せ。うわあ、2000円越えか。しまった。教職員互助会が配布した補助券があれば楽勝だったのに。
でも、窓口のお姉さんが
「あのぉ、スタンプがたまっているので、招待券で入場できますけど」
「え」
「3D料金とメガネ代はいただきますが」
計700円で入場。ラッキー。席は前から2列目のど真ん中を指定。
「見上げるような席ですけど」
いいのいいの。メガネにクリップオン式の3Dメガネをセット。館内はそれほど混み混みというわけでもない。まあ、家族で3Dだとかなりお高くなっちゃうしね。
製作はミニオンズのイルミネーションと任天堂。製作者としてマリオの生みの親、宮本茂さんの名もある。世界的にバカヒットしているので、関係各位は大喜びだろう。
オープニングからしばらくは調子が出ない。マリオとルイージのドジぶりにいらいらさせられる。またおなじみのファーザーコンプレックスものかよ。しかしゲームでおなじみの画面や音楽のつるべ打ち、マリオカートそのまんまのカーアクションなどで興奮してくる。
そうなの、この映画の成功は、その徹底した“そのまんま”さにあるんだと思う。ピーチ姫に課された“面”を、クリアできずにボロボロになるマリオは、ゲーム初心者のころ、何度もゲームオーバーしてくやしがった自分のことだし、タヌキマリオになって飛翔する爽快さもまた、ゲームでおなじみのものだ。
無限増殖や、コイン集めなどが今回ほとんど描かれなかったが、これはもう確実に作られるであろう続篇に期待。

雨の日曜。こんな日は映画だ。しかし前の週、鶴岡まちなかキネマに行って「RRR」を観ようとしたら
「満杯です。すみません」
おおお、残念だけど、まちなかキネマにとっては朗報。だったら続映してくれればいいのに……続映決定でした。しかしあさイチの上映のため、もう間に合わない。年寄りのくせにどんだけ寝てるんだ。
ならば三川イオンシネマか。「銀河鉄道の父」やってるし。でも、休日のイオンシネマって知り合いがたくさんいるようで気が重い(なぜだ)。
そこでふと気づく。東根に行ったらどうだと。あと1時間半後に黒澤明の名作をリメイクした(しかも脚本がカズオ・イシグロだ)「生きる Living」上映だ。迷っている暇はない。スタートぉ!
いつもは1時間40分ぐらいの距離だけれども、自動車道が東根まで延伸され、しかも無料供用されているので楽勝……じゃなかった。東根北ICで下りるべきだったのに東根ICまで行ってしまい、13号線を戻ってフォーラム東根へ。15分遅れ。さすがにダメでしょ。
じゃあこれから間に合う映画で観たいのはないか。
「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」
「生きる」との圧倒的な差(笑)。振れ幅大きすぎ。でも、ファミコン時代からマリオに淫してきたわたしだもの。正しい選択だ。東根だから生徒も知り合いもいないだろうし(だからなぜ嫌なんだ)。以下次号。

もうとまらない。二週続けて鶴岡まちなかキネマに行ってしまいました。これだけは見逃せないと心に決めていた「犬王」。
どんなファクターで決心したかは判然としない。だってわたしはこのアニメの監督も脚本も、どんな映画かもまったく知らなかったのだ。なんとなく、面白そうという雰囲気だけ。
当たりでした。
南北朝の時代。異形な姿で生まれた赤ん坊。誰もが彼を疎んじるが、彼=犬王には能楽(当時は猿楽と呼ばれていた)の才があった。
一方、壇ノ浦で生まれ育った漁師の息子、友魚(ともな)は足利義満の部下に壇ノ浦の合戦で失われた三種の神器のひとつ、草薙の剣を引き上げる依頼を受ける。しかし引き上げて鞘から剣を抜いた瞬間、父親は死に、自らは盲目となってしまう。彼はその後、琵琶法師として生きることになる……
このふたりが京で出会い、都の民を(まるでロックミュージシャンのように)熱狂させて行く。しかし。
画面からほとばしる色彩とエネルギーがすばらしい。そして、障がいをもつ二人の少年の人生がシンクロし、意外な展開を見せるストーリーと脚本も。
これ、誰がつくったのかなあ。エンドロールを見てびっくり。
原作は「サウンドトラック」「ベルカ、吠えないのか」の古川日出男であり
脚本は「逃げるは恥だが役に立つ」「重版出来!」「アンナチュラル」などの野木亜紀子で、彼女にとって初のアニメーション作品。
音楽は大友良英。「土を喰らう十二カ月」につづいて二週連続(笑)。
そして監督は「マインド・ゲーム」の湯浅政明。「最も評価されていない天才」という世評は、この作品でくつがえったのではないだろうか。