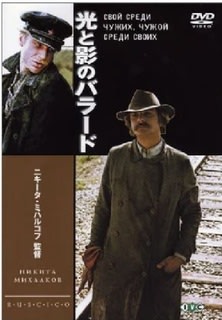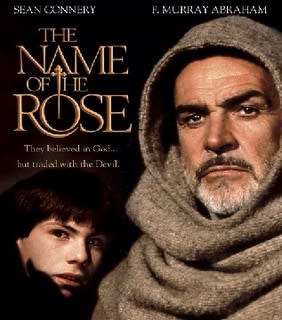(原題:POSSESSOR )本作の興味の対象は、鬼才デイヴィッド・クローネンバーグ監督の息子ブランドンが、演出家としてどれほどのパフォーマンスを見せてくれるかだった。しかしながら、その期待は裏切られた。少なくとも現時点では、彼は父親の足元にも及ばない。そもそも、父の作品群と似たような題材を選んでいることが賢明だとは思えない。もっと別の分野を手掛けた方が良かったのではないだろうか。
殺人請負会社のエージェントであるターシャ・ヴォスは、ターゲットとなる者の近くにいる人間の意識に入り込み、やがてその人物の内面を乗っ取る特殊能力の持ち主だった。乗っ取られた人間はターゲットを殺害し、その後は“宿主”を自殺に追い込んでターシャの人格はそこから“離脱”するというのがルーティンになっている。

今回の殺人請負会社への依頼は、ある富豪の娘婿を乗っ取り、その妻と父親を始末することだったが、任務途中で彼女は“宿主”から抜け出せなくなってしまう。“宿主”の強い自我が、ターシャを圧倒しているのだった。彼女の上司であるガーダーは、事態を収拾すべく思い切った策に出る。
こういうニューロティックなネタは元々デイヴィッド・クローネンバーグが得意としていたのだが、いくら息子のブランドンでも、真の“変態”である父親に容易に対抗できるものではない。全編これデイヴィッド作品の亜流のような、ホラーっぽい場面やスプラッターっぽい場面、あるいはシュールっぽい場面で埋め尽くされているが、どうも描き方が表面的だ。観る者を戦慄せしめるような“狂気”には、最後まで遭遇できなかった。さらに言えば、不自然に画面が暗いのも愉快になれない。
映画はターシャには別居中の夫と息子がいて、そのあたりの葛藤も描き出そうとしているが、取って付けたような印象しかない。そもそも、この“能力”が民間企業に過ぎない暗殺専門会社に帰属しているという設定自体、随分と無理がある。とっくの昔に政府組織の所管になっていてもおかしくない。しかも、暗殺の手口は後先考えない大雑把なもので、これで捜査当局が介入してこないのも噴飯ものだ。
主演のアンドレア・ライズボローをはじめ、クリストファー・アボット、ショーン・ビーン、ジェニファー・ジェイソン・リーといった顔ぶれは悪くはないが、皆何か肩に力が入っているようで印象が薄い。良かったのはジム・ウィリアムズによる音楽ぐらいだ。ブランドン・クローネンバーグ監督は、もっと違う作風を身に着けた方が良いような気がする。
殺人請負会社のエージェントであるターシャ・ヴォスは、ターゲットとなる者の近くにいる人間の意識に入り込み、やがてその人物の内面を乗っ取る特殊能力の持ち主だった。乗っ取られた人間はターゲットを殺害し、その後は“宿主”を自殺に追い込んでターシャの人格はそこから“離脱”するというのがルーティンになっている。

今回の殺人請負会社への依頼は、ある富豪の娘婿を乗っ取り、その妻と父親を始末することだったが、任務途中で彼女は“宿主”から抜け出せなくなってしまう。“宿主”の強い自我が、ターシャを圧倒しているのだった。彼女の上司であるガーダーは、事態を収拾すべく思い切った策に出る。
こういうニューロティックなネタは元々デイヴィッド・クローネンバーグが得意としていたのだが、いくら息子のブランドンでも、真の“変態”である父親に容易に対抗できるものではない。全編これデイヴィッド作品の亜流のような、ホラーっぽい場面やスプラッターっぽい場面、あるいはシュールっぽい場面で埋め尽くされているが、どうも描き方が表面的だ。観る者を戦慄せしめるような“狂気”には、最後まで遭遇できなかった。さらに言えば、不自然に画面が暗いのも愉快になれない。
映画はターシャには別居中の夫と息子がいて、そのあたりの葛藤も描き出そうとしているが、取って付けたような印象しかない。そもそも、この“能力”が民間企業に過ぎない暗殺専門会社に帰属しているという設定自体、随分と無理がある。とっくの昔に政府組織の所管になっていてもおかしくない。しかも、暗殺の手口は後先考えない大雑把なもので、これで捜査当局が介入してこないのも噴飯ものだ。
主演のアンドレア・ライズボローをはじめ、クリストファー・アボット、ショーン・ビーン、ジェニファー・ジェイソン・リーといった顔ぶれは悪くはないが、皆何か肩に力が入っているようで印象が薄い。良かったのはジム・ウィリアムズによる音楽ぐらいだ。ブランドン・クローネンバーグ監督は、もっと違う作風を身に着けた方が良いような気がする。