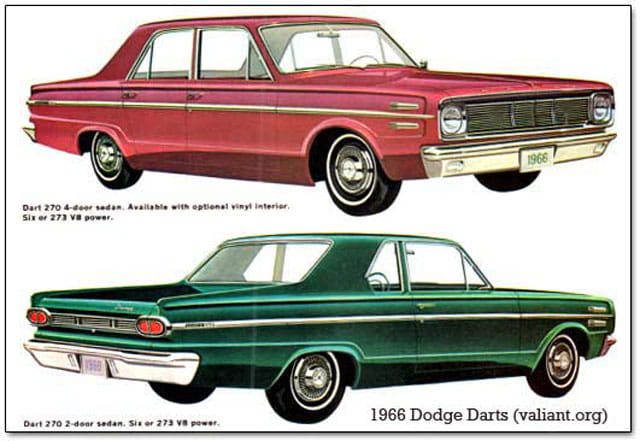年末で忙しく、更新が遅れがちですみません。
月水金でなんとか更新したかったのですが...
で、1週間ぶり!だってのに、こんなクルマで行きます。
まあ、ある意味、このコーナーらしいクルマなんですけどもね(汗
カムリ・グラシアセダン。

カムリとしては、6代め。
もとより北米向けにその性格をシフトしていたカムリは、
この世代で北米での販売が4年連続首位という快挙を達成しました。
ええと、ややこしいんですけど、
このカムリの「北米仕様の」前モデルは、日本名セプターの、カムリになります。
で、日本での「5代めカムリ」は、日本専用の5ナンバーボディ(V40型)、ってことになります。
ああーややこしや。
で、このカムリですが、日本では最初、ペットネームとして
「カムリ・グラシア」という名前を持って、
CMではなぜか西田敏行が「かなりグラシア」って寒めのギャグでワゴンとともに
(さらにややこしいことに、このワゴンがマーク2クオリスというなぜかFFのマーク2の兄弟車)
売ってたのですが(涙)、
マイナーチェンジにともなって、セダンは「カムリ」、ワゴンは「カムリグラシア」
と呼ばれるようになりました。
V8ドロドロエンジンのアメ車も魅力的ですが、こういう何気ない、
実はアメリカでいちばん売れた!というセダンを、
さりげなく、洗車もせず、ゆるゆると乗りこなすのって、このブログで
何度も書いているのでおわかりかと思いますが、憧れるんですよね。
いわゆる、エンジンが小さめい4気筒とかで、FFで、車体でかくて、
車内広い「ドンガラカー」ってやつですね...。
>>そう思うとこの世代のカムリ、まだ上級車上級車してないのでゴテゴテしてないし、
あくまでも大きな大衆車という「ドンガラカーの美学」も備わってるしw、
デザインもなかなか良く出来てるし、
そこはかとない大陸さもあるし、なかなかいいクルマではないか、って思う次第です。。
>>これのダイハツ版...その名はアルティス。いつお目に書かれて、このコーナーを飾れるんだろう(涙
月水金でなんとか更新したかったのですが...
で、1週間ぶり!だってのに、こんなクルマで行きます。
まあ、ある意味、このコーナーらしいクルマなんですけどもね(汗
カムリ・グラシアセダン。

カムリとしては、6代め。
もとより北米向けにその性格をシフトしていたカムリは、
この世代で北米での販売が4年連続首位という快挙を達成しました。
ええと、ややこしいんですけど、
このカムリの「北米仕様の」前モデルは、日本名セプターの、カムリになります。
で、日本での「5代めカムリ」は、日本専用の5ナンバーボディ(V40型)、ってことになります。
ああーややこしや。
で、このカムリですが、日本では最初、ペットネームとして
「カムリ・グラシア」という名前を持って、
CMではなぜか西田敏行が「かなりグラシア」って寒めのギャグでワゴンとともに
(さらにややこしいことに、このワゴンがマーク2クオリスというなぜかFFのマーク2の兄弟車)
売ってたのですが(涙)、
マイナーチェンジにともなって、セダンは「カムリ」、ワゴンは「カムリグラシア」
と呼ばれるようになりました。
V8ドロドロエンジンのアメ車も魅力的ですが、こういう何気ない、
実はアメリカでいちばん売れた!というセダンを、
さりげなく、洗車もせず、ゆるゆると乗りこなすのって、このブログで
何度も書いているのでおわかりかと思いますが、憧れるんですよね。
いわゆる、エンジンが小さめい4気筒とかで、FFで、車体でかくて、
車内広い「ドンガラカー」ってやつですね...。
>>そう思うとこの世代のカムリ、まだ上級車上級車してないのでゴテゴテしてないし、
あくまでも大きな大衆車という「ドンガラカーの美学」も備わってるしw、
デザインもなかなか良く出来てるし、
そこはかとない大陸さもあるし、なかなかいいクルマではないか、って思う次第です。。
>>これのダイハツ版...その名はアルティス。いつお目に書かれて、このコーナーを飾れるんだろう(涙