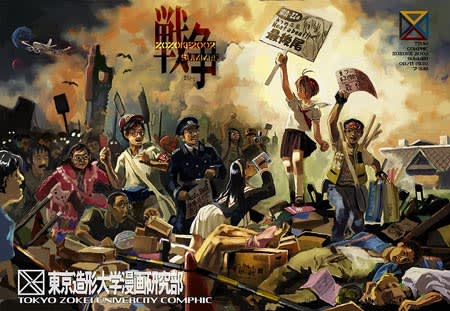これまたちょっと古い話なのですが、
日曜日は「江戸東京博物館」へ行ってきました。
浮世絵の肉筆画展、アラーキーの写真展などもしていたのと、
前々から「江戸時代」好きとしては行かずにはいられない!ところでった行ったのでした。
見所が多かったので、すんごく端折りますが、
ひとことで言うならこの博物館、「模型」がすごい。
なので今日はその模型たちをご紹介。
日本橋たもとの町の様子です。1/30サイズ。

被写界深度が浅いので奥まで見えませんが、一人一人が
まるで動き出しそうな、素晴らしいストーリーを持っています。
立ち話をするもの、橋の下をながめるものなどなど...
これ作った人、スタジオジブリのモブシーン
(群衆の、ひとりひとりに違う動き与える!)が描けますよ(^^

棒手振り(ぼてふり=売り子)がいっぱい。
商家の屋根には「うだつ」が立ち並び、その店の勢いを競っています。
(「うだつがあがらない」という成句は、このうだつから来ています)。

晩年の北斎の家!リアル杉です。

栄華を誇った大店(おおだな)、越後屋呉服店の模型。
軒はカットされていて、店の中が見えるようになっています。
商談、品定め、反物を運ぶ丁稚...みんな生きているようです。

見せ物小屋などが立ち並び、繁華街となっていた両国橋。
その模型です。これまた人がちゃんと「何かをしています」。

川には舟が沢山出ていますね。

今で言う、屋形船のようなものでしょう。
屋根上で風情を楽しむ男衆、屋根の下で宴を楽しむ女たち。
丁寧に、履き物まで脱いでいる様がわかります。
江戸の町では、今よりもきっとゆっくり毎日が過ぎていたのでしょう。
ファッションを楽しみ、見せ物や歌舞伎を楽しみ、初物を待ち、屋台で腹鼓。
季節の移り変わりをビンカンに受け止め、それを上手に暮らしにとけ込ませ、
そしてそれを楽しむ...
やはりこれこそが日本人らしさであり、忘れてはいけないことだと思うのです。
そして、統一された美しい江戸の町...。
すべてが自然のものだけで出来た、でも人口100万人もの人が住んでいた大都市の姿に、
今夜も思いを馳せるのでした。
>>いやはや、圧巻でした。
ちゃんとオペラグラスも用意されているので、町人達の暮らしが楽しめました。
>>おまけ...籠に乗って大名気分♪

それにしても小さい!こんなので何百キロも...大変だったでしょうねえ...。
日曜日は「江戸東京博物館」へ行ってきました。
浮世絵の肉筆画展、アラーキーの写真展などもしていたのと、
前々から「江戸時代」好きとしては行かずにはいられない!ところでった行ったのでした。
見所が多かったので、すんごく端折りますが、
ひとことで言うならこの博物館、「模型」がすごい。
なので今日はその模型たちをご紹介。
日本橋たもとの町の様子です。1/30サイズ。

被写界深度が浅いので奥まで見えませんが、一人一人が
まるで動き出しそうな、素晴らしいストーリーを持っています。
立ち話をするもの、橋の下をながめるものなどなど...
これ作った人、スタジオジブリのモブシーン
(群衆の、ひとりひとりに違う動き与える!)が描けますよ(^^

棒手振り(ぼてふり=売り子)がいっぱい。
商家の屋根には「うだつ」が立ち並び、その店の勢いを競っています。
(「うだつがあがらない」という成句は、このうだつから来ています)。

晩年の北斎の家!リアル杉です。

栄華を誇った大店(おおだな)、越後屋呉服店の模型。
軒はカットされていて、店の中が見えるようになっています。
商談、品定め、反物を運ぶ丁稚...みんな生きているようです。

見せ物小屋などが立ち並び、繁華街となっていた両国橋。
その模型です。これまた人がちゃんと「何かをしています」。

川には舟が沢山出ていますね。

今で言う、屋形船のようなものでしょう。
屋根上で風情を楽しむ男衆、屋根の下で宴を楽しむ女たち。
丁寧に、履き物まで脱いでいる様がわかります。
江戸の町では、今よりもきっとゆっくり毎日が過ぎていたのでしょう。
ファッションを楽しみ、見せ物や歌舞伎を楽しみ、初物を待ち、屋台で腹鼓。
季節の移り変わりをビンカンに受け止め、それを上手に暮らしにとけ込ませ、
そしてそれを楽しむ...
やはりこれこそが日本人らしさであり、忘れてはいけないことだと思うのです。
そして、統一された美しい江戸の町...。
すべてが自然のものだけで出来た、でも人口100万人もの人が住んでいた大都市の姿に、
今夜も思いを馳せるのでした。
>>いやはや、圧巻でした。
ちゃんとオペラグラスも用意されているので、町人達の暮らしが楽しめました。
>>おまけ...籠に乗って大名気分♪

それにしても小さい!こんなので何百キロも...大変だったでしょうねえ...。