今日の昼飯は意外なことに駅弁。かの有名な信越線・横川駅、おぎのや製「峠の釜めし」である。どうしたのかと聞くと、近くのスーパーで「今日午前11時から出張販売」をするという噂を何処かで聞いた同居中の姉が、わざわざ出向いて買ってきたのだという。
東京暮らしが長かった彼女は、東京駅八重洲のデパ地下にある弁当コーナーの常連だったようで、「弁松」の駅弁をよく東京土産にもらったこともある。ひょっとすると「峠の釜めし」も、このデパ地下駅弁めぐりあたりで味わったことがあったのかもしれない。
自分の「峠の釜めし」初体験は今でもしっかりと覚えている。すでに半世紀の昔となった「ケネディ暗殺事件」の起こった日、1963年の11月22日だったからである。
勤労感謝の日の連休を使って、中央線から信越線を乗り継いで東京を目指し、帰りは東海道線を使うという周遊旅行だった。当時の中央西線はまだ電化はされておらず、蒸気機関車のひく3等客車に揺られる旅だったが、信越線の方は電化が進み、その年の9月には碓氷峠のアプト式が廃止されたばかりだった。「釜めし」を食いながら新電化路線を走破しようという「鉄ちゃん」心理で出かけたのである。
アプト式はなくなっても横川停車は結構長い間だったような記憶がある。ホームの売り子から買った「峠の釜めし」が当時いくらだったかは覚えていないが、今日のものは税込で1個900円だ。1000円札一枚でおつり100円というのは、買い手の心理をついた値付けではないか。
益子焼の容器を包むラッピング紙には、「元祖・峠の釜めし」とあるが、ほかにも「本家」や「本元」などと名乗る商売敵がいるのだろうか。「元祖」なのだから、横川駅近くで製造しているのかと思ったら、製造者はおぎのやドライブインの諏訪インター店。なるほど、「駅弁」とは何処にも書いてはいないから、これはドライブインで販売する、いわば「ドラ弁」というわけか。
容器サイズは昔と変わらないが、釉の色が薄くなったような気がする。醤油で甘辛く煮つけた鶏肉、筍、牛蒡、椎茸に、茹でた栗とうずら玉子、さらに、杏の砂糖煮、しょうが酢漬け、グリーンピースが彩りよく盛りこんである。だが具材は昔の方もっと多かったのではなかったか。味付けは今風にあっさり気味の感じだ。シンプルな弁当だが、なつかしい昔の記憶と一緒に食べるせいもあって、なかなかに美味しかった。
1963年の汽車旅行以後、軽井沢周辺は幾度か訪れたが、信越線は使わずにもっぱらドライブばかりだった。信越本線は今も昔のままだとばかり思っていたのだが、今日、改めてWEBで検索すると、1997年の新幹線開業と同時に、横川-軽井沢間を廃止し、軽井沢-篠ノ井間が第三セクターに転換されたとあって少し驚いた。高崎-横川間は、いわば東信越線ということになるわけか。
おぎのやの営業形態が昔の「駅弁」オンリーから「どラ弁」に移り、さらに行商スタイルで我が町にも出張してくるのも、こうした時の流れと旅のスタイルの変化に適応したものなわけだ。
ところで、名古屋B級グルメの代表格の「ひつまぶし」だが、「櫃」ではなく「釜」で出してくる店もあれば、名古屋コーチンをつかった「とりめし」も「釜」スタイルのものがあったりで、名古屋には結構な数で「釜めし」を商売にする店が多いのは、なぜなのだろうか。
駅弁で売られている「釜飯」を調べてみても、どうやら日本の中央部に遍在していそうなのである。例えば、浜松のうなぎ釜めし(加熱プラ容器)、小淵沢のとり釜めし(陶製容器)、中津川の木曽路釜めし(プラ容器)、美濃太田の松茸釜めし(プラ容器)、飯田の山菜釜めし(プラ容器・車内販売)などが見つかる。容器は昔とちがって製造加工も廃棄処理もしやすいプラスチック成型の器が多くなったようだ。
おぎのやの商標「元祖」とは、今でも昔ながらの陶製の釜を使っているという意味もあるのかもしれない。包装ラベルには、「この容器は一合のご飯が炊けます」と書かれている。机に置いて何かの入れ物に使えそうだから捨てずに残しておくことにした。紅葉に色づく信越線の車窓風景を思い出すきっかけにもなりそうだ。
ごちそうさまでした。
東京暮らしが長かった彼女は、東京駅八重洲のデパ地下にある弁当コーナーの常連だったようで、「弁松」の駅弁をよく東京土産にもらったこともある。ひょっとすると「峠の釜めし」も、このデパ地下駅弁めぐりあたりで味わったことがあったのかもしれない。
自分の「峠の釜めし」初体験は今でもしっかりと覚えている。すでに半世紀の昔となった「ケネディ暗殺事件」の起こった日、1963年の11月22日だったからである。
勤労感謝の日の連休を使って、中央線から信越線を乗り継いで東京を目指し、帰りは東海道線を使うという周遊旅行だった。当時の中央西線はまだ電化はされておらず、蒸気機関車のひく3等客車に揺られる旅だったが、信越線の方は電化が進み、その年の9月には碓氷峠のアプト式が廃止されたばかりだった。「釜めし」を食いながら新電化路線を走破しようという「鉄ちゃん」心理で出かけたのである。
アプト式はなくなっても横川停車は結構長い間だったような記憶がある。ホームの売り子から買った「峠の釜めし」が当時いくらだったかは覚えていないが、今日のものは税込で1個900円だ。1000円札一枚でおつり100円というのは、買い手の心理をついた値付けではないか。
益子焼の容器を包むラッピング紙には、「元祖・峠の釜めし」とあるが、ほかにも「本家」や「本元」などと名乗る商売敵がいるのだろうか。「元祖」なのだから、横川駅近くで製造しているのかと思ったら、製造者はおぎのやドライブインの諏訪インター店。なるほど、「駅弁」とは何処にも書いてはいないから、これはドライブインで販売する、いわば「ドラ弁」というわけか。
容器サイズは昔と変わらないが、釉の色が薄くなったような気がする。醤油で甘辛く煮つけた鶏肉、筍、牛蒡、椎茸に、茹でた栗とうずら玉子、さらに、杏の砂糖煮、しょうが酢漬け、グリーンピースが彩りよく盛りこんである。だが具材は昔の方もっと多かったのではなかったか。味付けは今風にあっさり気味の感じだ。シンプルな弁当だが、なつかしい昔の記憶と一緒に食べるせいもあって、なかなかに美味しかった。
1963年の汽車旅行以後、軽井沢周辺は幾度か訪れたが、信越線は使わずにもっぱらドライブばかりだった。信越本線は今も昔のままだとばかり思っていたのだが、今日、改めてWEBで検索すると、1997年の新幹線開業と同時に、横川-軽井沢間を廃止し、軽井沢-篠ノ井間が第三セクターに転換されたとあって少し驚いた。高崎-横川間は、いわば東信越線ということになるわけか。
おぎのやの営業形態が昔の「駅弁」オンリーから「どラ弁」に移り、さらに行商スタイルで我が町にも出張してくるのも、こうした時の流れと旅のスタイルの変化に適応したものなわけだ。
ところで、名古屋B級グルメの代表格の「ひつまぶし」だが、「櫃」ではなく「釜」で出してくる店もあれば、名古屋コーチンをつかった「とりめし」も「釜」スタイルのものがあったりで、名古屋には結構な数で「釜めし」を商売にする店が多いのは、なぜなのだろうか。
駅弁で売られている「釜飯」を調べてみても、どうやら日本の中央部に遍在していそうなのである。例えば、浜松のうなぎ釜めし(加熱プラ容器)、小淵沢のとり釜めし(陶製容器)、中津川の木曽路釜めし(プラ容器)、美濃太田の松茸釜めし(プラ容器)、飯田の山菜釜めし(プラ容器・車内販売)などが見つかる。容器は昔とちがって製造加工も廃棄処理もしやすいプラスチック成型の器が多くなったようだ。
おぎのやの商標「元祖」とは、今でも昔ながらの陶製の釜を使っているという意味もあるのかもしれない。包装ラベルには、「この容器は一合のご飯が炊けます」と書かれている。机に置いて何かの入れ物に使えそうだから捨てずに残しておくことにした。紅葉に色づく信越線の車窓風景を思い出すきっかけにもなりそうだ。
ごちそうさまでした。











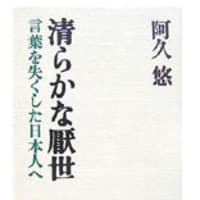






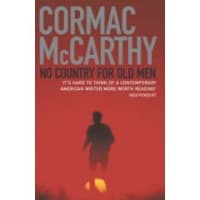
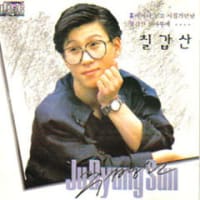
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます