「大根干済めば忽ち恵比寿講」
山口青邨の秋の句、季語はえびす講である。
ウイキによると、神無月(旧暦十月)に出雲に赴かない留守神とされたえびす神を祀って、十月二十日または十一月二十日に催される祭礼または民間行事。一年の無事を感謝し、五穀豊穣、大漁、あるいは商売繁盛を祈願するとある。
「ことばの歳時記」で金田一春彦先生は、エビスは漁神、農神、商神として幅広く信仰されている福の神。昔、江戸の商家では、エビスの像を掛けた前で、店の者たちが売り方と買い方に別れて、店の品物を売り買いする真似をした。千両万両という高い値をつけて「売りましょう」「買いましょう」と手締めをして祝った。そのハナシから、ありそうにない儲け話のことを「エビス講のもうけばなし」というと書いている。
金田一先生は、エビスに因んだエピソードとして、七福神の名を貰った福神漬のことにも触れている。
いろいろあるという福神漬の名前の由来では、ウイキにもある、「明治時代初頭、上野の漬物店・山田屋(現在の酒悦)の店主野田清右衛門が開発し販売したものが評判となり全国に広まった。名付親は、これを大いに気に入った流行作家の梅亭金鵞で、「これさえあれば他に菜は要らず、食費が抑えられ金が貯まる」と、まるで家に七福神がやってきたかのような幸福感だという解釈で、材料が七種類だったことと、店が不忍池の弁才天近くにあった事から「福神漬」と命名したとされる」という説を採っている。
七種の材料として、ダイコン、ナス、ナタマメ、シロウリ、レンコン、ショウガ、シソの実が挙げられているが、エビスに擬えられたのはいったいどの野菜なのか、ウイキも金田一先生もこの点は教えてくれていない。
エビス講は全国各地で行われているようだが、名古屋の熱田神宮では〈熱田恵比須講社大祭〉として摂社の上知我麻神社で十月二十日に行われるとある。講員は千二百名を数えるというから大きな組織である。今年は天皇即位礼を2日後に控えた開催だから参加者もきっと多かったことだろう。
最後に寺田寅彦のちょっと可笑しい句をひとつ。
「盗人の厨に入るや恵比寿講」
最新の画像[もっと見る]











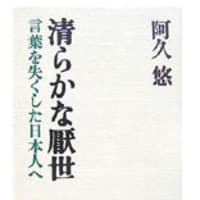






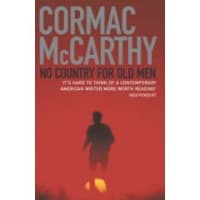
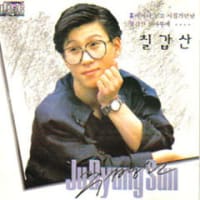
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます