愛知県発表の11月11日分ゴロナ感染確認者は104人で、10日の129人に続き2日連続で100人超えだ。名古屋市52人、岡崎市8人、豊田市6人、他市町村38人である。
「丹精の菊みよと垣つくろはず」
久保田万太郎はこう詠ったが、最近は路地に入っても昔のように丹精した菊の花をみる機会がずいぶんへった。それでも菊の愛好家はけっこういるようだ。
昨日の中日新聞には、知多半島阿久比の菊花連合会が各地区で育てた菊を展示中だと出ている。展示された手作りの菊は九種、約二百五十点。恒例の「菊花展」に向け育ててきたものだが、コロナで中止になった代りに、町役場で展示することになったらしい。記事横の写真を見ると「大輪や小花、鮮やか250点」という見出しの通り、見事な「作品」ばかりだ。
「季語集」の坪内稔典先生は「菊」の項に、こんな面白いエピソードを載せている。
評論家の桑原武夫が、昭和21年の「第二芸術」という評論の中で「菊作りを芸術とは言わないように、俳句もまた芸術ではない。しいて芸術と言いたければ第二芸術と言うべきだ」と書いた。俳句は菊作りと同じだと断定したわけで、これには当時の俳人たちが強く反発したのだそうだ。
現代俳人の坪内先生としても、こう指摘れてはイイ気はしなかろう。菊づくりを褒めることで桑原に反論を試みている。
曰く「今になって思えば、菊作りもすごい。花が咲く僅かな期間のために知恵や技術や情熱の一切を注ぐのだから。菊作りは芸術という無償の行為そのものだと言ってよい」
菊作りが芸術ならば菊作りのようだという俳句も芸術に違いなかろうと言うわけである。
しかし自分としては、日本伝統の職人芸的なこだわりが菊作りの真骨頂であって、どこかスノッブな響きのある芸術だとは断定しきれない。俳句も同じで、和歌のスノッブとは対極にある庶民の想いや視点を詠うものではないのかと、桑原に賛同したい気持ちもあるのだが、まあ、どちらでもよかろう。坪内先生が載せた五十嵐播水のこの句で終わろう。
「道の上に菊の鉢置き立話」











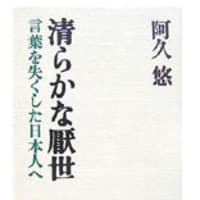






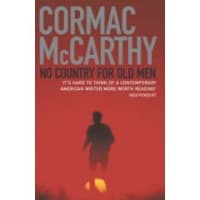
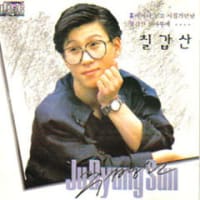
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます