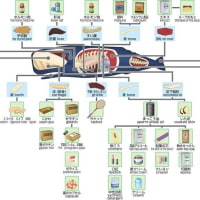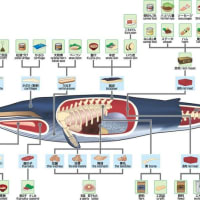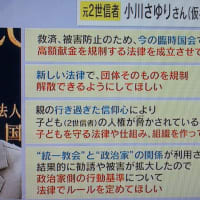5月5日(木):
「昔から地位にある者が学んでいないほど国家を病気にするものはない。害になるものはない。(保科正之)」
朝日デジタル:(憲法を考える)9条、立憲主義のピース 寄稿、憲法学者・石川健治 2016年5月3日05時00分
1916年元旦、大阪朝日新聞の第1面に掲載されたのが、戦前を代表する憲法学者・佐々木惣一の論説「立憲非立憲」であった。同論文は、1回の休載を挟み、18回連続で1面に掲載された。同じ頃、彼の親友・吉野作造は、「民本主義」を提起した記念碑的論文を発表している(「中央公論」16年1月号)。それから1世紀の記念すべき年の晩秋に、私たちは日本国憲法公布70周年を迎えることになる。にもかかわらず、立憲主義の定着を祝うべきこのときに、〈立憲・対・非立憲〉が再び対立軸となっているのである。
改憲を唱える人たちは、憲法を軽視するスタイルが身についている。加えて、本来まともだったはずの論者からも、いかにも「軽い」改憲発言が繰り出される傾向も目立つ。実際には全く論点にもなっていない、9条削除論を提唱してかきまわしてみたりするのは、その一例である。日本で憲法論の空間を生きるのは、もっと容易ならぬことだったはずである。
ここでは、逆に「重さ」を感じさせる一例として、77年に出された一つの最高裁判決をひもといてみたい。当時の長官は藤林益三。元々彼は、佐藤栄作内閣が最高裁を保守化させようと躍起になっていた時期、切り札として送り込まれた企業法務専門の弁護士だ。実際、リベラルな判決が相次いでいた公務員の労働基本権の判例の流れを「反動」化させるのに大きな勲功をあげた。その彼が定年退官直前に担当したのが津地鎮祭事件であった。津市が体育館の起工にあたり地鎮祭費用として公金から8千円弱の支出をし、憲法の政教分離原則に違反するとして争われた事件で、最高裁の多数派は「合憲」の結論になった。
しかし、この事件を「法律家人生をかけてとりくんだ」とのちに振り返る藤林は、裁判長ながら「違憲」の反対意見に回る。しかも、「違憲」派5人の共通の反対意見に加えて、さらに1人で追加反対意見を書いた。藤林が明記して断っているように、追加反対意見の前半は、内村鑑三が創始した無教会主義のキリスト者・矢内原忠雄の文章を、ほぼ一字一句「写経」することで成立している。
矢内原は、戦前、東京帝大における「植民政策」の講座担当者として、日本の植民地主義に加担するという葛藤を抱えながら、雑誌などでの政府批判を理由に、37年には辞職に追い込まれた反骨の人である(矢内原事件)。藤林が引用したのは、矢内原が戦後に書いた「近代日本における宗教と民主主義」。言論弾圧に直面して日本社会と丸腰で向き合った経験をもつからこその、迫力ある文章だ。
■ ■
矢内原は、戦後における「公」の再編過程を振り返る。第1段階は、終戦後も治安維持法によって投獄されたままだった哲学者・三木清の獄死という悲劇をきっかけに、連合国軍総司令部(GHQ)が45年10月に出した「自由の指令」だ。これにより、「私」の領域における思想の自由と、一般私人の政権批判の自由を回復した。
35年の天皇機関説事件以前は、神道式の儀礼と皇室の祭祀(さいし)によって演出された「公」と、「私」の領域における思想・信仰とは、どうにかこうにか切り分けられていた。それを支えていたのが、佐々木や美濃部達吉ら立憲主義学派の憲法学であった。とりわけ、国家を法学的に叙述する文法を堅持した美濃部の天皇機関説の冷静さが、公私の境界線の論理的な支えになっていた。
ところが、「事件」によって立憲主義憲法学が葬り去られ、機関説支持だった政府は、2度にわたる国体明徴声明を余儀なくされた。境界線は決壊し、「国体の本義」が「私」の世界にとめどなく浸入した。この境界線を「自由の指令」は回復したのであった。その延長線上に、集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障する、現憲法21条はある。
第2段階は、GHQが12月に出した「神道指令」であり、信教の自由を保障するとともに、国家神道を政治社会から切り離した。そして、矢継ぎ早の第3段階は、翌46年元旦に出された、天皇のいわゆる人間宣言である。それぞれ、現憲法20条、89条の政教分離原則と第1章の象徴天皇制に引き継がれた。矢内原は、日本の政治社会を、かつて「国体」色に染め上げるために活用された演出装置が、二つとも外された点に注意を喚起する。これらによって、ただ単に「公」と「私」の境界線が確保されたのみならず、「公」それ自体の無色透明化が図られた。これで、立憲主義が想定する政治社会は、ひとまず完成である。
■ ■
藤林長官は、ここで引用を止める。しかし、読ませたかったのはその先であろう。そのためにこそ、出典を明示しつつ、あえて他人の文章を「写経」する、という異例の手段を採ったに相違ない。引用されなかった部分。そこに書かれていたのは、矢内原にとって宿命的な論点だった、植民地主義と軍国主義の論点である。彼の理解によれば、自由の指令も神道指令も人間宣言も、植民地主義と軍国主義の過去を清算するためのプロセスであったのであり、これにとどめを刺したのが憲法9条であることは、いうまでもない。
ここから明らかになるのは、9条がまず何よりも、長らく軍国主義に浸(つ)かってきた日本の政治社会を、いったん徹底的に非軍事化するための規定である、という消息である。それにより、「公共」の改造実験はひとまず完成し、この「公」と「私」の枠組みに支えられる形で、日本の立憲主義ははじめて安定軌道にのることができた。結果オーライであるにせよ、70年間の日本戦後史は、サクセスストーリーだったといってよい。
しかし、こうした段階を踏むことで、かつて軍国主義を演出した何系統かの言説が公共空間から排除され、出入り禁止の扱いになった。もちろん憲法尊重擁護義務は「公共」「公職」にのみ向けられており、国民には強制されていない。それらの言説は、私の世界においては完全な自由を享受できる。けれども「戦後改革」から日本国憲法に受け継がれた諸条文がいわば「結界」として作用して、立憲主義にとって危険だとみなされる一連の言説を、私の領域に封じ込め続けているのは事実だ。
その意味で、封じ込められた側からいえば、日本国憲法が敵視と憎悪の対象になるのは、自然であるといえる。きわめて乱暴にいってしまえば、日本国憲法という一個の戦後的なプロジェクトには、少なくとも政治社会から軍国主義の毒気が抜けるまで、そうした「結界」を維持することで立憲主義を定着させる、という内容が含まれているのである。
■ ■
ところが、私の領域に封じ込まれていたはずの一連の言説が、ネット空間という新しい媒体を通じて、公の世界に還流し始めた。それに初めてふれて新鮮な印象を抱く人が、比較的若い世代に増えてきたようである。これを原動力にして、この際「結界」を壊してしまおうと考えている勢力もある。戦後、対外的危機は、実は一度ならずあったはずなのであるが、最近の北東アジアにおける安全保障環境の変化を前面に押し出して、「新鮮」な危機感に訴える傾向も顕著である。
こういう流れのなかで9条を動かすのは、危険きわまりないといわなくてはならない。日本の立憲主義を支える結界において、憲法9条が重要なピースをなしてきた、という事実を見逃すべきではないのである。もちろん、9条は、どんな国でも立憲主義のための標準装備である、という性質のものではない。しかし、こと戦後日本のそれに関する限り、文字通り抜き差しならないピースをなしているのであり、このピースを外すことで、立憲主義を支える構造物がガラガラと崩壊しないかどうかを、考えることが大切である。
それにしては、あまりにも無造作な9条論が、目立つ。9条は、とかく安全保障の局面だけで手軽に語られるが、決してそれだけの条文ではない。ただ、その一方で、世論調査による限り、9条改正は危険ではないかという直観が、おそらくは皮膚感覚のレベルで広がりつつあるのも事実である。すでに述べたように、この直観には根拠がある。私たちが生命・自由・幸福を追求する枠組み全体を支える9条をもっと慎重に扱うことが、国家の安全保障を論ずる前提条件になっている。
ただし、ここには、一つの問題がある。新しい結界のもとで再編された「公共」は、立憲主義が想定する「無色透明」なそれであるが、そうした「公共」に対して、国民の情熱や献身を調達することは難しい。ありていにいえば、そうした無色透明なものに対して命は懸けられないのである。この点は立憲主義の、それ自体としてのアピール力の弱さを示している。
この点、矢内原は、政教分離原則は「国家の宗教に対する冷淡の標識」ではなく「宗教尊重の結果」であることを強調し、むしろ「国家は宗教による精神的、観念的な基礎を持たなければ維持できない」ことを強調した。当然ながら、最もふさわしいのはキリスト教、というのが矢内原の立場だ。近代立憲主義国家は、実はキリスト教による精神的基礎なしには成り立たないという。実は藤林も無教会主義の敬虔(けいけん)な信者であった。
欧米の憲法史にそっていえば、矢内原らの見方は、かなりあたっている。しかし、少なくとも理論上は、「公共」はあらゆる世界観に対して中立的でなくてはならない。この点において、他のリベラル派判事4人は、藤林と袂(たもと)を分かつことになった。彼らにとって、公共をキリスト教の信仰で色づけることには、賛成できなかった。
こうした文脈で注意されるのが、第1次安倍政権の教育基本法改正による「愛国心」教育の強調である。国を愛するというのは自然な感情であり、否定のしようがない。しかし、それを国家が強要するのはまた別の話であって、ある特定の価値によって、しかも命を懸けるに値する公を染め上げようというのであれば、それは日本の立憲主義にとって致命傷になる。現代版「立憲非立憲」の戦線は、ここにもあるのである。
*
いしかわけんじ 1962年生まれ。東大教授。編著に「学問/政治/憲法 連環と緊張」など。「立憲デモクラシーの会」呼びかけ人の1人。
「昔から地位にある者が学んでいないほど国家を病気にするものはない。害になるものはない。(保科正之)」
朝日デジタル:(憲法を考える)9条、立憲主義のピース 寄稿、憲法学者・石川健治 2016年5月3日05時00分
1916年元旦、大阪朝日新聞の第1面に掲載されたのが、戦前を代表する憲法学者・佐々木惣一の論説「立憲非立憲」であった。同論文は、1回の休載を挟み、18回連続で1面に掲載された。同じ頃、彼の親友・吉野作造は、「民本主義」を提起した記念碑的論文を発表している(「中央公論」16年1月号)。それから1世紀の記念すべき年の晩秋に、私たちは日本国憲法公布70周年を迎えることになる。にもかかわらず、立憲主義の定着を祝うべきこのときに、〈立憲・対・非立憲〉が再び対立軸となっているのである。
改憲を唱える人たちは、憲法を軽視するスタイルが身についている。加えて、本来まともだったはずの論者からも、いかにも「軽い」改憲発言が繰り出される傾向も目立つ。実際には全く論点にもなっていない、9条削除論を提唱してかきまわしてみたりするのは、その一例である。日本で憲法論の空間を生きるのは、もっと容易ならぬことだったはずである。
ここでは、逆に「重さ」を感じさせる一例として、77年に出された一つの最高裁判決をひもといてみたい。当時の長官は藤林益三。元々彼は、佐藤栄作内閣が最高裁を保守化させようと躍起になっていた時期、切り札として送り込まれた企業法務専門の弁護士だ。実際、リベラルな判決が相次いでいた公務員の労働基本権の判例の流れを「反動」化させるのに大きな勲功をあげた。その彼が定年退官直前に担当したのが津地鎮祭事件であった。津市が体育館の起工にあたり地鎮祭費用として公金から8千円弱の支出をし、憲法の政教分離原則に違反するとして争われた事件で、最高裁の多数派は「合憲」の結論になった。
しかし、この事件を「法律家人生をかけてとりくんだ」とのちに振り返る藤林は、裁判長ながら「違憲」の反対意見に回る。しかも、「違憲」派5人の共通の反対意見に加えて、さらに1人で追加反対意見を書いた。藤林が明記して断っているように、追加反対意見の前半は、内村鑑三が創始した無教会主義のキリスト者・矢内原忠雄の文章を、ほぼ一字一句「写経」することで成立している。
矢内原は、戦前、東京帝大における「植民政策」の講座担当者として、日本の植民地主義に加担するという葛藤を抱えながら、雑誌などでの政府批判を理由に、37年には辞職に追い込まれた反骨の人である(矢内原事件)。藤林が引用したのは、矢内原が戦後に書いた「近代日本における宗教と民主主義」。言論弾圧に直面して日本社会と丸腰で向き合った経験をもつからこその、迫力ある文章だ。
■ ■
矢内原は、戦後における「公」の再編過程を振り返る。第1段階は、終戦後も治安維持法によって投獄されたままだった哲学者・三木清の獄死という悲劇をきっかけに、連合国軍総司令部(GHQ)が45年10月に出した「自由の指令」だ。これにより、「私」の領域における思想の自由と、一般私人の政権批判の自由を回復した。
35年の天皇機関説事件以前は、神道式の儀礼と皇室の祭祀(さいし)によって演出された「公」と、「私」の領域における思想・信仰とは、どうにかこうにか切り分けられていた。それを支えていたのが、佐々木や美濃部達吉ら立憲主義学派の憲法学であった。とりわけ、国家を法学的に叙述する文法を堅持した美濃部の天皇機関説の冷静さが、公私の境界線の論理的な支えになっていた。
ところが、「事件」によって立憲主義憲法学が葬り去られ、機関説支持だった政府は、2度にわたる国体明徴声明を余儀なくされた。境界線は決壊し、「国体の本義」が「私」の世界にとめどなく浸入した。この境界線を「自由の指令」は回復したのであった。その延長線上に、集会・結社・言論・出版その他一切の表現の自由を保障する、現憲法21条はある。
第2段階は、GHQが12月に出した「神道指令」であり、信教の自由を保障するとともに、国家神道を政治社会から切り離した。そして、矢継ぎ早の第3段階は、翌46年元旦に出された、天皇のいわゆる人間宣言である。それぞれ、現憲法20条、89条の政教分離原則と第1章の象徴天皇制に引き継がれた。矢内原は、日本の政治社会を、かつて「国体」色に染め上げるために活用された演出装置が、二つとも外された点に注意を喚起する。これらによって、ただ単に「公」と「私」の境界線が確保されたのみならず、「公」それ自体の無色透明化が図られた。これで、立憲主義が想定する政治社会は、ひとまず完成である。
■ ■
藤林長官は、ここで引用を止める。しかし、読ませたかったのはその先であろう。そのためにこそ、出典を明示しつつ、あえて他人の文章を「写経」する、という異例の手段を採ったに相違ない。引用されなかった部分。そこに書かれていたのは、矢内原にとって宿命的な論点だった、植民地主義と軍国主義の論点である。彼の理解によれば、自由の指令も神道指令も人間宣言も、植民地主義と軍国主義の過去を清算するためのプロセスであったのであり、これにとどめを刺したのが憲法9条であることは、いうまでもない。
ここから明らかになるのは、9条がまず何よりも、長らく軍国主義に浸(つ)かってきた日本の政治社会を、いったん徹底的に非軍事化するための規定である、という消息である。それにより、「公共」の改造実験はひとまず完成し、この「公」と「私」の枠組みに支えられる形で、日本の立憲主義ははじめて安定軌道にのることができた。結果オーライであるにせよ、70年間の日本戦後史は、サクセスストーリーだったといってよい。
しかし、こうした段階を踏むことで、かつて軍国主義を演出した何系統かの言説が公共空間から排除され、出入り禁止の扱いになった。もちろん憲法尊重擁護義務は「公共」「公職」にのみ向けられており、国民には強制されていない。それらの言説は、私の世界においては完全な自由を享受できる。けれども「戦後改革」から日本国憲法に受け継がれた諸条文がいわば「結界」として作用して、立憲主義にとって危険だとみなされる一連の言説を、私の領域に封じ込め続けているのは事実だ。
その意味で、封じ込められた側からいえば、日本国憲法が敵視と憎悪の対象になるのは、自然であるといえる。きわめて乱暴にいってしまえば、日本国憲法という一個の戦後的なプロジェクトには、少なくとも政治社会から軍国主義の毒気が抜けるまで、そうした「結界」を維持することで立憲主義を定着させる、という内容が含まれているのである。
■ ■
ところが、私の領域に封じ込まれていたはずの一連の言説が、ネット空間という新しい媒体を通じて、公の世界に還流し始めた。それに初めてふれて新鮮な印象を抱く人が、比較的若い世代に増えてきたようである。これを原動力にして、この際「結界」を壊してしまおうと考えている勢力もある。戦後、対外的危機は、実は一度ならずあったはずなのであるが、最近の北東アジアにおける安全保障環境の変化を前面に押し出して、「新鮮」な危機感に訴える傾向も顕著である。
こういう流れのなかで9条を動かすのは、危険きわまりないといわなくてはならない。日本の立憲主義を支える結界において、憲法9条が重要なピースをなしてきた、という事実を見逃すべきではないのである。もちろん、9条は、どんな国でも立憲主義のための標準装備である、という性質のものではない。しかし、こと戦後日本のそれに関する限り、文字通り抜き差しならないピースをなしているのであり、このピースを外すことで、立憲主義を支える構造物がガラガラと崩壊しないかどうかを、考えることが大切である。
それにしては、あまりにも無造作な9条論が、目立つ。9条は、とかく安全保障の局面だけで手軽に語られるが、決してそれだけの条文ではない。ただ、その一方で、世論調査による限り、9条改正は危険ではないかという直観が、おそらくは皮膚感覚のレベルで広がりつつあるのも事実である。すでに述べたように、この直観には根拠がある。私たちが生命・自由・幸福を追求する枠組み全体を支える9条をもっと慎重に扱うことが、国家の安全保障を論ずる前提条件になっている。
ただし、ここには、一つの問題がある。新しい結界のもとで再編された「公共」は、立憲主義が想定する「無色透明」なそれであるが、そうした「公共」に対して、国民の情熱や献身を調達することは難しい。ありていにいえば、そうした無色透明なものに対して命は懸けられないのである。この点は立憲主義の、それ自体としてのアピール力の弱さを示している。
この点、矢内原は、政教分離原則は「国家の宗教に対する冷淡の標識」ではなく「宗教尊重の結果」であることを強調し、むしろ「国家は宗教による精神的、観念的な基礎を持たなければ維持できない」ことを強調した。当然ながら、最もふさわしいのはキリスト教、というのが矢内原の立場だ。近代立憲主義国家は、実はキリスト教による精神的基礎なしには成り立たないという。実は藤林も無教会主義の敬虔(けいけん)な信者であった。
欧米の憲法史にそっていえば、矢内原らの見方は、かなりあたっている。しかし、少なくとも理論上は、「公共」はあらゆる世界観に対して中立的でなくてはならない。この点において、他のリベラル派判事4人は、藤林と袂(たもと)を分かつことになった。彼らにとって、公共をキリスト教の信仰で色づけることには、賛成できなかった。
こうした文脈で注意されるのが、第1次安倍政権の教育基本法改正による「愛国心」教育の強調である。国を愛するというのは自然な感情であり、否定のしようがない。しかし、それを国家が強要するのはまた別の話であって、ある特定の価値によって、しかも命を懸けるに値する公を染め上げようというのであれば、それは日本の立憲主義にとって致命傷になる。現代版「立憲非立憲」の戦線は、ここにもあるのである。
*
いしかわけんじ 1962年生まれ。東大教授。編著に「学問/政治/憲法 連環と緊張」など。「立憲デモクラシーの会」呼びかけ人の1人。