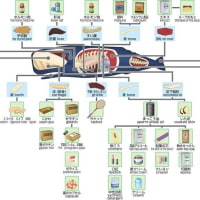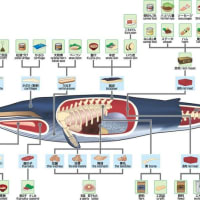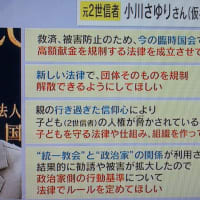9月2日(日): 





朝日デジタル:(日曜に想う)翁長知事の言葉のゆくえ 編集委員・福島申二 2018年9月2日05時00分
8月8日、二つの原爆の日にはさまれるように沖縄県の翁長雄志知事が不帰の人となった。全国紙5紙のうち日経を除くすべてが1面トップで伝えた(東京紙面)。一知事の死去としては異例の報道が沖縄の置かれた今を物語る。
〈八月や六日九日十五日〉
これは、多くの市井の人に詠まれてきた「詠み人多数」の俳句である。並ぶ日付が戦争の記憶のふたをあけ、祈りと誓いをよびさます。それらに6月23日の沖縄慰霊の日を加えた四つの日を、天皇陛下は「どうしても記憶しなければならないこと」として挙げている。
多くの日本人にとって、陛下の思いは胸に落ちるものだろう。今年も四つの日に式典があり、それぞれテレビで中継された。いずれも安倍晋三首相の姿があった。しかし沖縄で、広島で、長崎で、どこか義務的に参列している印象を受けたのは筆者だけではなかったと思う。
スピーチもしかりである。翁長氏や広島、長崎両市長の言葉はよく練られ、聞く人をうなずかせるものだった。それらに比して、常套句(じょうとうく)の組み合わせを聞かされた感は否めなかった。
〈原爆を知れるは広島と長崎にて日本といふ国にはあらず〉
長崎で被爆し8年前に90歳で亡くなった歌人竹山広さんの最晩年の一首を、首相のスピーチから思い出した。「沖縄を知れるは沖縄のみにて……」と変奏すれば沖縄にもあてはまる一首である。
*
ヤマトに向けた厳しい言葉を、幾つも翁長知事は残していった。
「沖縄が日本に甘えているのか、日本が沖縄に甘えているのか」(この言葉は事あるごとに繰り返された)
「総理が『日本を取り戻す』と言っていた。取り戻す日本の中に沖縄は入っているのか」(菅義偉官房長官に)
「普天間は危険だから大変だとなって、その危険性除去のために沖縄が負担しろ、と。こういう話がされること自体が日本の政治の堕落ではないか」(同)
「歴史的にも現在においても、沖縄県民は自由、平等、人権、自己決定権をないがしろにされてきた。私はこれを『魂の飢餓感』と表現している」(国と争う辺野古訴訟の陳述で)
ほかにも多々あり、言葉でたたかう人だったことがわかる。しかし腹の底から絞り出したであろう声が政府に届いた様子はない。安倍首相は二言目には「沖縄の気持ちに寄り添って」と、実際から程遠い美辞を単調に繰り返してきた。
「言葉の発し手と、受け手とが、ぴたり切りむすんだ時、初めて言葉が成立する」と言ったのは、詩人の茨木のり子さんである。続けて「全身の重味を賭けて言葉を発したところで、受け手がぼんくらでは、不発に終り流れてゆくのみである」と。政権が翁長氏の言葉と切り結ぶことはなかった。沖縄の民意をのせた重い言葉は、一強政権の驕慢(きょうまん)に問答無用の体で跳ね返されたままである。
*
沖縄は本土復帰からの46年を7人の知事でつないできた。8人目を決める選挙が今月30日にある。
国と協調するのか、対峙(たいじ)するのか。そんな選択を知事選挙で問われ続けてきた都道府県は沖縄をおいてない。政府は時の知事の姿勢をみて、振興費の蛇口を開いたり絞ったりした。大田昌秀知事の時代には政府との関係が冷え切って「県政不況」という言葉さえ生まれた。
一人ひとりに暮らしがある。それと同時に、沖縄はこうあってほしいという基地の島ゆえの思いがある。選挙は、そのはざまでの決心をそれぞれに迫る。その過程での地域や職場、ときには親戚や家族まで巻き込んでの分断や確執が、これまでも人々を苦しめてきた。
沖縄の人口は全国の1%しかない。その沖縄に「魂の飢餓感」を押しつけたまま、それすら忘れたように99%が安らぐ図は異様である。翁長氏が2年前、報道機関との懇親会で「政権の何が一番だめなのか」と聞かれ、「愛がない」と答えたという話が、いま胸にこたえる。
言葉は私たちに投げられたのだ。「ぼんくらな受け手」でありたくはない。
※沖縄ときちんと向き合った野中広務師のことが本当に偲ばれる(もみ)。







朝日デジタル:(日曜に想う)翁長知事の言葉のゆくえ 編集委員・福島申二 2018年9月2日05時00分
8月8日、二つの原爆の日にはさまれるように沖縄県の翁長雄志知事が不帰の人となった。全国紙5紙のうち日経を除くすべてが1面トップで伝えた(東京紙面)。一知事の死去としては異例の報道が沖縄の置かれた今を物語る。
〈八月や六日九日十五日〉
これは、多くの市井の人に詠まれてきた「詠み人多数」の俳句である。並ぶ日付が戦争の記憶のふたをあけ、祈りと誓いをよびさます。それらに6月23日の沖縄慰霊の日を加えた四つの日を、天皇陛下は「どうしても記憶しなければならないこと」として挙げている。
多くの日本人にとって、陛下の思いは胸に落ちるものだろう。今年も四つの日に式典があり、それぞれテレビで中継された。いずれも安倍晋三首相の姿があった。しかし沖縄で、広島で、長崎で、どこか義務的に参列している印象を受けたのは筆者だけではなかったと思う。
スピーチもしかりである。翁長氏や広島、長崎両市長の言葉はよく練られ、聞く人をうなずかせるものだった。それらに比して、常套句(じょうとうく)の組み合わせを聞かされた感は否めなかった。
〈原爆を知れるは広島と長崎にて日本といふ国にはあらず〉
長崎で被爆し8年前に90歳で亡くなった歌人竹山広さんの最晩年の一首を、首相のスピーチから思い出した。「沖縄を知れるは沖縄のみにて……」と変奏すれば沖縄にもあてはまる一首である。
*
ヤマトに向けた厳しい言葉を、幾つも翁長知事は残していった。
「沖縄が日本に甘えているのか、日本が沖縄に甘えているのか」(この言葉は事あるごとに繰り返された)
「総理が『日本を取り戻す』と言っていた。取り戻す日本の中に沖縄は入っているのか」(菅義偉官房長官に)
「普天間は危険だから大変だとなって、その危険性除去のために沖縄が負担しろ、と。こういう話がされること自体が日本の政治の堕落ではないか」(同)
「歴史的にも現在においても、沖縄県民は自由、平等、人権、自己決定権をないがしろにされてきた。私はこれを『魂の飢餓感』と表現している」(国と争う辺野古訴訟の陳述で)
ほかにも多々あり、言葉でたたかう人だったことがわかる。しかし腹の底から絞り出したであろう声が政府に届いた様子はない。安倍首相は二言目には「沖縄の気持ちに寄り添って」と、実際から程遠い美辞を単調に繰り返してきた。
「言葉の発し手と、受け手とが、ぴたり切りむすんだ時、初めて言葉が成立する」と言ったのは、詩人の茨木のり子さんである。続けて「全身の重味を賭けて言葉を発したところで、受け手がぼんくらでは、不発に終り流れてゆくのみである」と。政権が翁長氏の言葉と切り結ぶことはなかった。沖縄の民意をのせた重い言葉は、一強政権の驕慢(きょうまん)に問答無用の体で跳ね返されたままである。
*
沖縄は本土復帰からの46年を7人の知事でつないできた。8人目を決める選挙が今月30日にある。
国と協調するのか、対峙(たいじ)するのか。そんな選択を知事選挙で問われ続けてきた都道府県は沖縄をおいてない。政府は時の知事の姿勢をみて、振興費の蛇口を開いたり絞ったりした。大田昌秀知事の時代には政府との関係が冷え切って「県政不況」という言葉さえ生まれた。
一人ひとりに暮らしがある。それと同時に、沖縄はこうあってほしいという基地の島ゆえの思いがある。選挙は、そのはざまでの決心をそれぞれに迫る。その過程での地域や職場、ときには親戚や家族まで巻き込んでの分断や確執が、これまでも人々を苦しめてきた。
沖縄の人口は全国の1%しかない。その沖縄に「魂の飢餓感」を押しつけたまま、それすら忘れたように99%が安らぐ図は異様である。翁長氏が2年前、報道機関との懇親会で「政権の何が一番だめなのか」と聞かれ、「愛がない」と答えたという話が、いま胸にこたえる。
言葉は私たちに投げられたのだ。「ぼんくらな受け手」でありたくはない。
※沖縄ときちんと向き合った野中広務師のことが本当に偲ばれる(もみ)。