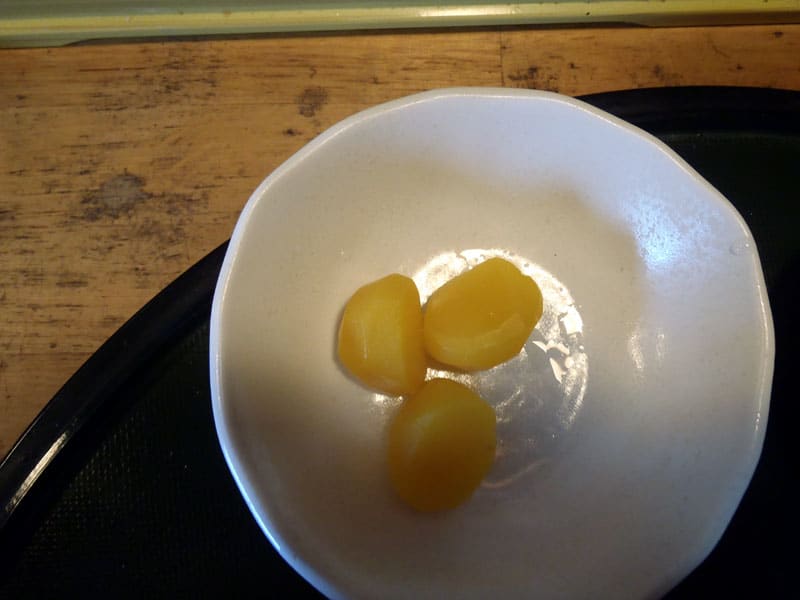今回の目的地は、白鳥の飛来地として有名な大田原市の羽田沼(はんだぬま)です。
白鳥を求めて北へ向かってGO!
今回も馬頭までは前回と同じ道で行きます。前回、八溝グリーンラインを馬頭グリーンラインと書いてしまいました。訂正します。
あの罰ゲームのようなアップダウンが癖になりそうです。

この日は、第一回ブリッツェンクリテリウムでした。朝早くから選手やスタッフの皆さんが準備しています。NHKでも報道してましたねえ。

さくら市に入ると回りは一面雪景色です。宇都宮では全然無かったのですがねえ。まだ15km位しか離れてないのに。
この日は、羽田沼周辺で歩くのを考慮してSPDペダル&シューズです。やはり巡航速度は2km/h位落ちます。

八溝グリーンラインに入ると路肩は雪が残ってます。雪解け水が路面で凍結していてスリル満点でした。

トンネルを抜けると絶景ポイントでした。雪が無ければ普通の景色ですけどね。

馬頭を抜け御前岩をスルーしてR461を北上します。車がやっとすれ違えるような道ですが国道です。
前日までの天気予報では晴れるはずだったのですが、一日中曇りでした。この日、大田原は最高気温、3.8℃寒い!

ちょっと寄り道をして雲巌寺を見学します。左の灯篭は明治32年、右の小さい方は明治40年。歴史を感じます。

立派なお寺です。中央の仏殿では、ご本尊?を惜しげもなく見せてくれます。
雪景色の雲巌寺の写真をたっぷり撮ったら羽田沼に急ぎます。

大田原市に入ると更に真っ白です。(路面悪いんだから走りながら撮るなよ、危ねえなあ)

今回の追加機材です。E-420ダブルズームキット。2008年購入です。
一眼レフ最軽量なので自転車での携帯にはピッタリです。暗いと焦点が合い難いのが欠点ですが昼間ならまったく問題なし。真っ白な白鳥の羽でもピタピタピントが合いました。
後ろはLoweproの巨大ウエストバッグです。大型の一眼レフでも入ります。満員電車でこれを付けているとかなり迷惑です。
3羽しか居ませんでした。100羽以上居るはずだったのに。。。
地元の人の話だと田んぼに餌を食べに行ってるのだそうです。以前はここで給餌していましたが、水質悪化の為、今は餌を与えず自然のままの状態にしているそうです。

白鳥も鴨もまったく人を警戒しません。危害を加える人が居ないからでしょう。この鴨はすぐ足元まで来ていました。当然餌はやってません。
写真を撮り終わった頃、お昼を告げるサイレンが鳴りました。田舎の方ではまだお昼のサイレンが残ってます。大田原市街の阿Qを目指します。
http://www.tochinavi.net/spot/home/index.shtml?id=360
この店は盛りが多いので有名です。何度か来た事がありますが自転車の人はここで食べた後、坂を上るのはやめましょう。
僅かに値上げして有りますが、量や質を落とすくらいなら値上げしたほうが良いです。

ブレブレ写真ですが、少し食べた所です。ご飯の上に分厚い肉の層が乗っていてまるで富士山の断面図です。こぼさないように食べるのは至難の業でした。
美味しかったですよ。ちょっと味は濃い目かな。脂っこいのが苦手の人はきついでしょう。
次は麺類に挑戦したいですね、洗面器のようなドンブリになみなみと麺とスープが入ってました。
本当は、お昼を食べたら帰路に付く予定でしたが羽田沼に白鳥が3羽しか居なくて悔しいのでもう一つの飛来地、琵琶池に向かいます。

羽田沼は大田原市の北の端、琵琶池は南の端です。大田原を縦断してしまいました。
琵琶池は20羽以上居ました。色が黒いのは子供でしょうか。

琵琶池のカモ達も人を警戒しません。写真を撮るには最高ですね。
夕方になると路面凍結の恐れがあるので急いで帰りました。
本日の走行距離、143km
獲得標高、900m