外国に なんか時々バッタが大量発生して 何もかも食べ尽くして
住んでいる人の食料が無くなって大変なことになる という話はなんとなく知っていた。
でも、大量発生しないときは そのバッタはどうしているのか、って考えたことも無かった。
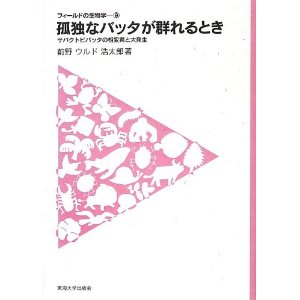
この東海大学出版会の フィールドの生物学 のシリーズは大変に興味深いです。
以前に紹介した「右利きのへび仮説」もそうです。
表紙が同じ絵(パターン)で色違いってのが 面白くないのだけど、なんか変えて!
で、バッタなんですが、大量発生しないときは 孤独なバッタなのよ。で、孤独相といいます。砂漠のあっちこっちにぱらぱら住んでいるそうです。
大量発生するときは 群生相というんだそうです。
で、この2タイプは終齢幼虫でも成虫でも 体色やサイズがゼンゼン違うのです。
孤独相は 幼虫は黄緑色 成虫は黄緑かかった明るい黄土色、まあよく見かけるバッタに似てますな。
こいつが、群生相になると子どもの時から 黒っぽくて(殆ど黒)で成虫になっても
黒やら赤っぽかったりしてケバくて サイズもでかい。別人のようです。
じゃあ どうして同じバッタ(サバクトビバッタ)が大量発生するのか。
そこのところは 研究のポイントなので、どのように調べていったのか書かれています。
孤独相のバッタと群生相のバッタは環境によってどちらにも変わるのです。
前野氏 かなり楽しい方のようで 所どころにはさまれるエピソードは笑えます。

年末から読み始めて読了したら、朝日新聞の 「ひと」の欄に前野氏が紹介されていました。あまりに タイムリーなので 笑ってしまいました。
惚れ込んだ生物をずっと研究するのには あこがれますねえ。
研究は殆ど日本でされていたのですが 今はアフリカで研究されてます。
バッタの研究は かなり世界中の学者が行なっているようで 学会の様子も面白いです。
私的には あまり人気のない ナメクジやら ミミズの研究の本も読みたいですなあ。
住んでいる人の食料が無くなって大変なことになる という話はなんとなく知っていた。
でも、大量発生しないときは そのバッタはどうしているのか、って考えたことも無かった。
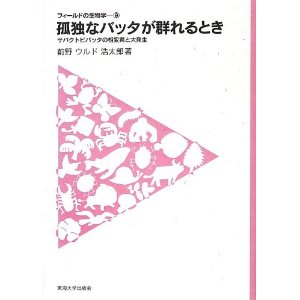
この東海大学出版会の フィールドの生物学 のシリーズは大変に興味深いです。
以前に紹介した「右利きのへび仮説」もそうです。
表紙が同じ絵(パターン)で色違いってのが 面白くないのだけど、なんか変えて!
で、バッタなんですが、大量発生しないときは 孤独なバッタなのよ。で、孤独相といいます。砂漠のあっちこっちにぱらぱら住んでいるそうです。
大量発生するときは 群生相というんだそうです。
で、この2タイプは終齢幼虫でも成虫でも 体色やサイズがゼンゼン違うのです。
孤独相は 幼虫は黄緑色 成虫は黄緑かかった明るい黄土色、まあよく見かけるバッタに似てますな。
こいつが、群生相になると子どもの時から 黒っぽくて(殆ど黒)で成虫になっても
黒やら赤っぽかったりしてケバくて サイズもでかい。別人のようです。
じゃあ どうして同じバッタ(サバクトビバッタ)が大量発生するのか。
そこのところは 研究のポイントなので、どのように調べていったのか書かれています。
孤独相のバッタと群生相のバッタは環境によってどちらにも変わるのです。
前野氏 かなり楽しい方のようで 所どころにはさまれるエピソードは笑えます。

年末から読み始めて読了したら、朝日新聞の 「ひと」の欄に前野氏が紹介されていました。あまりに タイムリーなので 笑ってしまいました。
惚れ込んだ生物をずっと研究するのには あこがれますねえ。
研究は殆ど日本でされていたのですが 今はアフリカで研究されてます。
バッタの研究は かなり世界中の学者が行なっているようで 学会の様子も面白いです。
私的には あまり人気のない ナメクジやら ミミズの研究の本も読みたいですなあ。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます