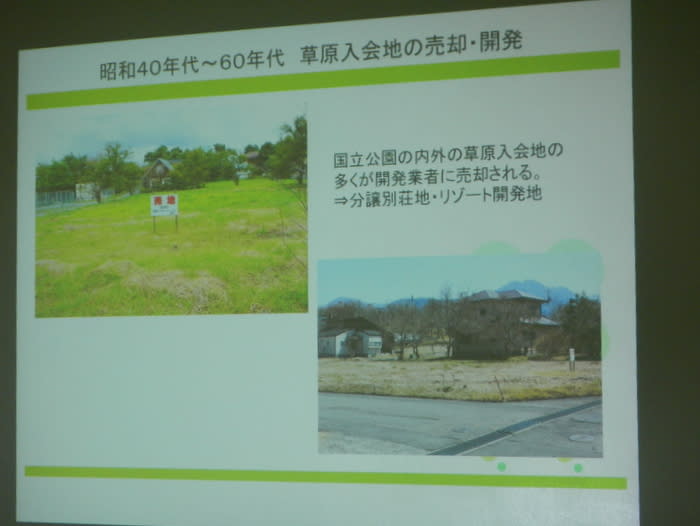梅雨明けの土曜日はサイエンス・カフェですよ。 さて外来生物 パート2
パート①と同じく 講師は 瀬口三樹弘 氏 です。

おとぼけ顔(ほんとは背中の模様)のラミーカミキリから 話が始まりました。
インドシナ半島や中国にいるラミーさんは1860年頃に日本(長崎)にやってきたらしい。
今や西日本各地で愛嬌を振りまいているらしい。 食草がカラムシなのでいろいろ言われなくてすんでるらしい。

キマダラカメムシも1770年代に長崎で見つかった。 この写真は上野墓地公園で撮った物。もうどこにでもおるがな。
人に悪さをしたり 人の食べモンに手を出すと いきなり 害虫!! となって大騒ぎ。

イセリアカイガラムシ(外来の害虫)を 食べる ベダリアテントウ(外来の益虫!!、、?)
さて大分名産 椎茸につく害虫(ハラアカコブカミキリ) にオオイタンシはどう立ち向かったか

これはすごいです。
キノコ(菌糸類)を使っての駆除です。
それでも どんどん外来種は 大手を振ってやって来ます。

カブトムシ好きな小学生は 大喜びしそうです。
ガーデニング自慢の奥さんは ご近所にない花(まあ外来種ですわ)を植えたがり 見せびらかしたがり
おされなレストランテは だいこん・カボチャじゃなくて イタリアやらフランス産のお野菜でのメニュー
おまけに珍しいモン 作りましょう ってなことで

亀さん受難の日々 「うんきゅう」とかいうのは 珍しいので 無理矢理作ったりするそうです。 ひどい、亀さんだって相手を選ぶ権利があります。

考えなしに輸入した生き物が今やとんでもないことになっています。 マングースとか ウシガエルとか ブラックバスとか、、(以下延々と続く)
さて 自然に関わっている 我々 自然観察指導員 はどうしたらいいのか。 これが今日のカフェのテーマです。
いろんな意見が出て検討されました。 そのいくつかは 試しにやってみましょう ということになりました。
さあ どうなるかなあ。こうご期待!
パート①と同じく 講師は 瀬口三樹弘 氏 です。

おとぼけ顔(ほんとは背中の模様)のラミーカミキリから 話が始まりました。
インドシナ半島や中国にいるラミーさんは1860年頃に日本(長崎)にやってきたらしい。
今や西日本各地で愛嬌を振りまいているらしい。 食草がカラムシなのでいろいろ言われなくてすんでるらしい。

キマダラカメムシも1770年代に長崎で見つかった。 この写真は上野墓地公園で撮った物。もうどこにでもおるがな。
人に悪さをしたり 人の食べモンに手を出すと いきなり 害虫!! となって大騒ぎ。

イセリアカイガラムシ(外来の害虫)を 食べる ベダリアテントウ(外来の益虫!!、、?)
さて大分名産 椎茸につく害虫(ハラアカコブカミキリ) にオオイタンシはどう立ち向かったか

これはすごいです。
キノコ(菌糸類)を使っての駆除です。
それでも どんどん外来種は 大手を振ってやって来ます。

カブトムシ好きな小学生は 大喜びしそうです。
ガーデニング自慢の奥さんは ご近所にない花(まあ外来種ですわ)を植えたがり 見せびらかしたがり
おされなレストランテは だいこん・カボチャじゃなくて イタリアやらフランス産のお野菜でのメニュー
おまけに珍しいモン 作りましょう ってなことで

亀さん受難の日々 「うんきゅう」とかいうのは 珍しいので 無理矢理作ったりするそうです。 ひどい、亀さんだって相手を選ぶ権利があります。

考えなしに輸入した生き物が今やとんでもないことになっています。 マングースとか ウシガエルとか ブラックバスとか、、(以下延々と続く)
さて 自然に関わっている 我々 自然観察指導員 はどうしたらいいのか。 これが今日のカフェのテーマです。
いろんな意見が出て検討されました。 そのいくつかは 試しにやってみましょう ということになりました。
さあ どうなるかなあ。こうご期待!