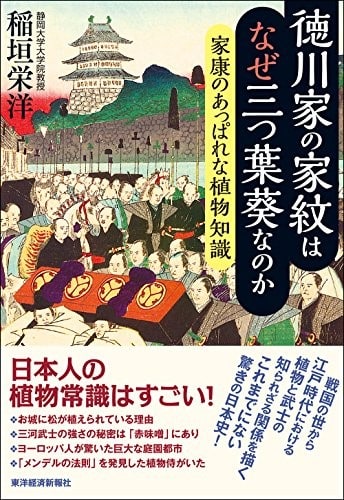誰だって化石採集は大好き これまで2回化石採集を企画したけど参加者のしつこさと熱中さには いささかあきれたのだ。

だからと言って 誰でも化石になりたいと思うだろうか?
この本は冒頭から どんなタイプの化石になりたいか で始まっている。 いや私、化石になりたくありません。
でも中身は やっぱり化石は大好きで どのタイプも魅力的。
土に埋もれて石化するばかりではない、ポンペイのように空洞になったり オパールのような宝石になったり
美しい化石の写真が満載で でき方も図化されて分かりやすい。 でもしつこくこのタイプで化石になると全身は無理とか、、化石にはなりたくないのよ!
どうやら作者の土屋氏に化石願望が強くあり このような体裁の本ができたそうです。
現代なら 冷凍保存やらいろいろな方法で後世に残せそうだけど これが存外難しい。いったい誰が保存をし続けるのか?
そーだよねえ プルトニウムだって きちんと放射能が漏れないようにいつまでも保全できるかなんて何の保証もないしねえ。
過去を知りたいと思うことと 未来に残したいと思う事は リンクしているのかな。