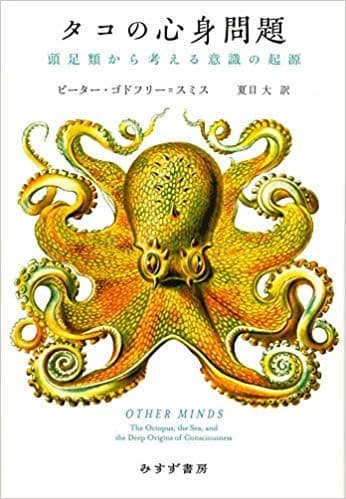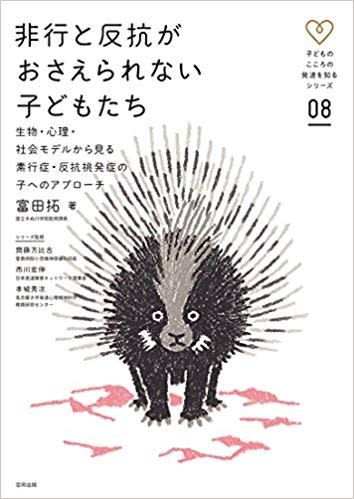表紙のイラストが楽しそうな本なので読んでみようと思った

高校んとき 地学はすかんかったし
今でも 化石掘りは好きだけど 石の名前は おぼえんなあ
てなことで 文系ではないが 地学の本を読もう
ところどころに宮沢賢治の作品が引用されて 石(地学)がわかるとこう読めるのだ というのが分かる
星座も出てきて ああ星は 大きな石なんだと思う
でも楽しかったのは 実際の岩石や地層ができる様子を試してみよう のコーナー
蒸しパンのもとに食用竹炭を混ぜて蒸かして緑のお菓子の粒をまぜれば 岩石
カタクリ粉を水で溶かして ゆっくり固めて 柱状節理を作ります
砂糖をカラメル状にして バットに流し込んで 固まりかけたところを斜めにして溶岩 これは後で食べられるねっ!
各地の地学博物館も紹介されて 見て回る楽しさも
石のでき方は3種類しかないので ちゃんと勉強しよう