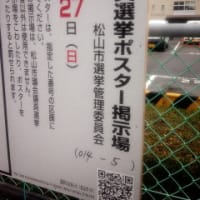子どもたちの農業体験学習である立岩ダッシュ村を一年通して学んだこと。
集団行動の中で、子どもたちは一人ひとりが本当に違うということを改めて感じた。
コーチ役の学生ボランティアのお兄さん、お姉さんに常にまとわりつく子。
日々の愛情が足りないのかもしれないと思ったり、自分のありかを探しているのかもしれないと感じたり、学ぶところがたくさんあった。
そんな中、常に集団からひとりポツンと景色だけ観ている少年がいた。
ある時は農業経験に加わらず、立岩の谷間の田園風景をひたすら観ている。
話しかけてみた。
「こういうのって好きじゃない?」
「あ~あ」
「ふ~ん。じゃあ、なぜ応募してきたの?」
「ママが申し込んだ」
「なぜ『いゃ』って言わんかったん?」
「めんどくさいけん」
「ふ~ん。ぜんぜんおもしろくない?」
「うん」
「そうか、そりゃあ苦痛でたまらんなあ」
「・・・」
そんな彼に変化が見られた。
ある時、畑を耕しているトラクターを子どもたちの最前列に来て、輝く目で見ている。
傍によっていき、「乗りたい?」と聞いてみた。
「うん!!」
「じゃあ、聞いてやろう」
その少年のささやかな希望がかなった。
最後のダッシュ村の日。
村長(松田公民館長)と二人で話していると、その少年が近づいてきた。
「あの里芋、どうするん?」と、里芋の畝(うね)を指差した。
「どうするんて?」と聞き返した。
「全部獲ら(収穫せ)んでええん?」
「ああ、あれは種ぶんじゃ」と村長が応える。
「種?」
「ああ、里芋はああやって増やした分を収穫して食べるんやが、ちい(少し)と残すんじゃ」
「残す?」
「そうじゃ。残すんじゃ」
「残して、どうするん?」
「残して、来年のために土の中に置いとくんじゃ」
「なんで土の中なん?」
「土の中に残しておくと腐らずに、ずっと生きとるけんよ」
「土の中で生きとる?」
「ほうよ」
少年の頭の中はきっとこんがらがっているにちがいない。
「わかったか?」
「んー...」
「次につなげるためには、すべて食べつくさんのよ。そしてそれを大事に保存するために土に守ってもらうんじゃ」
たぶん、半分くらいしか理解できなかったかもしれない。
でも、それでもいいと思った。
子どもたちは、大人の話を全て理解するのではなく、大人が発する言葉のキーワードをインプットしているだけかもしれない。
そして、成長する過程の中でだんだんとそのキーワードが格納庫から引っ張り出され、理解されていくのかもしれない。
そう考えると、私たちは子どもが理解しようとしまいと、上手に伝えようなどとは思わず、どんどん小難しい話を子どもたちにした方がいいような気がする。
そのときに大切なことは、上手に伝えることではなく、一生懸命に伝えることだと思う。
この少年のちょっとした変化であるが、この仕事をしてよかったと思う。
集団行動の中で、子どもたちは一人ひとりが本当に違うということを改めて感じた。
コーチ役の学生ボランティアのお兄さん、お姉さんに常にまとわりつく子。
日々の愛情が足りないのかもしれないと思ったり、自分のありかを探しているのかもしれないと感じたり、学ぶところがたくさんあった。
そんな中、常に集団からひとりポツンと景色だけ観ている少年がいた。
ある時は農業経験に加わらず、立岩の谷間の田園風景をひたすら観ている。
話しかけてみた。
「こういうのって好きじゃない?」
「あ~あ」
「ふ~ん。じゃあ、なぜ応募してきたの?」
「ママが申し込んだ」
「なぜ『いゃ』って言わんかったん?」
「めんどくさいけん」
「ふ~ん。ぜんぜんおもしろくない?」
「うん」
「そうか、そりゃあ苦痛でたまらんなあ」
「・・・」
そんな彼に変化が見られた。
ある時、畑を耕しているトラクターを子どもたちの最前列に来て、輝く目で見ている。
傍によっていき、「乗りたい?」と聞いてみた。
「うん!!」
「じゃあ、聞いてやろう」
その少年のささやかな希望がかなった。
最後のダッシュ村の日。
村長(松田公民館長)と二人で話していると、その少年が近づいてきた。
「あの里芋、どうするん?」と、里芋の畝(うね)を指差した。
「どうするんて?」と聞き返した。
「全部獲ら(収穫せ)んでええん?」
「ああ、あれは種ぶんじゃ」と村長が応える。
「種?」
「ああ、里芋はああやって増やした分を収穫して食べるんやが、ちい(少し)と残すんじゃ」
「残す?」
「そうじゃ。残すんじゃ」
「残して、どうするん?」
「残して、来年のために土の中に置いとくんじゃ」
「なんで土の中なん?」
「土の中に残しておくと腐らずに、ずっと生きとるけんよ」
「土の中で生きとる?」
「ほうよ」
少年の頭の中はきっとこんがらがっているにちがいない。
「わかったか?」
「んー...」
「次につなげるためには、すべて食べつくさんのよ。そしてそれを大事に保存するために土に守ってもらうんじゃ」
たぶん、半分くらいしか理解できなかったかもしれない。
でも、それでもいいと思った。
子どもたちは、大人の話を全て理解するのではなく、大人が発する言葉のキーワードをインプットしているだけかもしれない。
そして、成長する過程の中でだんだんとそのキーワードが格納庫から引っ張り出され、理解されていくのかもしれない。
そう考えると、私たちは子どもが理解しようとしまいと、上手に伝えようなどとは思わず、どんどん小難しい話を子どもたちにした方がいいような気がする。
そのときに大切なことは、上手に伝えることではなく、一生懸命に伝えることだと思う。
この少年のちょっとした変化であるが、この仕事をしてよかったと思う。