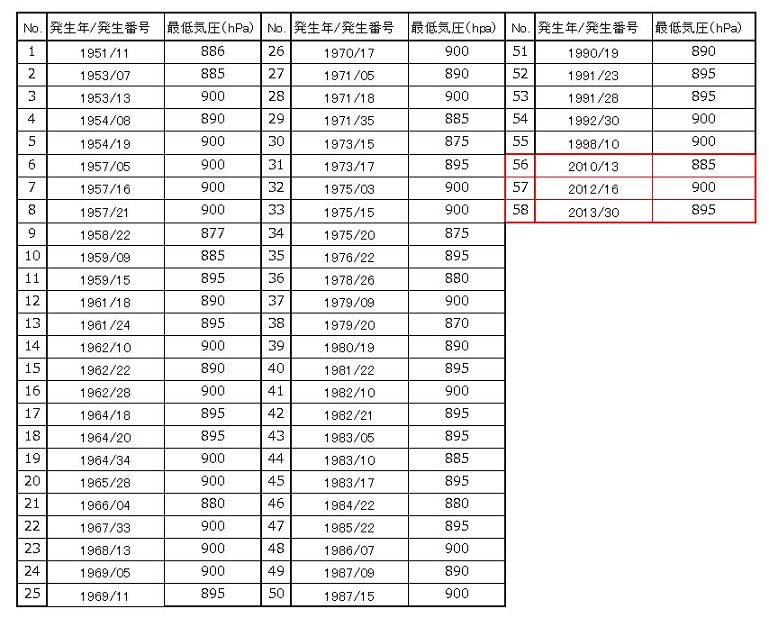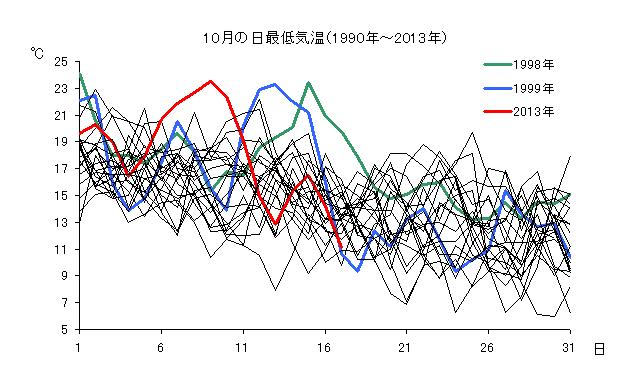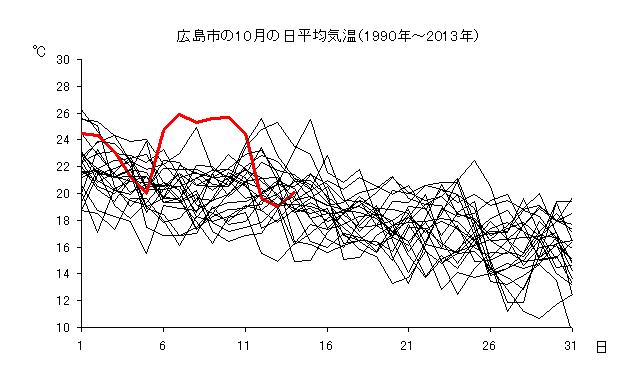すばらしいサイトを見つけたので、久しぶりに地球温暖化と黒点について書きます。
上記サイトから1949年1月から2017年10月までの月毎の黒点数の推移データをダウンロードしグラフにしました。
黒点数は11年周期で増減を繰り返しています。
本当にそうなのでしょうか?
パワースペクトルを計算して確かめてみましょう。
FFT法などは分解能が低いのでMEM法で計算します。
ピークをしっかりとらえています。
概ね11年といわれていますが、厳密には10.6年です。
ただし周期は変動しており10.6年を中心に前後に揺らいでいます。
これは太陽が生きている証拠です。
黒点数と太陽活動は正の相関があり、黒点が多いときは活発で、少ないときは静穏です。
17世紀に黒点がほとんど現れない期間が30~40年続き(マウンダー極小期)、地球は寒冷化しました。
19世紀にもダルトン極小期とよばれる黒点の少ない時期があり気温を押し下げました。
多くの太陽研究者はCO2温暖化説に懐疑的で、地球の気候を決めるのは太陽だと考えています。
現在、太陽はダルトン極小期の再来と思われるほど不活発で、太陽研究者はそれが気候にどのように影響するか注意深く見守っています。
黒点の変動を人の心拍数にみたてると、マウンダー極小期は不整脈ですね。心房細動によく似ています。