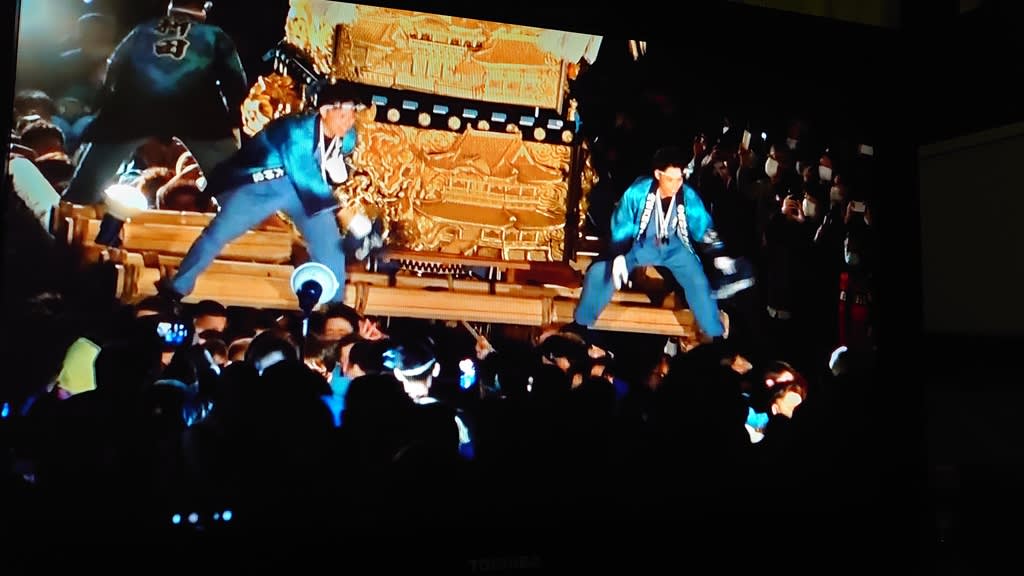寒くなると畑の土の中から大根の首の部分が勢いよく顔を出した姿をあちこちで見かける。

大根は煮物や汁物、サラダ、それにおろし大根といったいろいろな料理に用いられ、私も好物の1つだ。
大根は古くから親しまれてきた野菜の一つだが、夏の終わりから初秋(9月前半)に種を播いて冬に収穫する種類のものと、春に種を蒔いて梅雨時に収穫する"秋まき"大根の2種類がある。
今、旬を迎えている大根は"秋蒔き"大根で、煮物にしても汁物の中に入れても大変旨い。また、よく味がしみ込んだおでんのダイコンは美味い。
"葉"に栄養があるダイコンだが、スーパーでは葉っぱを落とした大根が主流で、白い根の部分が並べられている。


この写真では葉っぱがついたままの大根が登場しているが、まもなく葉の部分が切り取られた大根がそれぞれの畑に登場する。何故だろう???
実は、葉っぱが栄養分を吸い取ってしまい、本体の根の部分が"ス"になってしまうからだ。(葉に栄養分が無くなり、ダイコン特有の味がなくなってしまう)
このため、葉はまもなく切り取られる。
👇葉っぱが付いていないダイコンは冬のひとつの風物詩ともいえる。
(22/02撮影)










































 ※10年前、自宅近くの神社境内で撮った"紅梅"の写真(このころはウメの開花が早かったようだ。)
※10年前、自宅近くの神社境内で撮った"紅梅"の写真(このころはウメの開花が早かったようだ。)