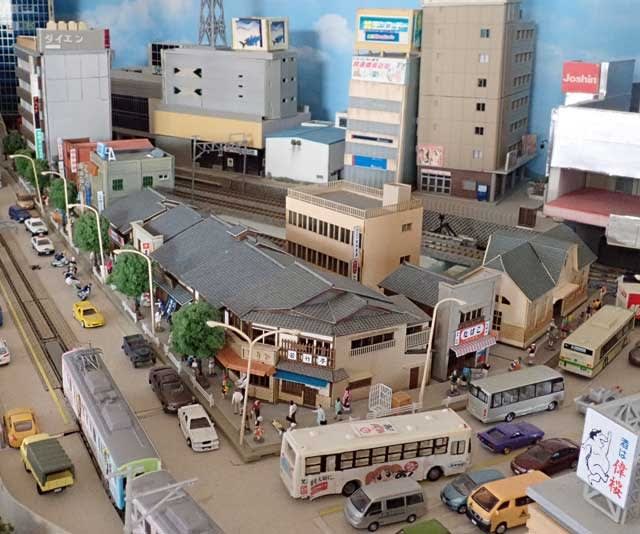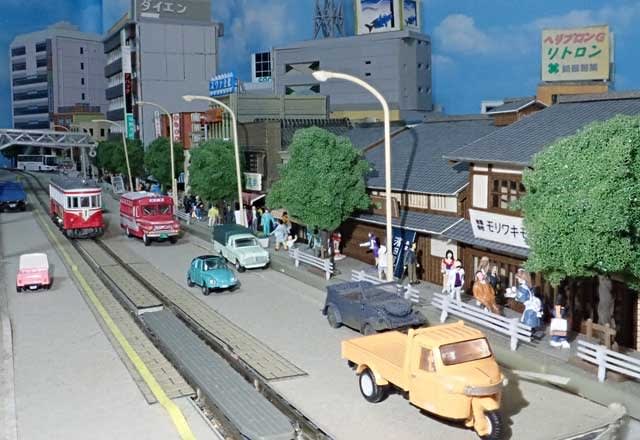先日は久しぶりの平日休。
コロナ禍の影響もあり基本自宅蟄居に近い一日です。
という訳で遅めの朝食が終わると、早速作りかけのペーパーキットの仕上げに掛かります。
前にも書いた事がありますが私の工作場所は家族の邪魔にならない範囲で「台所の片隅、流しの脇」を使う事が多いです。
火を使う場所だけに塗装の類はできないのですが頭上に換気扇があるので簡単なプラ工作程度まではできます。

尤も、ここ1年くらいは車両もストラクチャーもペーパーキットが主体ですし、塗装も外で行なうので台所モデリングのデメリットは意外に少ない。デカール貼りで「蒸しタオルが欲しい」時なんかは脇の電子レンジで手軽にできたりしますしカッターマットがあれば流しに傷も付きません。
問題は「毎回工作が終わったらすべて元通りに撤収しなければならない事と(当然ですが)調理中や皿洗い中は使えなくなる事」です。
まあ、毎回片付け癖が身に着くと思えば悪くはないですし、工作がしたさに食器洗いを率先してやってしまうメリットもないではありません。
BGMは後ろのラジオから流れる「東京FM」
特に昼間の番組は田舎住まいからすれば別世界の様な都会っぽさが感じられ、これも一種非日常的な空気に浸れます。
(これが地元のミニFM局なんかだと自分が田舎にいる事を認識できるメリットもw)

工作がひと段落着いたところで流しの裏側にこっそり存在する「鉄道カフェ風スペース」で紅茶とおやつを。
一見こう書いたらカッコいいですが壁面は冷蔵庫の側面ですし背中合わせに流しですから、視線を動かすと「ただの台所」です。
夕方に晩御飯のおかずを買いに外出したほか、その日は蟄居で済ませてしまえました。
ですが外に出ると夕焼けの山々が眩しい。
たとえ表の通りであってもたまには外の空気を吸わないと体に悪いという事も認識させられます。
さて、平日休を使ってやった工作については次の機会にでも。
コロナ禍の影響もあり基本自宅蟄居に近い一日です。
という訳で遅めの朝食が終わると、早速作りかけのペーパーキットの仕上げに掛かります。
前にも書いた事がありますが私の工作場所は家族の邪魔にならない範囲で「台所の片隅、流しの脇」を使う事が多いです。
火を使う場所だけに塗装の類はできないのですが頭上に換気扇があるので簡単なプラ工作程度まではできます。

尤も、ここ1年くらいは車両もストラクチャーもペーパーキットが主体ですし、塗装も外で行なうので台所モデリングのデメリットは意外に少ない。デカール貼りで「蒸しタオルが欲しい」時なんかは脇の電子レンジで手軽にできたりしますしカッターマットがあれば流しに傷も付きません。
問題は「毎回工作が終わったらすべて元通りに撤収しなければならない事と(当然ですが)調理中や皿洗い中は使えなくなる事」です。
まあ、毎回片付け癖が身に着くと思えば悪くはないですし、工作がしたさに食器洗いを率先してやってしまうメリットもないではありません。
BGMは後ろのラジオから流れる「東京FM」
特に昼間の番組は田舎住まいからすれば別世界の様な都会っぽさが感じられ、これも一種非日常的な空気に浸れます。
(これが地元のミニFM局なんかだと自分が田舎にいる事を認識できるメリットもw)

工作がひと段落着いたところで流しの裏側にこっそり存在する「鉄道カフェ風スペース」で紅茶とおやつを。
一見こう書いたらカッコいいですが壁面は冷蔵庫の側面ですし背中合わせに流しですから、視線を動かすと「ただの台所」です。
夕方に晩御飯のおかずを買いに外出したほか、その日は蟄居で済ませてしまえました。
ですが外に出ると夕焼けの山々が眩しい。
たとえ表の通りであってもたまには外の空気を吸わないと体に悪いという事も認識させられます。
さて、平日休を使ってやった工作については次の機会にでも。