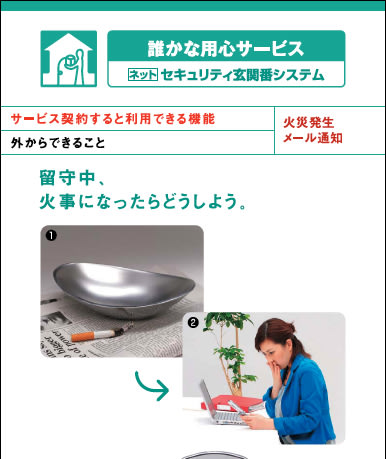台風12号が北上し、関東に上陸すると思っていたら、一歩手前で東に逸れました。
新潟方面では大陸側からの寒気が入り込み、肌寒い一日となっています。
今年は、太平洋高気圧の張り出しが弱いのか、台風も本州まで到達できないようです。大陸の気団の勢力が強いのか?
今年の冬は寒いんだか、暖冬になるのだか・・わからん
秋雨前線の形成が無いのがちょっと気になります。
美沢町N邸では、地鎮祭も終わり、基礎工事の前の地盤補強工事を行っています。
「柱状改良」による地盤補強を29箇所、平均7mの予定です。
事前の地盤調査の結果、この一体は分譲する時に田んぼを埋め立て、その時に玉石を敷き詰めたということが分りました。
1mくらいの深さに50センチの石の層があり、地盤を補強して切り売りしたようです。
新潟県中越地震では、ここより東側の中沢町で家屋にかなりの被害がありましたが、その近くで比較的被害が少なかったのは、分譲時にちゃんと補強を行っていたからなのでしょう。
当時としては、土地を買う人のために最大限の努力をしたのでしょう。
ところが、この固い地盤を、新しい建物の定着地盤としては使えないと言うのが地盤保証機構の回答でした。
当初の予定通り、1m深さの玉石の層を突き破り、7mまで掘って柱状改良とすることを要求してきました。
24坪程度の基礎で30本もの柱状改良自体、1坪に1本の割合ですから、殆ど主要な柱ごとに改良部分があり、さらにベタ基礎なのに布基礎でも良いような改良をしなければならない・・・
念には念を入れる。
というか、よっぽど保険金を払いたくない(事故による保証)といった感じです。
おそらく、背景には、1つでも事故を起したような方法は消していくというところです。
こういった玉石補強がしてあった場所で沈下が起こったという前例があるのでしょう・・
いずれにせよ、玉石地盤を破って7mの圧密地盤まで到達し、摩擦杭として地盤補強をしなければならず、この玉石の層を破るのが、通常の補強工事よりも手間がかかってしまうことになりました。
先人の努力が仇になってしまった結果になったのですが・・・
それでも、地盤改良をしない部分のベタ基礎は、その玉石の層があるために強固になるはずです。
地盤改良自体は10年しか保証しませんが、その下の層と一体となったベタ基礎で長期間もたせるような基礎にしてやればよい。
制度的には地盤補強が必修となりましたが、それ以上になる努力をする必要があると思います。

地盤補強のためのセメント
これを掘った土と混ぜて土中に硬い柱を作ります

セメントの袋ごとミキサーに入れます
この機会で水とセメントを混ぜ、ドリルで掘った穴に注入します。
(セメント・ミルク)

ドリルで地面を掘りながら、セメントを注入中・・

使用後の袋
産廃処理されるそうです。(もったいない)
このトンパックの袋は、ミキサーにかけるときにクレーンで吊って、下を針で破り、セメントを放出する仕組みとなっているので、使い終わったら、廃棄するしかないそうです。
まだ使えそうなのですが、もったいない限りです。
工場に持ってきて袋に使えないか検討中です。
解体時も、石膏ボードの搬出にトンパックを使いますが、わざわざ新しい袋を買ってきて、処理業者へ渡し、その後は廃棄するだけだと聞きました。
こういったボード搬出用に、地盤改良時のトンパックを使ってもらい、なるべく廃棄するまでの時間を稼げないものかと考えています。
地球温暖化を防止するためのゴミ処理なのですが、こういったエネルギーや資源ののムダ使いをしているのも変な話です。
もったいないことを止める
もう一度使う工夫をする
そういった一つ一つの行動が地球温暖化防止の第一歩です。