
「考え抜く社員を増やせ! 変化に追われるリーダーのための本」 柴田昌治・著、日本経済新聞出版社、2009年11月9日
p.1-2 最近の企業の人材育成方針はどの企業を見ても、「自発性とか自主性をどう引き出すか」が主要テーマになっています。掛け声ばかりは威勢が良いけど実態はまったくと言ってよいほど伴っていないのが現状です。何が欠けているのでしょう。その答えとは「考える力」を引き出す努力です。
p.2 社長はお客様本位を熱心に唱えているのに、営業本部長は「そんなきれいごとで飯が食えるか」と、本心では苦々しく思いながらも表向きは社長の言うことに付き合っている、というような状況です。こうした企業では“お客様に親切にすることがお客様本位だ”と、薄っぺらにお客様本位というものを捉えているケースが多いようです。特に物事を形式的にこなすのが得意な大手企業には、この傾向が強い。
その結果、お客様に親切にする負担は、一方的に現場に「しなくてはならない努力」という形で押し付けられています。単にお客様に表面的に親切にするとか喜んでもらうだけのお客様本位は、当然、業績とは連動していきません。ただ押し付けられるだけでは知恵も本当の意味でのやる気も出てこないからです。でも、儲からないと飯は食えませんから、結局、お客様本位などときれいごとばかり言ってはいられなくなります。そこで、月初はお客様本位を唱え、月末になると数字で締め付ける、といったちぐはぐなことが起こるのです。
p.29 次世代を担うはずの経営人材には、特にしっかりとした「考える力」が不可欠です。仕事をこなす力ではなく、その意味や目的を要所要所で問い直す姿勢と、事実にもとづくいて現状を把握し、制約を外して問題点を考え抜く、という姿勢がなくては不確実な時代の経営の舵取りはできない、と思えるからです。
p.30-1 物事をとにかく先に進めることばかりに目がいっている人がほとんどで、「なんのために」とか、「この仕事にどういう意味があるのか」などを常に問い直しながら展開していく力を持っている人は現代の経営においては間違いなく少数派です。
しかし、本来、成長する企業の経営者というのは、そうした本質的な問いかけを自らに課しているものです。
p.33-4 現実の多くの仕事では、三人部下がいる場合、能力のある三人と、能力のない三人とでは、パフォーマンスがまったく異なる・・・、にもかかわらず従来からある常識的な見方では、基本的に人間のクオリティはカウントせず、すべて「員数」で見るという傾向があったのです。
こうしたものの見方の持つ一番の問題点は、物事や出来事の価値、質、その持っている意味などを、思考の対象から外してしまうところにあります。質ではなく数えやすい量が重視され、中身ではなく、形式が大切にされます。
物事の価値や意味、つまり「なんのために」「どういう意味があるのか」を問う姿勢も後ろに追いやられ、いつの間にか「どうやればいいのか」「どうやると効率的か」しか考えなくなってしまうのです。
ひたすら目先の利益の最大化だけを追い求め、そのことの意味や価値を問わず、「どうやるか」しか考えないとするなら、環境激変時の対応策にしても、何がそうなったかは問いませんから、どうしてもモグラ叩き敵なアイデアしか浮かんでこなくなってしまうのです。
経営品質にしても顧客本位主義にしても、本来はすばらしい考え方であるにもかかわらず、結局、多くが中身の伴わないスローガン倒れやきれいごとになってしまっているのはそうした理由からなのです。
p.35 「上司から言われたことを効率的にこなす」のが仕事だ、と思っているときは、「仕事を処理する」ことが、あたかも最終目的のようになっています。本来の目指すべき目的が意識されていないと、形を整えたらそれでよしとされます。
p.36 深く考えることが習慣化された組織になっていくと、目の前の仕事を処理することはあくまでも「手段」にすぎないことが見えてきます。自分たちのやっている仕事が社会にどういう影響を与えているのか、会社が果たすべき社会的な役割はなんなのだろう、という自らに対する問いかけが新たな「気づき」を生み出します。
p.37 「目的を考える」ことが習慣化された組織は、このようにして、“本当にやらなくてはならない仕事”に集中していく組織に変わっていくのです。
p.52-3 強い「思い」を持って仕事をしていないということは、自分の守備範囲の責任を果たしていればとりあえず良しとすることにつながります。結局、相手を傷つけず、自分も傷つかない状態が最も望ましい、という事なかれ主義がはびこりやすくなってしまうのです。
p.60 ただ、問題は立場でものを言う、というのは事実よりも立場が優先される可能性があることを意味しています。言い換えれば事実よりも建て前を優先するということです。これに対し、立場を離れて、というのは立場に左右されず、事実に基づいて、という意味です。
p.72 「さばく」というのは、今ここだけなんとかやり過ごすこと。そして、「考える」というのは、「解決するのは簡単ではないけれど会社にとってより重要なこと」を考えることで生み出されてくる知恵で周りを巻き込み解決の行動に移っていくことです。だから、改革のためには、考えることが重要になってくるのです。
p.85 知恵を出す、というのは飛び抜けた料理を作るのと同じなのかもしれない。『そもそも』『なんのために』と考えて、しっかりとした土台を作ったうえで、あとは右脳で飛躍する。
p.88 「企業の目的は利中である」にはじまり、「マネジメントはかくあるべき」といった、「答えはこれでなくてはならない」的な、機械論的な決め付けをする傾向を少なからず持っていたのが日本的な経営の負の部分であった。
意味よりも形式が大切にされ、重要か否かよりも手続きは正しいか、実効性よりも整合性が重んじられる傾向が強かったのは、この機械論的な形式主義のもたらした結果といっても言いすぎではないだろう。
p.89 今の日本企業に必要なものは、過去の経験知にとらわれたり、成功体験のあるビジネスモデルに固執することではない。また、ロジカルシンキングのような、「一見ありがたそうな方法論」を心奉することでもない。
今、本当に必要なのは、こうした便利な道具やスキルを「なんのために」使うのか、という問いかけをすることだろう。
なんのために仕事をするのか? 会社とは何をするためのものか? 仕事とはいったいなんなのか?
p.92 日本企業の「人材的体力」を弱めてきた本当の原因は、「手っ取り早く結果を追い求め続けていく」アングロサクソン的な経営姿勢のネガティブな側面のみを模倣したことにあると思われます。
p.95-6 優秀な本社スタッフをそろえた大企業でごく当たり前に見られるようになった光景とは、本社スタッフによって練り込まれた対応策をラインの管理職が徹底的に管理することで全社に実行させる「合理的な」経営スタイルです。
今まで当たり前と思われてきたこの仕事の仕方に、問題の本質が隠されています。すなわち、「目指すものは数値目標のみ。その結果、深く考えることをすっ飛ばし、ただひたすら頑張る」ことだけに価値を置いた、右肩上がりの時代の仕事の仕方そのものに問題を抱えていたにもかかわらず、それをそのままにして、ただ管理だけを強化し合理化する、という愚行を犯しているからです。
p.97 もちろん一方で、脱企業本位としての顧客志向、お客さま本位、という非常に大切な経営姿勢があらゆるところで強調される時代にはなってきています。しかし、物事を本質的に考える、という習慣を持たないままにこうした課題に取り組んでいくと、せっかくの理念も単なるきれいごとに終わります。
p.100 物事を深く考え抜くことのできる環境として欠かせないのが、問題の思惑に左右されたり、中身よりも形式を重視したりせず、何よりもあるがままの事実を大切にし、事実に基づいて問題解決ができる経営体質を作る、という経営の意思です。
p.101 経営が問題を解決するよりも不透明さを守ろうとするなら、当然のことですが考えることが経営にとってはネガティブな意味を持つことになってしまいます。
p.121-2 どんな仕事でもそうなのですが、一番の問題は、いつも仕事を右から左へと単に処理しているだけだと、さばくことが仕事、という感覚が身についてしまいます。
現実に起こっている重大な問題は、過去に経験したことのないケースの場合、本来は新しいスキルが必要で、さばくことなどできないはずなのに、考える習慣そのものがないため、無意識のうちにさばいてしまう、という仕事の仕方です。処理するスキルが身についていないのに、さばけるはずのないものをさばいてしまうと当然問題が起こります。
p.132-3 総論(方針)として正しい答えを出すことは可能であっても、お客さまと直接接している現場が、お客さまとの関わりの中でしなくてはならない判断(各論)としての適切な答えを与え続けることは不可能だ、ということです。したがって、いつも指示を待つ、という姿勢で仕事がなされているとしたら、指示された答えが適切ではないという事態が頻繁に起こるのです。
p.134 考える力をなくしてしまった結果、それが仕事のやりがいの有無とか、働きがいなどにもきわめて大きな影響を及ぼすということです。
なぜならば、仕事を通して自分が成長をしている、という実感を持つことができて、初めて人は働きがいを感じるものだからです。考える力をなくしつつある人間が、自分の成長を感じる可能性は小さいでしょう。
p.137 必ずしも正解があるとは限らない。言い換えれば「ひとつの正しい答えがある」という前提そのものに「?」をつけるべき時代だからこそ、意味や目的を徹底的に考え抜く「考える力」が磨くアンテナが必要なのです。
100年に一度の危機は、実は大きなチャンス、企業の体質を「ただ何も考えずに仕事をさばくことをよしとする体質」から「対応力を育んでいく体質」に変えていくのです。
p.156 自分自身の役割を「コマ」としてしか認識していない人は、管理職になっても、果ては役員になっても与えられた職務をひたすらこなすことに精いっぱいで、「自分が将棋指しになり得る」などということは考えたこともないのです。
p.157 優秀と言われている人の中にも、エネルギー(情熱)のある人と、ない人がいます。物事に対する関心が強く、物事を深く突き詰めて「なんのために」「どういう意味があるのか」などを考え抜く、という傾向を持つ人は、自分が持っている使命感から発想しますから、問題解決に立ち向かう、より大きなエネルギー(先を見ようとする力)を持っていることが多いのです。
p.159 意味とか目的とは無関係に仕事をしていることに何の違和感も感じない人だけが集まって仕事をしたとしても、決められた役割、与えられた制約条件の範囲内でうまくこなすだけで仕事は終わります。チームにはなっていない、ということです。
仕事に関心が持てなくて、深く考える姿勢を持っていないと、どうしてもさばき仕事、対症療法的にならざるを得ないため、問題は先送りしていきます。さばき仕事というのは、本来の目的がどこかに行ってしまって、手段が目的になってしまっている状態。
p.162-3 ビジネスモデルが安定している時代には、指示さえしっかりしていれば、あとは動いていきました。ところが、このビジネスモデルが陳腐化し、新たなビジネスモデルが必要な段階になると、新しい経営の方向性を示すだけでは機能しません。現場に近いところでの具体的な各論が求められるようになります。
p.169 現状とは無関係にまず「どうありたいか」を考えることからはじめると、現状とは非連続的な「ありたい姿」が浮かんできます。もちろん、これは現状と比較してしまうと実現不可能なのですが、このありたい姿を目指すには何がネックになっているのかを考えるのです。ネックになっているものが現状での制約条件です。この制約条件をひとつずつ吟味していくのです。そうして、何が本質的な要因なのかが見えてくると、どこをブレークスルーすれば実現可能になるのかも、およそ見えてくるのです。
p.191 こうした価値観を基礎にチームとしての方向性をぶれなくさせるのが全体観の共有です。全体観を共有していることが、チームが実際に役に立つチームプレーをできるかどうか、ということを決定づけます。
ここで全体観と言っているのは、目的とか、なんのために、誰のために、どこに向かってどういう価値を提供していくか、というようなことを共有していることです。
p.1-2 最近の企業の人材育成方針はどの企業を見ても、「自発性とか自主性をどう引き出すか」が主要テーマになっています。掛け声ばかりは威勢が良いけど実態はまったくと言ってよいほど伴っていないのが現状です。何が欠けているのでしょう。その答えとは「考える力」を引き出す努力です。
p.2 社長はお客様本位を熱心に唱えているのに、営業本部長は「そんなきれいごとで飯が食えるか」と、本心では苦々しく思いながらも表向きは社長の言うことに付き合っている、というような状況です。こうした企業では“お客様に親切にすることがお客様本位だ”と、薄っぺらにお客様本位というものを捉えているケースが多いようです。特に物事を形式的にこなすのが得意な大手企業には、この傾向が強い。
その結果、お客様に親切にする負担は、一方的に現場に「しなくてはならない努力」という形で押し付けられています。単にお客様に表面的に親切にするとか喜んでもらうだけのお客様本位は、当然、業績とは連動していきません。ただ押し付けられるだけでは知恵も本当の意味でのやる気も出てこないからです。でも、儲からないと飯は食えませんから、結局、お客様本位などときれいごとばかり言ってはいられなくなります。そこで、月初はお客様本位を唱え、月末になると数字で締め付ける、といったちぐはぐなことが起こるのです。
p.29 次世代を担うはずの経営人材には、特にしっかりとした「考える力」が不可欠です。仕事をこなす力ではなく、その意味や目的を要所要所で問い直す姿勢と、事実にもとづくいて現状を把握し、制約を外して問題点を考え抜く、という姿勢がなくては不確実な時代の経営の舵取りはできない、と思えるからです。
p.30-1 物事をとにかく先に進めることばかりに目がいっている人がほとんどで、「なんのために」とか、「この仕事にどういう意味があるのか」などを常に問い直しながら展開していく力を持っている人は現代の経営においては間違いなく少数派です。
しかし、本来、成長する企業の経営者というのは、そうした本質的な問いかけを自らに課しているものです。
p.33-4 現実の多くの仕事では、三人部下がいる場合、能力のある三人と、能力のない三人とでは、パフォーマンスがまったく異なる・・・、にもかかわらず従来からある常識的な見方では、基本的に人間のクオリティはカウントせず、すべて「員数」で見るという傾向があったのです。
こうしたものの見方の持つ一番の問題点は、物事や出来事の価値、質、その持っている意味などを、思考の対象から外してしまうところにあります。質ではなく数えやすい量が重視され、中身ではなく、形式が大切にされます。
物事の価値や意味、つまり「なんのために」「どういう意味があるのか」を問う姿勢も後ろに追いやられ、いつの間にか「どうやればいいのか」「どうやると効率的か」しか考えなくなってしまうのです。
ひたすら目先の利益の最大化だけを追い求め、そのことの意味や価値を問わず、「どうやるか」しか考えないとするなら、環境激変時の対応策にしても、何がそうなったかは問いませんから、どうしてもモグラ叩き敵なアイデアしか浮かんでこなくなってしまうのです。
経営品質にしても顧客本位主義にしても、本来はすばらしい考え方であるにもかかわらず、結局、多くが中身の伴わないスローガン倒れやきれいごとになってしまっているのはそうした理由からなのです。
p.35 「上司から言われたことを効率的にこなす」のが仕事だ、と思っているときは、「仕事を処理する」ことが、あたかも最終目的のようになっています。本来の目指すべき目的が意識されていないと、形を整えたらそれでよしとされます。
p.36 深く考えることが習慣化された組織になっていくと、目の前の仕事を処理することはあくまでも「手段」にすぎないことが見えてきます。自分たちのやっている仕事が社会にどういう影響を与えているのか、会社が果たすべき社会的な役割はなんなのだろう、という自らに対する問いかけが新たな「気づき」を生み出します。
p.37 「目的を考える」ことが習慣化された組織は、このようにして、“本当にやらなくてはならない仕事”に集中していく組織に変わっていくのです。
p.52-3 強い「思い」を持って仕事をしていないということは、自分の守備範囲の責任を果たしていればとりあえず良しとすることにつながります。結局、相手を傷つけず、自分も傷つかない状態が最も望ましい、という事なかれ主義がはびこりやすくなってしまうのです。
p.60 ただ、問題は立場でものを言う、というのは事実よりも立場が優先される可能性があることを意味しています。言い換えれば事実よりも建て前を優先するということです。これに対し、立場を離れて、というのは立場に左右されず、事実に基づいて、という意味です。
p.72 「さばく」というのは、今ここだけなんとかやり過ごすこと。そして、「考える」というのは、「解決するのは簡単ではないけれど会社にとってより重要なこと」を考えることで生み出されてくる知恵で周りを巻き込み解決の行動に移っていくことです。だから、改革のためには、考えることが重要になってくるのです。
p.85 知恵を出す、というのは飛び抜けた料理を作るのと同じなのかもしれない。『そもそも』『なんのために』と考えて、しっかりとした土台を作ったうえで、あとは右脳で飛躍する。
p.88 「企業の目的は利中である」にはじまり、「マネジメントはかくあるべき」といった、「答えはこれでなくてはならない」的な、機械論的な決め付けをする傾向を少なからず持っていたのが日本的な経営の負の部分であった。
意味よりも形式が大切にされ、重要か否かよりも手続きは正しいか、実効性よりも整合性が重んじられる傾向が強かったのは、この機械論的な形式主義のもたらした結果といっても言いすぎではないだろう。
p.89 今の日本企業に必要なものは、過去の経験知にとらわれたり、成功体験のあるビジネスモデルに固執することではない。また、ロジカルシンキングのような、「一見ありがたそうな方法論」を心奉することでもない。
今、本当に必要なのは、こうした便利な道具やスキルを「なんのために」使うのか、という問いかけをすることだろう。
なんのために仕事をするのか? 会社とは何をするためのものか? 仕事とはいったいなんなのか?
p.92 日本企業の「人材的体力」を弱めてきた本当の原因は、「手っ取り早く結果を追い求め続けていく」アングロサクソン的な経営姿勢のネガティブな側面のみを模倣したことにあると思われます。
p.95-6 優秀な本社スタッフをそろえた大企業でごく当たり前に見られるようになった光景とは、本社スタッフによって練り込まれた対応策をラインの管理職が徹底的に管理することで全社に実行させる「合理的な」経営スタイルです。
今まで当たり前と思われてきたこの仕事の仕方に、問題の本質が隠されています。すなわち、「目指すものは数値目標のみ。その結果、深く考えることをすっ飛ばし、ただひたすら頑張る」ことだけに価値を置いた、右肩上がりの時代の仕事の仕方そのものに問題を抱えていたにもかかわらず、それをそのままにして、ただ管理だけを強化し合理化する、という愚行を犯しているからです。
p.97 もちろん一方で、脱企業本位としての顧客志向、お客さま本位、という非常に大切な経営姿勢があらゆるところで強調される時代にはなってきています。しかし、物事を本質的に考える、という習慣を持たないままにこうした課題に取り組んでいくと、せっかくの理念も単なるきれいごとに終わります。
p.100 物事を深く考え抜くことのできる環境として欠かせないのが、問題の思惑に左右されたり、中身よりも形式を重視したりせず、何よりもあるがままの事実を大切にし、事実に基づいて問題解決ができる経営体質を作る、という経営の意思です。
p.101 経営が問題を解決するよりも不透明さを守ろうとするなら、当然のことですが考えることが経営にとってはネガティブな意味を持つことになってしまいます。
p.121-2 どんな仕事でもそうなのですが、一番の問題は、いつも仕事を右から左へと単に処理しているだけだと、さばくことが仕事、という感覚が身についてしまいます。
現実に起こっている重大な問題は、過去に経験したことのないケースの場合、本来は新しいスキルが必要で、さばくことなどできないはずなのに、考える習慣そのものがないため、無意識のうちにさばいてしまう、という仕事の仕方です。処理するスキルが身についていないのに、さばけるはずのないものをさばいてしまうと当然問題が起こります。
p.132-3 総論(方針)として正しい答えを出すことは可能であっても、お客さまと直接接している現場が、お客さまとの関わりの中でしなくてはならない判断(各論)としての適切な答えを与え続けることは不可能だ、ということです。したがって、いつも指示を待つ、という姿勢で仕事がなされているとしたら、指示された答えが適切ではないという事態が頻繁に起こるのです。
p.134 考える力をなくしてしまった結果、それが仕事のやりがいの有無とか、働きがいなどにもきわめて大きな影響を及ぼすということです。
なぜならば、仕事を通して自分が成長をしている、という実感を持つことができて、初めて人は働きがいを感じるものだからです。考える力をなくしつつある人間が、自分の成長を感じる可能性は小さいでしょう。
p.137 必ずしも正解があるとは限らない。言い換えれば「ひとつの正しい答えがある」という前提そのものに「?」をつけるべき時代だからこそ、意味や目的を徹底的に考え抜く「考える力」が磨くアンテナが必要なのです。
100年に一度の危機は、実は大きなチャンス、企業の体質を「ただ何も考えずに仕事をさばくことをよしとする体質」から「対応力を育んでいく体質」に変えていくのです。
p.156 自分自身の役割を「コマ」としてしか認識していない人は、管理職になっても、果ては役員になっても与えられた職務をひたすらこなすことに精いっぱいで、「自分が将棋指しになり得る」などということは考えたこともないのです。
p.157 優秀と言われている人の中にも、エネルギー(情熱)のある人と、ない人がいます。物事に対する関心が強く、物事を深く突き詰めて「なんのために」「どういう意味があるのか」などを考え抜く、という傾向を持つ人は、自分が持っている使命感から発想しますから、問題解決に立ち向かう、より大きなエネルギー(先を見ようとする力)を持っていることが多いのです。
p.159 意味とか目的とは無関係に仕事をしていることに何の違和感も感じない人だけが集まって仕事をしたとしても、決められた役割、与えられた制約条件の範囲内でうまくこなすだけで仕事は終わります。チームにはなっていない、ということです。
仕事に関心が持てなくて、深く考える姿勢を持っていないと、どうしてもさばき仕事、対症療法的にならざるを得ないため、問題は先送りしていきます。さばき仕事というのは、本来の目的がどこかに行ってしまって、手段が目的になってしまっている状態。
p.162-3 ビジネスモデルが安定している時代には、指示さえしっかりしていれば、あとは動いていきました。ところが、このビジネスモデルが陳腐化し、新たなビジネスモデルが必要な段階になると、新しい経営の方向性を示すだけでは機能しません。現場に近いところでの具体的な各論が求められるようになります。
p.169 現状とは無関係にまず「どうありたいか」を考えることからはじめると、現状とは非連続的な「ありたい姿」が浮かんできます。もちろん、これは現状と比較してしまうと実現不可能なのですが、このありたい姿を目指すには何がネックになっているのかを考えるのです。ネックになっているものが現状での制約条件です。この制約条件をひとつずつ吟味していくのです。そうして、何が本質的な要因なのかが見えてくると、どこをブレークスルーすれば実現可能になるのかも、およそ見えてくるのです。
p.191 こうした価値観を基礎にチームとしての方向性をぶれなくさせるのが全体観の共有です。全体観を共有していることが、チームが実際に役に立つチームプレーをできるかどうか、ということを決定づけます。
ここで全体観と言っているのは、目的とか、なんのために、誰のために、どこに向かってどういう価値を提供していくか、というようなことを共有していることです。











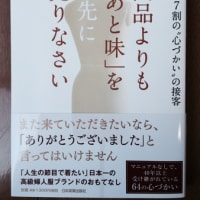

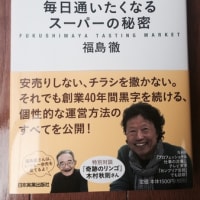

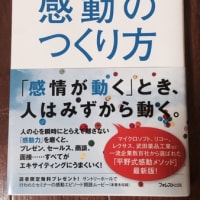

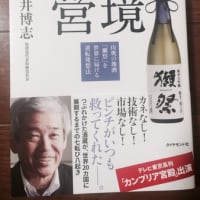
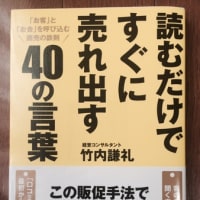






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます