 9月30日に聴いたハーゲンカルテットの感想を。
9月30日に聴いたハーゲンカルテットの感想を。現代の代表的な名カルテットである彼らの演奏を聴くのは、実に7年ぶりです。
前回2001年の時は、ベルク「抒情組曲」&ベートーヴェンの13番変ロ長調というプロでした。
今回は、モーツァルトとドボルザークというオーソドックスな感触をもった曲を最初と最後に持ってきて、真ん中には一筋縄ではいかないラヴェルを配しています。
この日の席は、2列めのほぼセンター。
室内楽のまろやかな響きという点では少し前すぎるかもしれませんが、音楽をアクティヴに聴こうとする場合はうってつけの席だと思います。
また、奏者の呼吸を肌で感じることができるので、私には大変好ましい席でした。
<日時>2008年9月30日(火)19:00開演
<会場>浜離宮朝日ホール
<曲目>
■モーツアルト:弦楽四重奏曲第16番 変ホ長調 K.428
■ラヴェル:弦楽四重奏曲 ヘ長調
■ドボルザーク:弦楽四重奏曲第14番 変イ長調 Op.105
(アンコール)
■ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第11番「セリオーソ」から第1楽章
<演奏>
ハーゲン弦楽四重奏団
■ルーカス・ハーゲン(第1バイオリン)
■ライナー・シュミット(第2バイオリン)
■ヴェロニカ・ハーゲン(ビオラ)
■クレメンス・ハーゲン(チェロ)
モーツァルトもドボルザークももちろん良かったのですが、とくに面白く聴かせてもらったのが、さきほど「一筋縄ではいかない」と申し上げたラヴェル。
春のやわらかな光を感じさせる幸福感に満ちた第1楽章冒頭から、絶えず音楽は変化していきます。
緊張感を増しながら、いざクライマックスだと思って気合いを入れた瞬間に、ふわりと体をかわされて地面に落されてしまう。
そんなことを何度か繰り返しているうちに、いつの間にか最初のテーマが現われ、「あー、最初に戻った」と思って安心していると、今度は違う景色を見せられている。
この楽章は、こんなパターンの連続です。
まさにラヴェル・マジックと呼びたくなるような音楽ですが、ハーゲンカルテットは、このあたりの表現が実に上手い。
第2楽章の、ピチカートの弾けるような勢いと中間部の気だるい雰囲気の対比も、これまた絶妙。
濃密で沈み込むような歌が深く心に残る第3楽章を経て、終楽章はまさに圧倒的なテクニックで一気呵成にゴールまで突っ走ってくれました。
ブラーヴォ、ブラーヴォ!
緊密なアンサンブルと研ぎ澄まされた感性、そしてたぐい稀なを色彩感覚をもった彼らにとって、まさにぴったりの音楽だったのでしょう。
このカルテットは、ルーカスとクレメンスが逞しい骨格を作り、ヴェロニカとライナー・シュミットが微妙な色調の変化を与えながら、独特の緊張感をもった生気あふれる音楽を作り上げるところに特色があります。
造形感覚の高さも特筆ものでしょう。
この日は、とくにヴェロニカ・ハーゲンのヴィオラが、アンサンブルにしなやかさと瑞々しい情感をもたらしていて、大きな感銘を受けました。
ハーゲンカルテットは、メンバー全員が40歳代ということですから、今後まだまだ年代物のワインのように熟成していくことでしょう。
5年後、10年後にどのような変貌を遂げているか、本当に楽しみです。










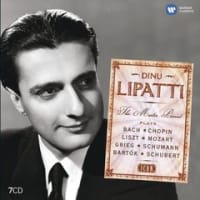
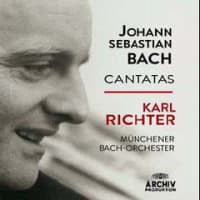

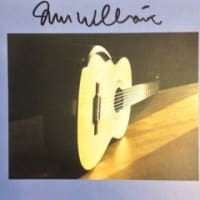

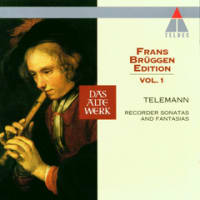
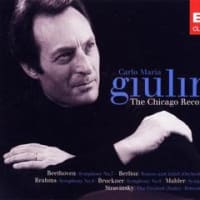
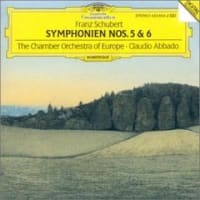
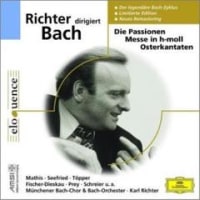
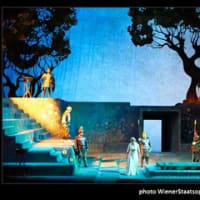





同じ空間で同じ演奏を楽しんでいたのですね(^^
しかも2列目まで同じです(笑・私は右側でしたが・・・)
今までCDで聴いていたかぎりでは、室内楽がこれほどパワフルだとは思ってもいませんでした。という演奏で本当に感動しました。。
おっしゃるとおり5年後、10年後の彼らの演奏を是非聴いてみたいものですね。
いやー、それにしてもお会いしたかったです(^^;
驚きました。
数メートルの距離をおいて、聴かれていたのですね。
でも、演奏は素晴らしかったですね。
室内楽らしいというよりは、触れば火傷しそうなくらいの熱さも感じられるコンサートでした。
今度はぜひご一緒しましょう。
ありがとうございました。
幸せに包まれた時間でした~
大スキなカルテットです
ようこそおいでくださいました。
3列目でお聴きになっておられたのですね。
このカルテットはウィーンやベルリン、イタリアといった「土」に根ざした香りで勝負するのではなく、もっとインターナショナルなスタイルでまっすぐに迫って来るところが、大いに気に行っています。
次回も本当に楽しみです。
これからも、どうぞよろしくお願いいたします。