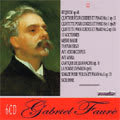
昨夜2泊3日の出張から帰ってきました。
それにしても最近は出張が多いなあ。今回は予想外に準備に手間どり、内容的にもハードな出張になってしまいましたが、何とか終わりほっとしているところです。
旅先のホテルで、そんなくたびれた頭と身体を慰めてくれたのが、初めて聴くこのフォーレの合唱曲でした。実はこのディスク、安さに惹かれて買ったフォーレの作品集(6枚組)の中の1枚だったのです。
<曲目と演奏者>
ガブリエル フォーレ作曲
■小ミサ曲
ミシェル・ピクマル指揮
ピクマル・ヴォーカル・アンサンブル
■タントゥム・エルゴ
■アヴェ・ヴェルム・コルプス Op.65-1
■タントゥム・エルゴ Op.65-2
■アヴェ・マリア Op.93
■ヴィレルヴィル漁夫協会のためのミサ(メサジェとの合作)
・キリエ
・グロリア
・サンクトゥス
・オ・サルタリス
・アニュス・デイ
■ラシーヌ賛歌 Op.11
クロード・トンプソン指揮
トリス・リヴィエレ合唱団
大して期待もしないで、例によって愛用のipodで聴き始めました。
ところがどっこい。何という美しさ!これは尋常ではありません。
とくに感動したのが、「ヴィレルヴィル漁夫協会のためのミサ」です。
この曲は、1881年にメサジェとの共作という形で書かれ、ノルマンディ地方にあるヴィレルヴィルの教会で初演されたそうです。
曲は5曲で構成されていますが、メサジェが「キリエ」「オ・サルタリス」を、フォーレが「グロリア」「サンクトゥス」「アニュス・デイ」を担当しています。
メサジェは1853年生まれの作曲家・指揮者で、フォーレやサンサーンスにも師事しています。興味深いことに、フォーレとはピアノ4手のための「バイロイトの思い出」というワーグナー風刺の曲も共作しています。
話が横にそれてしまいました。
メサジェ作とされる冒頭の「キリエ」から、魂が浄化されるような美しさです。
コーラスに絡むヴァイオリンが、チェロが、オーボエが、クラリネットが、ほんとにため息がでるような美しい調べを聴かせてくれます。
続く「グロリア」は東洋的な懐かしい響きを運んでくれるし、「サンクトゥス」、「オ・サルタリス」は清らかな美しさが際立っています。最後の「アニュス・デイ」は高貴なまでの美しさが、まるでチャイコフスキーのアンダンテ・カンタービレのようです。
とても素敵な曲と出会うことができました。
演奏も決して派手さはないけど、どこまでも暖かく、聴き進むうちに目頭が熱くなってきます。
ちなみに、フォーレはこの曲をベースに、新たに自分で「キリエ」を書き加え、「グロリア」を「ベネディクトゥス」にアレンジし、「小ミサ曲」を作っていますが、それがディスク冒頭の曲です。
一方、このディスクの最後には名作「ラシーヌ賛歌」が収められています。
いつもお世話になっているyurikamomeさんが、亡き本田美奈子さんに捧げると仰っていたあの曲です。
弦楽四重奏(コントラバスも入っている?)をバックに歌われるコーラスの何と純粋で美しいこと!天上の響きといっても差し支えありません。
私が今まで聴いてきたラシーヌ賛歌の中で、最高の演奏でした。
でも、こんなフォーレの音楽を続けて聴いていると、うっかり向こうの世界へ引き込まれそうになるくらいの危うさを感じました。
あぶない、あぶない・・・。
最後に、この6枚組のアルバムには、フォーレ弾きとして名高い女流ピアニストのジェルメーヌ・ティッサン=ヴァランタンのノクターン集(新盤のほうです)や、彼女を中心とした室内楽、エミール・マルタン指揮のレクイエム等隠れた名演が多く収められています。今日その中の何枚かを聴きましたが、いずれも素晴らしい名演ぞろいでした。
値段のことは言いたくないですが、1,490円でこんな素敵な6枚のCDが手に入るんですから恵まれた時代かもしれません。
それにしても最近は出張が多いなあ。今回は予想外に準備に手間どり、内容的にもハードな出張になってしまいましたが、何とか終わりほっとしているところです。
旅先のホテルで、そんなくたびれた頭と身体を慰めてくれたのが、初めて聴くこのフォーレの合唱曲でした。実はこのディスク、安さに惹かれて買ったフォーレの作品集(6枚組)の中の1枚だったのです。
<曲目と演奏者>
ガブリエル フォーレ作曲
■小ミサ曲
ミシェル・ピクマル指揮
ピクマル・ヴォーカル・アンサンブル
■タントゥム・エルゴ
■アヴェ・ヴェルム・コルプス Op.65-1
■タントゥム・エルゴ Op.65-2
■アヴェ・マリア Op.93
■ヴィレルヴィル漁夫協会のためのミサ(メサジェとの合作)
・キリエ
・グロリア
・サンクトゥス
・オ・サルタリス
・アニュス・デイ
■ラシーヌ賛歌 Op.11
クロード・トンプソン指揮
トリス・リヴィエレ合唱団
大して期待もしないで、例によって愛用のipodで聴き始めました。
ところがどっこい。何という美しさ!これは尋常ではありません。
とくに感動したのが、「ヴィレルヴィル漁夫協会のためのミサ」です。
この曲は、1881年にメサジェとの共作という形で書かれ、ノルマンディ地方にあるヴィレルヴィルの教会で初演されたそうです。
曲は5曲で構成されていますが、メサジェが「キリエ」「オ・サルタリス」を、フォーレが「グロリア」「サンクトゥス」「アニュス・デイ」を担当しています。
メサジェは1853年生まれの作曲家・指揮者で、フォーレやサンサーンスにも師事しています。興味深いことに、フォーレとはピアノ4手のための「バイロイトの思い出」というワーグナー風刺の曲も共作しています。
話が横にそれてしまいました。
メサジェ作とされる冒頭の「キリエ」から、魂が浄化されるような美しさです。
コーラスに絡むヴァイオリンが、チェロが、オーボエが、クラリネットが、ほんとにため息がでるような美しい調べを聴かせてくれます。
続く「グロリア」は東洋的な懐かしい響きを運んでくれるし、「サンクトゥス」、「オ・サルタリス」は清らかな美しさが際立っています。最後の「アニュス・デイ」は高貴なまでの美しさが、まるでチャイコフスキーのアンダンテ・カンタービレのようです。
とても素敵な曲と出会うことができました。
演奏も決して派手さはないけど、どこまでも暖かく、聴き進むうちに目頭が熱くなってきます。
ちなみに、フォーレはこの曲をベースに、新たに自分で「キリエ」を書き加え、「グロリア」を「ベネディクトゥス」にアレンジし、「小ミサ曲」を作っていますが、それがディスク冒頭の曲です。
一方、このディスクの最後には名作「ラシーヌ賛歌」が収められています。
いつもお世話になっているyurikamomeさんが、亡き本田美奈子さんに捧げると仰っていたあの曲です。
弦楽四重奏(コントラバスも入っている?)をバックに歌われるコーラスの何と純粋で美しいこと!天上の響きといっても差し支えありません。
私が今まで聴いてきたラシーヌ賛歌の中で、最高の演奏でした。
でも、こんなフォーレの音楽を続けて聴いていると、うっかり向こうの世界へ引き込まれそうになるくらいの危うさを感じました。
あぶない、あぶない・・・。
最後に、この6枚組のアルバムには、フォーレ弾きとして名高い女流ピアニストのジェルメーヌ・ティッサン=ヴァランタンのノクターン集(新盤のほうです)や、彼女を中心とした室内楽、エミール・マルタン指揮のレクイエム等隠れた名演が多く収められています。今日その中の何枚かを聴きましたが、いずれも素晴らしい名演ぞろいでした。
値段のことは言いたくないですが、1,490円でこんな素敵な6枚のCDが手に入るんですから恵まれた時代かもしれません。










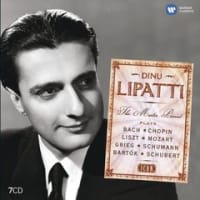
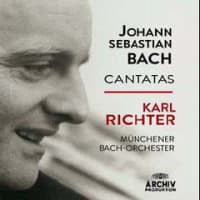

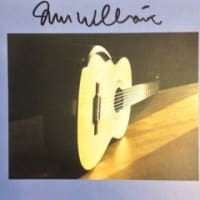

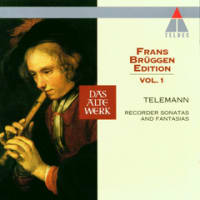
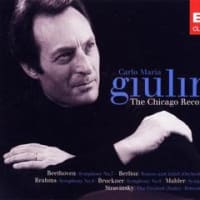
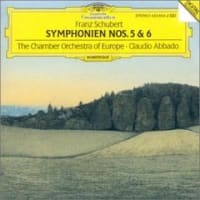
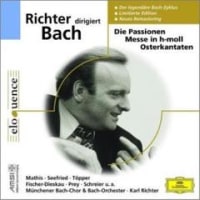
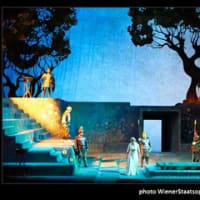






フォーレの透明感のある合唱曲は、何か安らぎをくれますね。私の期待するそういうアルバムのようですね。来週にでも私もHMVかタワー・レコードに行ってみることにします。
またの機会を心待ちにしております。。。
おはようございます。
>フォーレの透明感のある合唱曲は、何か安らぎをくれますね
全く同感です。昔LP時代にvoxの輸入盤を買って聴いたときのイメージによく似ていました。「手作りの木の香りがするような」そんな印象の演奏です。
P.S
このアルバムは、タワーレコードの特別企画のようなので、タワーレコードでしか販売していないかもしれません。
おはようございます。
こちらこそ、急な話で申し訳ありませんでした。また近いうちに是非お目にかかりたいです。オーマンディの106歳のお祝いもしなくちゃ!
楽しみにしております。
今日は仇に(?)フルネの「フォーレク」を買ってきました。これも素晴らしい!
こんばんは。
ネットの販売価格と店頭価格が若干違うことはよくありましたが、これだけ違うと問題ですよね。
でも、このアルバムお勧めです。
木の香りがする演奏ですよ。
是非ネットで入手されたらいかがでしょうか。
>興味深いことに、フォーレとはピアノ4手のための「バイロイトの思い出」というワーグナー風刺の曲も共作しています。
これ、「風刺」なんですかね?
日本ではフォーレはフランス音楽の精髄として捉えられ、そんな彼がワーグナーになど興味を示すはずがないとの認識が一般的なようですが、実はフォーレは外国旅行を趣味とし、メサジェを伴ってワーグナーの緒作品を度々鑑賞しているんですよ。ケルン、ロンドン、ミュンヒェン、そして「聖地」バイロイトにまで赴いて。
聖地の雰囲気を反芻しつつ『ニーベルングの指環』のライトモティーフで戯れるのは、ドビュッシーやオッフェンバックがやったような「風刺」とは異なるもののように思います。
コメントいただきありがとうございました。
なるほどと思いながら拝読させていただきました。
ただ、この曲については、何度聴いても私にはパロディにしか聴こえないんです。特に冒頭はどこかラグタイムのような印象すら感じてしまいます。
でも、ちょっと先入観もあるかもしれないので、もう一度聴いてみたいと思います。
真夏の盛りに暑苦しい文章を書きますが、ご容赦ください。
『バイロイトの思い出』の少し後に、シャブリエが今度は『トリスタンとイゾルデ』のライトモティーフを用いた『ミュンヘンの想い出(Souvenirs de Munich)』という曲も書いておりますね。
さて、この曲に諧謔の色が濃いのは確かですが、曲調がパロディックであることが直ちに原曲への“諷刺”に結び付くかというと、それはちょっと待ってほしいと思うのです。
結局、他の作曲家の引用によって作られた曲が原曲への“諷刺”であるか、それとも“オマージュ”であるかは、原作曲家に対する思いを知らなければ判断は不可能ではないでしょうか。
フォーレとメサジェの外遊では、かの大作『ニーベルングの指環』全4作を2回も観ています。
仮にこれが諷刺曲を書くための素材集めに過ぎないとすれば、フォーレという人は随分と暇人、いやマゾヒストなんだなあと言わざるを得ませんが、それは納得できないでしょう?(続きます)
殊に日本語のWeb空間ではフォーレがサン・サーンスに音楽の手解きを受けて以来ワーグナーを愛好していたことに言及する文章は少なく、それはWikipediaの英語版(すみませんがフランス語は読めません)と日本語版の情報の質と量の格差にも表れています。
例えば、Wikipedia英語版のフォーレの項にはこうあります、
Fauré admired Wagner and had a detailed knowledge of his music, but he was one of the few composers of his generation not to come under Wagner's musical influence.
然るに日本語版では前半部分に相当する記述を欠き、後半部分のフォーレはワーグナーの音楽からは超然としていたという部分だけが書かれています。
勿論、誰を好んで誰を嫌うのは個人の自由ですが、音楽の歴史を語るときにも個人的好悪で目が曇り、読む人に先入観を与えることは好ましくないのではと思います。