思いがけないことは、本当に突然やってくるものだ。
今日一日、出張先でどんな話をしたか、あまり良く覚えていない。
今は詳しく書けないけど、このことについては、いつかまた機会をみて書かせていただきたいと思う。
さて、一昨日は大好きなグリモーのコンサートをサントリーホールで聴いた。
プログラムは、前回ご紹介させていただいたCDと全く同じ曲目・同じ順番。
 ☆エレーヌ・グリモー ピアノ・リサイタル
☆エレーヌ・グリモー ピアノ・リサイタル
<日時>2011年1月17日(月)19:00開演
<会場>サントリーホール
<曲目>
■モーツァルト:ピアノ・ソナタ第8番 イ短調 K.310
■ベルク:ピアノ・ソナタ op.1
■リスト:ピアノ・ソナタ ロ短調
■バルトーク:ルーマニア民族舞曲
(アンコール)
■グルック:精霊の踊り
■ショパン:3つの新しい練習曲 ヘ短調
全体の演奏スタイルは、(予想されたことではあるが)CDとまったく同じ。
しかし、この日グリモーと同じ空間・時間を共有することで、彼女の意図するところが一層鮮烈なメッセージとして伝わってきた。
ひとことで印象を書いてしまうと、彼女は他のどんなピアニストにも似ていない。
「一流ピアニストは、皆そうだ」と言われたら返す言葉もないが、グリモーの歩んでいる道には先人がいない。
そんな思いを、強く印象付けられたコンサートだった。
モーツァルトは、やっぱり草書体。
しかし、グリモーの草書は、軽く柔らかなタッチのそれとは対極にある。
嵐が吹き荒れるような力と、火傷しそうな熱さをもった草書だ。
CDでは可憐なロンドのように聴こえた第3楽章も、この日の演奏では激情のロンドだった。
こんなK.310は聴いたことがない。
グリモーの眼は、モーツァルトではなく、明らかにベートーヴェン(あるいはそれ以降)を見据えていたと思う。
私の想い描くK.310とはまるで違うが、ここまで己の信ずるところを見せつけられると、やはり納得するしかない。
続くベルクはCDでも文句なしの名演だったが、この日の演奏はさらに一段上をいっていた。
こんな魅力的なベルクを弾ける人は、本当に少ないのではないかしら。
この曲だけグリモーは譜面を見て演奏していたが、なんら違和感を感じさせることはなかった。
ブラーヴォ!
休憩をはさんで聴かせてくれたリストのソナタが、この日のクライマックス。
最初の音がやや乾いた音で、どちらかというと無機的に響く。
それが、曲が進み演奏に熱を帯びてくると、どんどん生々しい響きに変わっていく。
とくに後半は、息を継ぐ間もないほど強烈なインパクトを持った演奏だった。
こんな演奏を聴かされたら、聴き手はたまらない。
このリストでコンサートが終わっていたら、私はしばらく客席から立ち上がれなかったかもしれない。
次のバルトークの闊達な音楽のおかげで、かろうじて精神の均衡を回復できたように思う。
それにしても凄い演奏だった。
前回来日時にパーヴォ・ヤルヴィと組んで聴かせてくれた「皇帝」も本当に素晴らしかったけど、今回の演奏は、またまた大きく変貌をとげていた。
今後、エレーヌさまは、どんな道を開拓するんだろう。
ただひとつ確信できることは、中途半端なことは絶対しないであろうということ。
「妥協」だとか「中庸」なんて言葉は、おそらく彼女の辞書にないはず。
次回のコンサートが、今から本当に楽しみだ。
それから、この日はホールで何人かの音楽仲間にお目にかかることができた。
そして、終演後にプチ新年会?で遅くまでお付き合いいただいたminamina様とやだもん様には、心から感謝いたします。
あっという間に焼酎のボトルが空になってしまいましたが、無事にお帰りになられたでしょうか。
新年の最初の月からこんな衝撃的なコンサートに出会えて、今年はおみくじ通り「大吉」かも。
今日一日、出張先でどんな話をしたか、あまり良く覚えていない。
今は詳しく書けないけど、このことについては、いつかまた機会をみて書かせていただきたいと思う。
さて、一昨日は大好きなグリモーのコンサートをサントリーホールで聴いた。
プログラムは、前回ご紹介させていただいたCDと全く同じ曲目・同じ順番。
 ☆エレーヌ・グリモー ピアノ・リサイタル
☆エレーヌ・グリモー ピアノ・リサイタル<日時>2011年1月17日(月)19:00開演
<会場>サントリーホール
<曲目>
■モーツァルト:ピアノ・ソナタ第8番 イ短調 K.310
■ベルク:ピアノ・ソナタ op.1
■リスト:ピアノ・ソナタ ロ短調
■バルトーク:ルーマニア民族舞曲
(アンコール)
■グルック:精霊の踊り
■ショパン:3つの新しい練習曲 ヘ短調
全体の演奏スタイルは、(予想されたことではあるが)CDとまったく同じ。
しかし、この日グリモーと同じ空間・時間を共有することで、彼女の意図するところが一層鮮烈なメッセージとして伝わってきた。
ひとことで印象を書いてしまうと、彼女は他のどんなピアニストにも似ていない。
「一流ピアニストは、皆そうだ」と言われたら返す言葉もないが、グリモーの歩んでいる道には先人がいない。
そんな思いを、強く印象付けられたコンサートだった。
モーツァルトは、やっぱり草書体。
しかし、グリモーの草書は、軽く柔らかなタッチのそれとは対極にある。
嵐が吹き荒れるような力と、火傷しそうな熱さをもった草書だ。
CDでは可憐なロンドのように聴こえた第3楽章も、この日の演奏では激情のロンドだった。
こんなK.310は聴いたことがない。
グリモーの眼は、モーツァルトではなく、明らかにベートーヴェン(あるいはそれ以降)を見据えていたと思う。
私の想い描くK.310とはまるで違うが、ここまで己の信ずるところを見せつけられると、やはり納得するしかない。
続くベルクはCDでも文句なしの名演だったが、この日の演奏はさらに一段上をいっていた。
こんな魅力的なベルクを弾ける人は、本当に少ないのではないかしら。
この曲だけグリモーは譜面を見て演奏していたが、なんら違和感を感じさせることはなかった。
ブラーヴォ!
休憩をはさんで聴かせてくれたリストのソナタが、この日のクライマックス。
最初の音がやや乾いた音で、どちらかというと無機的に響く。
それが、曲が進み演奏に熱を帯びてくると、どんどん生々しい響きに変わっていく。
とくに後半は、息を継ぐ間もないほど強烈なインパクトを持った演奏だった。
こんな演奏を聴かされたら、聴き手はたまらない。
このリストでコンサートが終わっていたら、私はしばらく客席から立ち上がれなかったかもしれない。
次のバルトークの闊達な音楽のおかげで、かろうじて精神の均衡を回復できたように思う。
それにしても凄い演奏だった。
前回来日時にパーヴォ・ヤルヴィと組んで聴かせてくれた「皇帝」も本当に素晴らしかったけど、今回の演奏は、またまた大きく変貌をとげていた。
今後、エレーヌさまは、どんな道を開拓するんだろう。
ただひとつ確信できることは、中途半端なことは絶対しないであろうということ。
「妥協」だとか「中庸」なんて言葉は、おそらく彼女の辞書にないはず。
次回のコンサートが、今から本当に楽しみだ。
それから、この日はホールで何人かの音楽仲間にお目にかかることができた。
そして、終演後にプチ新年会?で遅くまでお付き合いいただいたminamina様とやだもん様には、心から感謝いたします。
あっという間に焼酎のボトルが空になってしまいましたが、無事にお帰りになられたでしょうか。
新年の最初の月からこんな衝撃的なコンサートに出会えて、今年はおみくじ通り「大吉」かも。










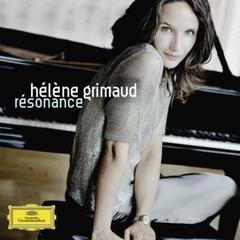 <曲目>
<曲目> 2011年の最初の週がようやく終わった。
2011年の最初の週がようやく終わった。 指揮を見ないで演じようとした男子学生に、小澤さんは注意する。
指揮を見ないで演じようとした男子学生に、小澤さんは注意する。 今日は、会社のメンバーたちと神田明神へ初詣に出かけた。
今日は、会社のメンバーたちと神田明神へ初詣に出かけた。 ニーノ・ロータ
ニーノ・ロータ 今年の初詣は、いつもと同じ氷川神社へ。
今年の初詣は、いつもと同じ氷川神社へ。 お酒もよく飲んだなぁ。
お酒もよく飲んだなぁ。 そして、本家フランスのシャンパンのほうは、この日のためにセラーでずっと寝かしていた「ジャック・セロス」。
そして、本家フランスのシャンパンのほうは、この日のためにセラーでずっと寝かしていた「ジャック・セロス」。 さて、新年最初に聴いた曲は、ブルッフのスコットランド幻想曲。
さて、新年最初に聴いた曲は、ブルッフのスコットランド幻想曲。





